2025年7月2日記者会見「路面電車駅前大橋ルートの開業について」
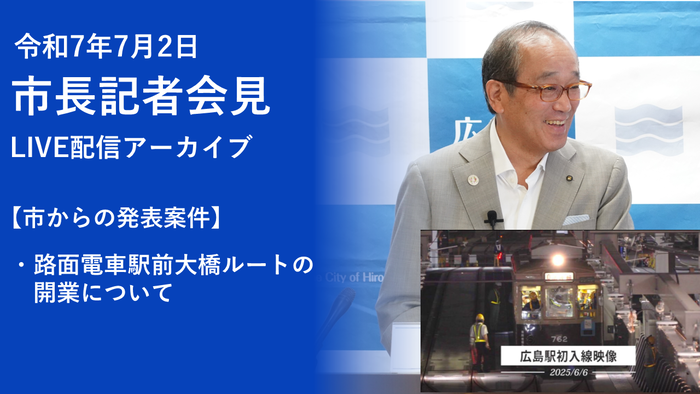
- 日時 令和7年(2025年)7月2日(水曜日)午前10時15分~午前11時00分
- 場所 市役所本庁舎11階第1会議室
市からの発表案件
路面電車駅前大橋ルートの開業について
本日は、JR西日本・広島電鉄・本市の三者相互協力のもとで進めておりますこの事業、広島駅南口広場の再整備等の大きな節目となります路面電車駅前大橋ルートの開業について、これまでの振り返りを含めて皆さんに紹介させていただきたいというふうに思います。
まず、こちらの動画を御覧いただきたいと思います。
(広島駅初入線映像)
見ていただきました動画は、駅ビルの2階に路面電車が初めて乗り入れた映像になっています。
5月末に駅前大橋ルートに関わる工事が概ね完了いたしまして、6月6日(金曜)深夜から試運転が始まりました。すでに新ルートを走っている車両を見られた方も多いんじゃないかなというふうに思うところであります。
ここから、事業をちょっと振り返ってみたいと思います。こちら、平成31年3月に「魅力的な空間・駅前の空間の整備方針」、この共同記者会見を開きまして、三者が連携して一体感のある魅力的な駅前空間を創出するということで、JR西日本の駅ビル建て替え計画の発表、そして、駅前大橋ルートの開業予定時期といったものを発表した場面であります。
令和2年4月からは、JR西日本が行う広島駅ビルの建替工事が開始されまして、これに伴って、本市においては広場の利用形態を変更するための工事、タクシー・バスエリアの利用停止といったことを行いました。
利用者の方々が長期にわたって不便になるということで、御不便をおかけいたしましたけれども、バスエリアについては令和6年6月に暫定利用開始、そして、タクシーエリアについては令和7年3月に利用を開始いたしました。
続いて、こちらの動画を御覧ください。
(駅前大橋橋りょうの架設工事の映像)
こちら、駅前大橋橋りょうの架設工事の記録となっております。
こちらの橋りょうの一部区間では、直下にあります駅前地下広場など、既存の構造物に影響を与えないよう橋脚を設けずに、盛土構造となっております。盛土の部分については軽量盛土材、いわゆる発泡スチロール製の材料を使用いたしまして、軽量化を図るなど技術的な工夫をしております。
また、擁壁部分は、新たにできるコンクリート製の構造物が周囲に圧迫感を与えないようにするために、それを軽減するような意匠性の高いデザインというふうになっております。
続いて、動画を御覧ください。
(稲荷町交差点の軌道ブロック設置工事の映像)
こちらは稲荷町の交差点の工事記録動画になっています。
令和5年10月中旬から約6か月の間に、夜間工事でレールの敷設工事を行っております。
線路の土台となる「軌道ブロック」といわれる材料を、大小約500個組み合わせて線路を繋げております。
また、令和7年3月には華やかに生まれ変わったJR新駅ビルの開業記念式典に出席いたしました。
三者が連携して進める広島駅南口の再開発プロジェクトの「一番手」といたしまして完成した、新駅ビル、ミナモアや、ホテル棟からは陽の光に輝いております瀬戸内海の水面(みなも)や、安芸の小富士似島、さらには遠くは宮島まで見渡すことができるすばらしい眺望に感激したところであります。
新駅ビルが新たな広島のにぎわいの拠点として多くの人が集い、憩い、そして交流する、その中心的な場となるんじゃないかなと強く感じたところであります。
こちらは先月6月1日になりますけれども、駅前大橋ルート高架区間、約260メートルを三者で確認して歩いた図であります。
新しい路線の高架部では、レールを特殊な樹脂で固定することによりまして、電車の振動、あるいは騒音を軽減いたしまして、乗車する方々の乗り心地や、周辺の環境に対して配慮したすばらしい技術が採用されることに感銘を受けました。
この場所から、開放的で魅力的な中央アトリウム空間に、路面電車が乗り入れるという、唯一無二の広島ならではの新たな景観ができ、国内外から広島を訪れた方々を魅了して、そして、地元の方々にとって誇りに思える広島プライドの一つになっていくんじゃないかというふうに思っています。
そして、今月の27日には、三者で開業前最後の確認を行います。
その後、8月2日に開業式典を行ったのちに、8月3日には、いよいよ駅前大橋ルートが開業となります。全国初の高架で駅ビルに乗り入れる路面電車、これを皆さんに御利用いただける日が、もう少しの間ということになりました。楽しみにお待ちいただけたらというふうに思います。
8月2日の開業式典でありますけれども、御覧のとおり現在計画しているところであります。この事業を支えていただきました国会議員・市議会議員・国土交通省・事業関係者、そして、地元町内会の方々などを招待いたしまして開催する予定にしております。今後、別途プレスリリースの予定であります。
そして、最後、こちらの動画を御覧ください。
(電車が駅前大橋を通過していく映像)
最後になりますけれども、この駅前大橋ルートの開業は紙屋町・八丁堀地区へのアクセスとともに、東西の核を中心とした広島都心全体の回遊性を向上させ、広島広域都市圏、ひいては中四国全体のにぎわいの創造につながる重要な事業のステップの一つでありますので、今後も三者で連携いたしまして、広島駅南口周辺の発展に取り組んでいきたいと考えているところであります。以上です。
記者
開業式が8月2日とあるんですが、この日は式典が終わったらそれで終わりで、その日はまだ乗れない。あくまでも開業は翌日3日という認識でよろしいでしょうか。
市長
はい、そのとおりです。分けて行います。
記者
今、試運転の段階ですけれども、市長は実際に乗られたりというのは、まだされていない。
市長
まだ乗っていません。
記者
この2日の日に乗られる感じですか。
市職員
昨日、7月1日付けでプレスリリースの方を、広島市・広電(広島電鉄)・JR(西日本)三者で、今後の報道機関向けのスケジュールについて、プレスリリースさせていただいています。その中で、メディアさんの試乗会ということで、7月27日をメディア向け試乗会の開催についてということで記載させていただきまして、今の予定では、この段階で市長の方も計画しております。
記者
改めてこの(駅前)大橋ルート、できることでの期待感と効果、もう少し詳しく教えていただければありがたいです。
市長
今、申し上げたとおりなんですけど、見ていただいても、いわゆる、乗り物が好きな方、マニアにとっても垂涎の的だというふうに言われているというのをよく聞きまして。都市部で、特に国内で坂道を上っていくような景色を形成する路面電車はないんだそうでありまして、路面電車が坂道を走っているという意味では、サンフランシスコの電車とかね。スペインとか、ポルトガル、あっちの方の坂道で、都市の中を抜けている電車があるじゃないですか。ああいったイメージが、この広島の地で再生されるので、非常に興味があるとかっていうふうなことを言われる方が多いようでありますので、確かにそうなんだなというふうに思います。
私自身はそういった景色、出来上がった景色そのものをありがたいと思うんですけれども、先ほどの写真を見ていただいたように、まちづくりに関してそれに関する関係者が、三者が一緒になって同じ方向に向いて作業できたという、そのことにむしろ重きがあります。これからもまちづくりをやっていく上で、関係者の方々が同じ思いを持って、連携して仕事をしていくということをやっていけば、必ずいろいろなところで、これからのまちの発展に役立つような取組ができると思っています。
とりわけ、公共交通については、人口減少の社会の中で地域社会の方々の人とかモノ、それを移動循環型で活性化していくということが不可欠でありまして。そうすることで、そのまちの活力が生まれて、多くの方々を引きつけて、人口減少が進んだとしても多分、他の地域よりかは、この地域の愛着心を持っていただいて多くの方が住み続けるまちができるんじゃないかなと思うんですけれども。
そういった面での、ハード面での取組、機能面プラスそういったものに対する評価といいますかね、自分たちとして誇りに思えるようなまちづくりが進むということに関して、非常に感銘を受けているというものであります。とりわけ南口は、これから新幹線を通じて、九州方面、あるいは関西方面から来るお客さんが最初に乗り入れる場所で。そこで、こういったものを直接見ていただける、そのまちの構造が大きく変わって利便性も高まっている。先ほど申し上げたように循環型の機能も高まるということ、そのことを一切合切含めて、いいものができたんじゃないかなというふうに思っています。
記者
広島駅周辺というのは、ミナモアも含めて今大変にぎわっていることと思います。一方で紙屋町・八丁堀については西の核ともいわれているんですけれども、この辺りの現状について一部の地元の方とか商店主の方からは、少し沈滞化が進んでいるといったような嘆きも聞こえてきます。その辺りはどのように受け止めていらっしゃいますか。
市長
その沈滞化っていうのは、紙屋町・八丁堀の方?
そうですね。人間そうですけど、2人のライバル意識を持った方々がいろいろ活躍していてね。実力は同じようなんだけれども、あるとき何かの拍子で少し半歩なり一歩前に出ると、みんなの注目がそちらに集まると、その片方のライバルが、遅れたようなイメージになって、あちらばかり人気があるんだけど、あんたは大丈夫かというような人間の基本的な心理で頑張れという意味も込めて、頑張るぞという意味を込めて大丈夫かというような御意見が出るんですけれども。そういった状況を作りながらお互いに切磋琢磨して、この地域を活性化するという動機付け、そのための道具というか、機会にしてもらいたいと思うんですね。
その際、ライバルといいますけれども、私自身は、それぞれのまちの中での地政学的な位置付けなどをよく見ていただいて、自分たちの特色を生かしたまちづくりということに、これからしっかり注力していただければ、そちらに向けて行政としてもしっかり支援し、いわゆる特色のあるまちづくりをするということで、お互いが引き続き競い合うということをやってもらいたいと思うんですね。
今申し上げましたように、広島駅南口は、大阪とか九州とか、飛行機で来るとまた三原の方からやって来るということで、高速道路のつなぎで、ある意味で多くの外の方々を招き入れる第一の玄関。そしてそこで降り立って紙屋町・八丁堀は広島市内、もう少し広島というまちをしっかり見てみようかなというような方々を、さらに引き込む地域にするということと、日常生活の中で元々のデルタ市街地の中での中心街でありますから、地元の方々が慣れ親しんで自分たちの歴史とか文化というのを、楽しむようなことができるまちづくり、そういうふうにして、それぞれ特色を持たせて、そして、両方がいわば、平和都市広島の平和記念公園辺りに誘導するための途中の経過地点と、こういうふうな両方とも共通の機能を持たせながら、しかし迎え入れるときのまちづくりについては違うコンセプトで、取り組んでいただくようにするならば、それぞれがいい競争関係で、にぎやかなまちになっていくんじゃないかというふうに思うんですね。
ですから、今考えているのは駅前で多くの人が来たときに、平和公園に向かっていくときの紙屋町・八丁堀を通過するときに、例えば歴史の道とかという形で通っていただいて、そこを経過していくとか、西国街道をたどりながら商店街を通って抜けていくと。そういったときに、紙屋町・八丁堀という繁華街があると。そういったつくりになるように、またそれが言葉じゃなくて体験談で、あるいは見て分かるようなまちづくりができればなというふうに実は思っています。そして、そういう意味で全てを通じていわゆるウォーカブルな、自分たちの足でもって回れるまちというものを目指せたらなというふうに思っています。
その他の質問
中東情勢とトランプ(米国)大統領の発言について
記者
6月25日にトランプ大統領が、イランの核施設の攻撃のことを「原爆の投下と本質的には一緒だ」というような発言をされましたけれども、市長の受け止めを聞かせてください。
市長
まずもって大前提ですけれども、被爆者の平和への願い、「ヒロシマの心」というふうに言っていますけれども、それを世界中に広めて、あらゆる暴力をまず否定すると、あってはならないと。そして平和文化を振興していこうということ。その中で、市民生活の安寧が確保されるような平和な国際社会の実現に資する環境づくりをやっていこうという立場にある本市でありますから、そんな中で中東情勢が悪化していく、そして罪のない一般市民がどんどん犠牲になるということ、これはあってはならないことじゃないかなと思っていまして、このために長崎市とも一緒になっていろいろ行動をしているんですね。
今回はそういった視点で、平和首長会議共同アピールという形で、その思いを発出させてもらいました。これは、ある意味でいろんな行為、罪を憎んで人を憎まず、そういう行為そのものをやめていただくということ、特定の人じゃなく為政者レベルでそういったことをという気持ちを込めて、全ての為政者に対して暴力行為に依存することなく、理性的で平和的な外交によって、国家間の問題を解決してくださいというふうに訴えています。いわば暴力行為を通じて物事がいったん沈静化したというふうな発想、あるいはそうした発言をされるというのは、自分たちの経験でもそうですけれど、一過性で終わるんですよね。結局、暴力を振るわれて犠牲になった方は、そのときには自らの身を守るために萎縮して行為を停止するかも分からないけれども、冷静に考えてまた仕返しをしようとかしていって、かえって長期化する、争いの長期化を招く要因にもなりかねないじゃないですか。そういう意味で、全ての為政者に対して暴力行為に依存するんじゃなくて、平和的な外交努力をやっていただきたいというふうに言ったところであります。
そういう意味で改めて、この度の米国大統領の発言については、原爆が一旦使用されると、敵味方の区別なく多くの無辜の市民の命を奪うだけでなく、人類の存続すら危うくするものであるということ、あるいはその被爆の実相を十分に理解されていないということじゃないかというふうにも思えるんですね。そういう意味で、そういう視点に立ってトランプ大統領にはぜひ被爆地を訪問して、被爆の実相、そしてヒロシマの心というものを一回、しっかり受け止めていただいた上で、発言していただければと思っています。
記者
市長がさっきおっしゃったように、被爆地を訪れてほしいということでしたけれども、何かトランプ大統領宛てに要請をするだとか、そういった予定はおありでしょうか。
市長
これは各国の代表に機会を捉えて来てくださいというふうに言っていますから、それをやったから来いというんじゃなくて、ずっと言い続けていることであります。ただ、しっかり区別しているのは8月6日という(平和記念)式典の日は、広島の(原爆で)犠牲になった方々の慰霊で、そういう祈りをやる、祈りを捧げる日というふうにしていますから、そこについて来てくださいというんじゃなくて、それはこういったことをやるからそれを理解する方は、来てくださいというメッセージを送っていますでしょ。
だから、そういった日に限定するんじゃなくて、広島の地を訪れて、例えば平和記念資料館などに行ってしっかり見ていただいて、被爆者の言葉を聞くなりして、よくよく噛みしめてもらいたいということを、常日頃から言っていると、改めてお伝えしたいというふうに思っています。
記者
アメリカ政府に対して、発言の撤回だとか抗議だとかを求めるような考えはありますでしょうか。
市長
政府に対して?
記者
トランプ大統領に対してです。
市長
先ほど申し上げた、平和首長会議共同アピール、全てであります。全ての為政者に対して外交努力をと、その言葉をしっかり受け止めてくださいというふうに言っています。
記者
このあと午後からも、(アーロン・)スナイプ首席公使が来られるということでして、今回の発言だったり等に絡めて、トランプ大統領にぜひ来てほしいとか、そういった抗議でもいいですし、ぜひ来てほしいというふうな発言でもいいですし、何かおっしゃられる御予定とかっていうのはあるのでしょうか。
市長
抗議とかという言葉そのものにこだわるわけではないんですけれども、ヒロシマの立場を申し上げて、そういったことを暴力行為などで問題解決を図るということは、ヒロシマの心からするととんでもないことでありますよということを言い続けていますから。ぜひ世界の為政者の方は、こういった考え方を理解の上で、政治活動をしていただきたいということを伝えることに尽きるんですね。
そして、その気持ちを分かっていただくためには、もし被爆の実相なるものを知らないから、そういうことを言っておられるのであれば、広島に来てよく見てくださいと。御自身、見れば分かるはずなんではないですかという気持ちを込めて言っています。
ロシアの平和記念式典への不参加について
記者
先日、駐日ロシア大使が、9日の長崎の方の平和祈念式典に出席されると話していて、一方で、広島の式典については、依然として政治的姿勢を改めていないとして参加しない。行事の正式な招待状とは言えないというふうな旨で参加を見送るというような発表をされていました。広島市としては、式典自体を国際政治の舞台にしてほしくないというのは常々話しているかと思うんですけれども。結局、言い方悪いですけど、外様の方々は国際政治の舞台にしようとしているというふうな形にも見受けられると思うんですけど、その点の受け止めを教えていただけませんでしょうか。
市長
今の話は、直接私が聞いたわけでなくて、新聞等の記事からの話なので、今の大使が、あるいは大使館から、「正式な招待状とは言えない」とか、「政治姿勢を改めていない」ということ、それを理由に参加を見送るという発言があったということのようなんですけれども、これについては繰り返し言わざるを得ない、本市の意図をぜひとも御理解いただきたいということに尽きます。
まずは、正式な招待状じゃない。まさに、招待状ではなくしたわけでありまして、それぞれの立場で広島がこういうふうに考えているということを理解して、それを受容するといいますか。その上で式典に臨んでいただけないでしょうかと。政治的利用というのは、広島が認めたから広島と仲がいいんだとか、広島が我々の政治的立場を認めないから仲悪くするんだとか、そういった伝え方をされたくないから、広島の式典はこういうことで開くので、そういった立場で出ていただけないでしょうかと、こういうことを申し上げるのが招待状をやめた原因であります。
元々、慰霊祭を開き始めながら来ていただいて、この思いを世界に届けるためにどうするかというその手段として来ていただくということをやったんですけれども、そうした中で、当事者同士が戦争を始めたときに、どちらかが悪くてどちらかがいいかというような判断をして、始めた人は呼ばない。いや、両方とも呼ぶんだとかいうふうな議論をして、そのこと自身について、市はどういう判断しているんだとかっていうことを臆測させる、あるいはそれを推量させて、広島の願いをある意味で政争の具にされるような状況が起こることを避けたいということで、招待方式はやめて御案内方式に変えたということ。まず、これを繰り返し御理解いただきたいと思います。
そして、今回参列者、主体的に判断していただくということで、196の国・地域など、宛名なしで開催を通知いたしました。これをもって政治姿勢といわれるかと。平和姿勢です私たちは。政治の、広島の平和を政争の具にされたくないから、平和思想とか平和姿勢で御理解いただきたいということをお願いしたいというふうに思っています。
記者
その点でいうと、こんなふうに政争の具にされているということは残念というふうな…。
市長
世の中の政治家の方々の習わしということなんだと思います。だからといって、私はコントロール権があるわけじゃないので、こういった立場も理解していただきたいということでありますし、政治的に世界中いろいろな形で勢力争いされていますからね。国内でもそうでしょう。
だから、政治的な立場を主張するという政治的な政治家の仕事もありましょうけれども、一点、またそこに対してお願いするのは、為政者という立場で、国民、あるいは市民の安心・安全・安寧を保つという政治家としての発想として、思想というもの、大事かも分かりませんけれども、少なくとも暴力などを使って人をコントロールするという方法を過去のいろいろな経験から、人間、英知を蓄えてきているわけですから、対話を通じてやりましょうというようなことを言っていますよね。そういったことをしっかりやっていこうという国連組織まで作っているんですよ。それを言い続けるということを我々広島市はやりたいということをぜひ御理解いただきたいです。
ノーベル賞委員会委員長の広島訪問について
記者
一部報道で、今月の21、22日に、ノルウェーのノーベル委員会のフリードネス委員長が来られるという報道が一部ありましたが、広島市としての今の調整の状況と、改めてにはなるんですが、来られることへの期待感といいますか、受け止めを改めて伺えますでしょうか。
市長
誰が来られる…。
記者
ノーベル委員会のフリードネス委員長です。
市長
私自身、委員長と直接会ったことはないと思うんですけれども、ただ、来られる動機付けなどを見てまいりますと、この度の(日本)被団協へのノーベル賞受賞の要因とかというお話をいろいろなところで開陳されながら、広島に来ることの意義を強調されていますので、そこの考え方、今申し上げたようなところで、根底で共通するところがありますので、ぜひその立場でヒロシマが持っているヒロシマの心のようなものを広げていくということについて御理解を深めてもらって、そして、ある意味で一緒に連携しながら、為政者の外交方針、いわゆる核に頼るとか武力に頼るということを改めていくという、そういう環境づくりにいろいろな形で協力・連携できたらいいですねみたいな話は、もしお話しできるんだったらやりたいなというふうに思っています。
記者
具体的に面会の調整だとか、そういう状況って何かありますでしょうか。
市長
私自身、まだ聞いていない。
市職員
今、調整させていただいていまして、平和記念資料館の視察であったり、(原爆死没者)慰霊碑の参拝、あと時間があれば、市長の訪問ということで考えておりますけれども、まだ先方から正式な返事をいただいておりませんので、また受け入れのプログラムの詳細が決まりましたら、こちらの方からプレスリリースという形でお知らせをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
小学校教員のわいせつ未遂事件について
記者
先月の30日に、広島市内の小学校の教員がわいせつ未遂の疑いで逮捕されるという事案が発生しました。それに対して市長の受け止めをお聞きしたいんですけど。
市長
直接的には教育委員会の方で対処していただいていますけれども、最近ですと、名古屋(市)の方でも問題が起こったというふうなことを聞いています。いわば、お子たちをしっかりと育てていくという重要な職責を負った先生方でありまして、多分、多くの先生は教員としての本務をしっかり全うされているということは間違いないと思うんですね。そうしないと教育というのは成り立ちませんから。
そんな中でこういった、その教育そのものを実行できないといいますか、教員に対する信頼を損なうようなことが起こるということ自体あってはならないことじゃないかというふうに思っておりまして。起こったこと自体については厳正な対処がいりますけれども、改めて先生方、こういったことが多くの方、先生になるときから、きちんとした志を持ってなっている方が多いと思うんですけど、そういったことが貫徹できない、こういった事象が生じることについて、改めて教育委員会、先生方の中で確認行為をするとか、しっかりやっていこうということを申し合わせていただくというようなことをやってもらいたいなという思いがあります。
いずれにしても直接的には教育委員会の方でやっていただいているので、しっかり対応していただきたいということは申し上げております。
被爆者数が10万人を下回ったことについて
記者
昨日、厚労省(厚生労働省)の調査が発表されまして、全国の被爆者が初めて10万人を割ったという結果が出ていました。被爆80年で被爆者の方の高齢化であったりとか、いなくなっている現状があると思うんですけれども、広島市としてどのように受け止められているか教えていただけますでしょうか。
市長
今言われたのは、いわゆる被爆手帳(被爆者健康手帳)所持者、この方々で存命な方々が10万人を切るというふうな状況になって、一時期たくさんおられた方々のピークから比べて4分の1になったとかというコメントがありますけれども、それくらい皆さんが高齢化されて、平均年齢が86歳を超えるという状況であります。
まず、被爆を受けながらここまでしっかりと生きてこられたということ、ここに来るまで大変な御苦労、いろいろな意味であったというふうに推察いたしますけれども、そんな中で広島としては、とりわけ平和ということを考えたときに、そういう争い、国同士の争いを直接経験していない多くの若い方々が今、これからの国あるいは地方を支えていくという中で、そういう苦い体験、あってはならないというような体験をしたことを踏まえて、平和の国家をつくろうということを考え、それをしっかり将来に伝承していこうと、伝えていこうということを思った方々が多くおられる。その方々の意志なり気持ちを若い方々にしっかりつなぐということを本当に今やっておかないと、あっという間に今おられた方々がいなくなるわけですね。
だから被爆の伝承ということ、その中で、原爆を使うとこんなになるんだよと、こんなふうに考えるべきじゃないかとか、そういったことを若い方々にしっかり伝えるということをやってきて、そして、御苦労されている方について、今、国等における援護措置ありますから、それについての手当てを引き継いでしっかりやってくださいということを注文するといいますか、お願いする。この2本立てでやっていくということが重要かというふうに思っています。
記者
ちょっと今のに関連しての質問なんですけれども、先ほど市長もおっしゃったとおり、10万人を下回ったということで、これ、あくまで被爆者健康手帳を持っている方々で、実際には今、広島の今の黒い雨の裁判でしたり、長崎の方の被爆体験者訴訟でしたり、まだ被爆者として認められていない原爆被害者、さらに言えば、今、別にそれに該当せずとも今申請して認められない人とかもぽつぽついますけれども、そういった今、(被爆者健康)手帳の取れない原爆被害者に対する今後の対応だったり何か措置だったり、お考えとか受け止めとかってあったりされるんでしょうか。
市長
被爆手帳、黒い雨の問題については、広島としての対応の仕方は今申し上げたように、実際に事実、被爆を受けて、そして黒い雨など浴びて放射能の影響があり得る方々がおられるという事実は間違いありませんから、そういった方々に対する援護措置をきっちりやる。しかし、これは国家全体でやる、そういう措置を窓口としてというか、そういう作業というか事務を、広島市としてしっかりやらせていただくことで、その気持ちを届けるということをやってきています。
黒い雨問題については、そういう方々であるということを認定するための要件設定などがあまりにも厳しすぎるといいますか、ということがありましたので、市として国とのいろいろなやり取りの中で、間違いなく黒い雨を浴びたと、そういったことが分かるのであれば、こういう地域の外か中かだけで決めるのではなくて、そちらの方を重視した判定の仕方をということをお願いして、ある程度、広島の思いは届いて、今の広島に関わる認定基準はだいぶ改善されたというふうに、ただ行政の方は、というか国の方がこだわった判断は、放射能を浴びたことに伴う、いわば健康障害などの問題で明らかに放射能の影響であるそういう病状とか、そういったものが見受けられるというふうになるとかっていう、そちらの方で要件といいますか、いわゆる国でいうと科学的知見というようなものを重視しないと、それまでいろいろな形で援護措置を講じてきた方々とのバランスが取れないから、それにこだわるっていうようなことを言われたので、そこは実際に高齢化していく中で、高齢化による病状と放射能による病状、そういったものを、神様じゃないから完全に分かるわけではないですから、そういった取り扱いの部分ももっと短略化して、本当に体験したんだという方がおられれば、それをむしろしっかりと受け止めて手帳を発給するようにという立場でやってまいりまして、広島とすれば、国が制度をある意味で前後ブレなくやっていきたいという中で、より援護措置を弾力的に広げていただくという方向で取り組んできて、その成果も踏まえながら、今でも申請があれば、きちっとその手当てして手帳を出すというふうにしておりますので、制度運用主管の国と現場での皆さん方の気持ちをうまく調整するという立場をやり続けていく中で、援護措置の充実あるいは適用拡大ということを引き続きやっていきたいというふうに思っています。
名古屋市長が倒れた件で首長自身の公務のあり方について
記者
先日、名古屋市長さんが記者会見中に倒れるというような事案がございまして、とりわけ政令市長というのは所掌範囲も広いわけですけれども、首長自身の公務のあり方とか、そういったものについて何かお考えあれば、お伺いしたいと思います。
市長
公務のあり方。考えてなかった。自分自身は市長をやらせていただいて、ちょうど14年になりますので、あえて言えば、前、市長を今後どうしますかというふうに言われたときの答えと一緒なんですけれども、本当にこの広島で市長をやらせていただいて、自分は幸せ者だなと思っているんです本当に。
なぜかというと、こういった人間に関わる基本的な平和の問題ということをこんなにも真剣に考えて、皆さんいろいろな意見がある中で、それらについて吟味して、広島というまちの市長としてどうすべきかという大きな課題をいただいていて、それを考えることそのものを仕事にできるという立場で、そんな市長ってそんなにいないと思うんです。しかも、それが法律に書いてあって、頑張れよとこうなっているわけですから、それをやり続けるためには、市長をやり続けるかということと一緒なので、三力次第ですと申し上げています。
つまり体力・気力・知力、これがしっかり自分としてメンテができるかどうか、そういったことをやはり多くの基礎自治体、そうでない、広島と違うとしても、基礎自治体の首長さんは市民生活全般にわたることについて、その地域内の環境設定とか、いろいろな事務、国からのいろいろな事務を適切に対処するという、いわば、その総まとめ役ですから、そういった知力・気力・体力をしっかり維持して、そして、そのこと自身を多くの選挙の際に投票してくれるだろう市民の方に認知していただく。「そうだな」というふうに言っていただける仕事ぶりをやり続けるということだというふうに思っていますけれども、それが「もういいですよ、あなた御苦労さん」と言われれば市長を辞める他ないと、こんなふうに思っていますけどね。答えになっているかどうか分かりませんけれどもそんな感じです。
※( )は注釈を加えたものです。
配付資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画総務局 広報課報道担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2116(報道担当) ファクス:082-504-2067
[email protected]
