2025年9月2日記者会見「令和7年第3回広島市議会定例会提出案件について」外7件
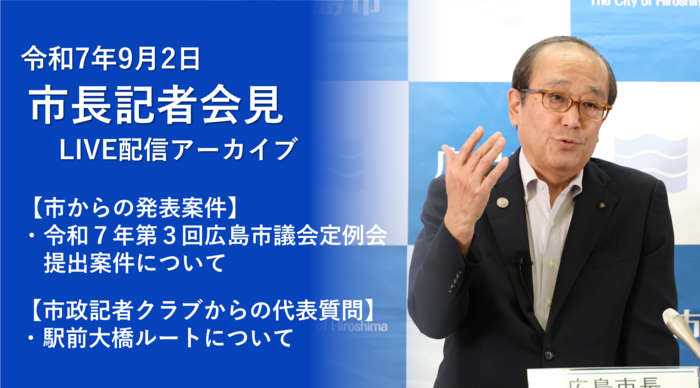
- 日時 令和7年(2025年)9月2日(火曜日)午後1時15分~午後2時00分
- 場所 市役所本庁舎11階第1会議室
市からの発表案件
令和7年第3回広島市議会定例会提出案件について
市長
9月11日(木曜日)に開会予定になっております令和7年第3回広島市議会定例会に提出する議案でありますけれども、これは一般会計補正予算案など22件あります。
まず、補正予算案についてでありますけれども、今回の補正予算の規模は、お手元の資料の「令和7年度9月補正予算の概要」のとおりでありまして、57億7,904万8千円となっています。
その内訳としては、まずは損害賠償請求事件に係る解決金についてであります。市立保育園の園児の死亡に係る損害賠償請求事件につきまして遺族と和解することに伴う解決金を計上しております。
次に、開発事業特別会計への繰出金についてです。西風新都負担事業宅地の売払いに伴って、開発事業特別会計への繰出金を計上しています。
次に、開発事業基金への積立金についてです。西風新都特別会計からの繰入れに伴って、開発事業基金への積立金を計上しています。
次に、乗合バス事業の共同運営システムの構築についてです。乗合バスの自動運転の実現に向けた課題を整理するために一般社団法人バス協調・共創プラットフォームひろしまが行う実証実験に要する経費を補助いたします。
以上の補正措置を行った結果、補正後における全会計の総予算規模は、1兆2,834億2,140万1千円となります。
最後に、予算以外の議案としては、広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正案など条例案10件、その他の議案9件を提出いたします。
以上が今議会に提出する議案の概要になっております。私からの説明は以上であります。
記者
今おっしゃった補正(予算)の中で、市立保育園の訴訟に関係する解決金というのを計上されていますけれども、昨年の4月に訴訟を提起されまして、当初は市も争う姿勢だったと思うんですけれども、今回和解をするという方向に転じた理由、その辺りを教えてください。
市長
まずはこの件、解決するということになりまして、改めまして亡くなられたお子様の御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の皆様に対してのお悔やみ申し上げたいと思います。
その上でなんですけれども、本事案に関しましては、実は昨年、令和6年4月12日に、御遺族から本市に損害賠償を求める訴訟が提起されました。裁判所で、御遺族と本市の方の双方のそれぞれの考え方、根拠となります資料、そういったものの確認をする、整理をすると。弁論の準備手続きを進めてきた中なんですけれども、そこで裁判所の方から御遺族に対して解決金というものを支払うことでどうかという、いわゆる和解勧告がありました。その和解勧告の取り扱いをどうするかということが、この取組の理由なんですけれども、本市としては市立保育園において、保育中の園児が園内から所在不明になって園外でお亡くなりになったという事実、そのことはまず重く受け止めると。
問題は、そうしたいなくなったことについての過失責任になるかどうかと、こういうことが争いの基本的な額の算定になるんですけれども、これに関しては相手方が、職員側に過失があったから、だから損害賠償ということを言われたんですけれども、お子さんが亡くなられた事実はあるんですけれども、職員の取り扱いについて国の配置基準とか、保育士の方の役割分担というものを検証した結果、保育士に過失があるとは我々としては認められないと、ここの部分は譲れないということで弁論の準備を進めるということにしていたんですけれども、裁判所の方から御遺族の心情に配慮してこれ以上争うのではなく、何とかできないかとこういうお話がありましたので、園内にいて外に行って亡くなられたという事実を重く受け止めるということで、裁判所も争うんじゃなくて何らかの対応という御趣旨がありましたので、請求額からだいぶ額は裁判所の方で調整していただいたということもありますので、この内容について、争うことなく早く解決する方がいいだろうということで決断したというものであります。
記者
今の解決金の補正予算に関する御説明いただいたところに関連をしてなんですけれども、これ予算自体というよりは少し市の施策のところに触れる部分ではあるんですけれども、その事案があった後、市の方でもフェンスを取り付けたりですとか、安全に対する施策というのはされてきたと思います。
今回の解決金計上のタイミングで改めてお伺いをしたいのが、そうした安全対策ですとか、市内の市立保育園に対してこういった事案が起きないように、こういうふうにやっていきたいなどの市長のお考え、スタンスがありましたらお聞かせください。
市長
今申し上げましたように、児童(園児)が亡くなるという不幸なこと、亡くなった御家族、身内の方にとっては大変な苦痛でありましょうし、やはり何らかの形でこちらからお気持ちに応えるということをやらなきゃいけないということが発生します。
その際に、支払う理由などについて、やはり議会などにも諮ってやるということから、本当にこちらに咎があればというようなことを検証するという作業がないと、安易に出せないだろうということもまた容易に想像がつきますので、どうしようかというところで、裁判所の方から早期解決を図るべくという、ある意味で間を取った、しかも要求額をうんと調整していただいた上で、労をかけたわけですけれども、こういったことそのものが発生しないのが一番いいわけでありますので、再発防止ということをしっかり、あるいはそれ以上に再発防止をしっかりやらなきゃいけないというのが第一義的な判断でありまして、実は「園児死亡事案に係る検証委員会」というところで提言を受けておりまして、令和5年の1月に、いわゆる取組方針なるものを策定できておりますので、これを踏まえた対応をしてきております。まず、園庭と園外を隔てている生け垣のフェンスを改修するとか、それから園児が行方不明になった場合の対応のマニュアルの改訂をするということ、それから普段からのいろいろな訓練を実施して、いわばハードとソフト両面での安全対策強化ということをやっておりまして、こういう園と外の隙間がないようにということを点検するとか、他の園についても手当てをするということで、こういった事案が二度と起こることのないような、いわば安全・安心な保育環境をやっていかなきゃいけないなというふうに思っておりまして、こういった取組を一層しっかりしていきたいなというふうに考えているところであります。
記者
今の質問と関連で、例えば園庭を園外に出られないようにするための改修だとかというのは、一定に進んでいくんだと思うんですけれども、保育士の人数というか、保育士不足の点で、ちょっと伺いたいんですが、国が配置基準を見直して、一人あたりの保育士の数、先生が一人で見る園児の数を減らそうという動きもあると思うんですけれども、なかなか広島市も保育士の確保が難しいというふうに聞いておりますが、その辺り、保育士の確保をどのように進めていくのかというのを考えがあれば教えてください。
市長
保育士の確保、保育士については、いわゆる園児等をお世話するための基準といいますか国の方で園児何人あたり何人と、こういった基準があって、それに基づく配置をすれば、それに必要な人件費というか、それに設備に関わるようなものも国から支援いただけるという、そういう仕掛けになっていて、それに従って最低限の条件を満たすための措置を講ずるというのが国内全般の措置でありまして、我々とすれば、現場を見て、今の中でいろいろなお手間というか、しっかりと世話をしなきゃいけない園児が増えるとか、先生方の、いわばその業務が学校でも一緒なんですけれども、園児そのものを見る業務の他に事務作業とか、いろいろなことがあって、働き方改革のようなものもしていかなければ十分な人を確保できないという現場の声も一部ありますので、そういったものをしっかり届けながら、充実していただけるべきものはしてほしいという要望を国にしながら、そして、現場での働き方、取組改善等はできるかぎりのことをやっていただくということをやりながら、ある意味しのいでいるということであります。より良い労働環境にするための、しっかりとした定員確保というものもやっていきたいというふうに思っていますけれども、それがステップ・バイ・ステップ、いきなり全てが全部いくという状況ではありませんので、これからも、環境、いわゆる園の状況、労働環境を整えるという視点に立って、充実強化をしっかり国に要望するということもやっていきたいと思っています。
記者
これまでの質問と関連して同じ事案についてなんですけれども、裁判の和解というのは、もちろん相手方がいらっしゃるというところだと思いまして、いつ頃、まず和解が成立する見込みなのかというところと、何か和解にあたっての条件ですね、和解金以外に、例えば市の謝罪ですとか、どういった条件があるのかというところをお聞きしてもよろしいでしょうか。
市長
今のところ聞いていますのは、今の条件で、双方にこれ以上争いはありませんということを確認するということをやっていただければ、和解できるというふうな状況になっているという。それを今、議会に諮っていますから、議会で承認いただければ、了解できましたよということを御本人に伝えて成立するというふうに思います。
記者
事案を受けて、市の方で保育士不足の現状などを調べられたという経緯があったのではないかと思うんですけれども、その点、何か進捗があれば、もしくは結果が出ているのであれば、その辺の辺りの進展をお聞かせください。
市長
分かる範囲で言ってください。
市職員
今、おっしゃられたのは、恐らく国が配置基準を見直された3歳児、4歳児、5歳児のあたりの保育士不足の現状の調査ということになろうかと思います。それにつきましては、まず私立保育園の方に状況を確認したところ、おおむね9割以上は達成できているという回答をいただいております。
したがって、今度は公立保育園の方になるんですけれども、公立保育園につきましては、現状まだ配置基準の見直しに必要な保育士というのが確保できていないという状況がありましたので、今年度から3歳児の配置基準を改善できるように保育士の確保を進めてきているという状況にあります。以上です。
市政記者クラブからの代表質問
駅前大橋ルートについて
記者
JR広島駅に乗り入れる路面電車の駅前大橋ルートは、開通からまもなく1か月を迎えます。開通に伴う効果と課題をどう考えているかについてお聞かせください。
市長
今言われた(駅前)大橋ルートの件ですけれども、開業から1週間、この間でJRの広島駅、この利用客に関しての情報がありました。これは、JR西日本の発表なんですけれども、一日平均で約15万6,000人の利用客があったということで、この数字は、前年の同時期と比較すると114%に伸びていますと、こういった発表がありました。その他、路面電車の利用客の数、これも関心があるんですけれども、これは現在、広島電鉄の方で集計中というふうな話を聞いているのが直近の状況であります。したがって、開通に伴う効果全般が把握できているような状況ではないんですけれども、非常に多くの方が路面電車に乗り換えられている様子が伺えるというようなことを、広島電鉄とかJR西日本からはお聞きしておりますし、電停が広くなって乗りやすくなったとか、駅周辺の商業施設にも集客が増すという効果が広がっているというようなことを、皆さん様々な形で実感しておられるような状況でもありますので、一定の効果として東の都心核と位置付けている駅周辺地区の状況は多くの人々が集まって、新たなにぎわいが確実に生まれているなというふうな受け止めをしているところであります。
今後の課題、これについては、こういった形で生まれた新たなにぎわい、東の核のにぎわいをいかに西の方に波及させるかという問題意識、それとともに、さらには広島広域都市圏全域にも波及させるにはどうしたらいいかなと、そんなことを今、問題意識として持っています。
その他の質問
新型コロナウイルス予防接種の費用助成について
記者
新型コロナウイルスの定期接種についてなんですけれども、今年度から国の費用助成が終了となりましたけれども、広島市として、この費用助成をどのように考えているのかというのを教えてください。
市長
基本は御本人負担ということでやっていただく。それで接種するための先生方への手間といいますか、委託費は出しますけれども、御本人負担で今までもインフルエンザとかいったようなものをやっていると。同じ取り扱いでいいんじゃないかなと思っています。
記者
ごめんなさい。同じ取り扱いというと…。
市長
御本人負担。
記者
御本人負担…。
市長
それと、注射などをするにあたっての委託費は、先生方に払うということになろうかと思います。
広島県知事について
記者
県庁のことなんですけれども、先日、湯﨑知事が次は出馬をしないというふうな表明をしておりまして、次の知事選に向けては、すでに横田(前)副知事が出馬の調整をされているということで、仮に横田氏が当選したら、県内初の女性知事が誕生するというふうな見通しになります。
改めましてなんですけれども、今回の湯﨑知事の不出馬の表明及び、今後の新たな知事誕生への展望でしたり、期待について教えていただけますか。
市長
まず、湯﨑知事に関しましては、相当、長期にわたってお付き合いさせていただいて、県政をけん引されてきましたし、県・市の連携ということに関しても、御一緒に仕事させていただいて、着実に進んだものというふうな受け止めを私はしてますので、この間の御尽力に改めて敬意を表したいなというふうに思っています。
新たに選ばれる方、選挙がありますから、どなたということは、まだ分かりませんけれども、いずれにしても本市とすれば、県との持続的な発展に向けての連携をしっかり図れるようにしていきたいというふうに思っていまして、新たに知事になられる方としっかりと連携を組んだ行政展開ができるようにできればなというふうに思っているところであります。
宇部市の炭鉱で発見された人骨について
記者
全然別件の質問なんですけれども、また、隣の山口県の話なんですけど、先日、山口県の宇部市の長生炭鉱で、当時、炭鉱に従事していて、そこで事故によって犠牲者となった方々がいらっしゃいまして、そこで、先日、犠牲者とみられる人骨が市民団体の手によって発見されまして、一方で、政府としては、遺骨に対しては、戦没者遺骨収集推進法の対象外として、市民の犠牲者であるので、遺骨収集に対して、国が消極的な姿勢を見せておりまして、その辺に関する、もし市長がその件についてご存じであれば、受け止めを教えていただきたいんですけれども。
市長
ごめんなさい。今、初めて聞きました。その件は承知してないんです。
4期16年にわたる湯﨑県政への市長の思いと、次の知事に広島市長として望むこと
記者
先ほど、毎日新聞さんがおっしゃった、知事の退任の受け止めのとこなんですけれども、市長、おっしゃったように、長きにわたって、県・市のトップとして歩んでこられたと思います。で、近年では、サッカースタジアムの建設だとか、(広島)西飛行場ですよね。西飛行場の活用とか、いろいろなこの10年あまり、いろいろな懸案がある中で、それぞれ尽くしてこられたと思うんですが、特に県と一緒にやったという課題の中で印象深いものが、市長の中でどういったものがあるのかということと、あと、今、県・市に課せられている課題というか、こういったことをもっとやっていかないといけないというのがあれば、その辺り教えてください。
市長
私自身、県・市連携という課題を掲げてやった中で、一応、成果が上がっているのは、始めの頃は、西飛行場の跡地の利活用をどうするかっていうのがあって、ヘリポート共用で解決しましたが、その辺も費用負担を最終的には折半するっていいますか、やっていこうじゃないかということで、飛行場はなくなったけれども、ヘリポートにして、消防ヘリなんかも利用できるようにというふうなことで解決したということがありますよね。
その他には、「美しい川づくり」将来ビジョンなんかを策定して、これは、駅前の大橋のたもとをきれいにして、あの辺りを整理して、そのあと、駅をきれいにするっていう予定ありましたから、猿猴川の周辺をきれいにするということ。
当然、河川管理は国から県に下りてますので、県と連携して、きれいにしたというのもありますし、あとは都心活性化プランも、これ県も市も、それから民間の方も入っていただいて、活性化に向けての都心、東西の核とかっていう考え方も前提に協力いただいているし、それから、特に紙屋町・八丁堀、県庁のある周辺の辺りも市のまちの整備にあわせて、県庁の前なんかもやっていただいて、景観がだいぶ変わってきているというのがありますね。
それから、あとは、G7サミットが、何と言っても、国の対応でしたけれども、県・市一緒になってお迎えしてある意味でそのG7開催の広島というのは世界のブランドにもなったんじゃないかなと思います。そして一番思い出深いのがエディオンピースウイング(広島)の建設でありまして、これはどこでやるか、やらないかと、その知事のその考えがあろうし、県議会の考えや、広島の私の考えもあるし、議会があると多くの方の意見がある中で、やらないための工夫をやったつもりはなくて、やるためにどこにどうやるかと、その設定条件がどうかということで、いろいろな御意見が出てね、時間がかかりましたけれども出来上がったものについては多くの皆さんからいいものができたと、このような評価を受けていますから、そういった意味で先ほど申し上げたようにいろいろな意味で成果が上がったんじゃないかなというふうに思っています。
記者
これから何というんですか、まだ残された課題というか、県・市で多々あると思うんですけど、ハードもソフトもですね。この直近に差しあたって、市長、思いつくものがあったらよろしくお願いします。
市長
これからっていうか、私自身は、例えば、今度の予算措置なんかでも出した、公共交通をしっかりやることでハード面が整うけれども、そのハードからどう人々が行き来する上で足の便を考えなきゃいかん。それは市内だけじゃなくて、広域都市圏でも広げていこうと、こういうふうに考えるんですけれども、そういったその取組にあたって、県全体をやるときに県との協力関係も得ながら、県を越えるところについても、やはり県同士で連携というか、仲良くしていただいた上でお互いの県の市町と仲良くすると、そういうことをやれるようにと思っていまして、その広域都市圏の県・市を超えた、今33の市町の、いわゆる協議会とか、会合には関係する県の方からオブザーバー、それぞれ、山口、島根、広島と出ていただいて、我々の動きをフォローするとともに、いつでも協力していただけるような取組をしています。こういった意味で、市の中心部プラス広い領域でのいろいろな取組も連携を取れたらいいなというふうに思っています。
「多選自粛」に対する市長の考え
記者
湯﨑知事の発言の中で、4期やってきて、そろそろこれは潮時かという、そういうタイミングなんだという発言があったんですけれど、市長も今4期目に入られているかと思うんですけれど、もう折り返しは過ぎていますけど、今後の御自身の次の市政をどうされるのかという、まず考えがあるのかという点が一点と、それを考えるにあたって、4期やってきたというのが長いのか短いのかというのは、どう判断するのかはそれぞれあると思いますけど、やってきたことの長さというのを、その判断にあたってどのように考えられるのかというのを教えてもらえればと思います。
市長
「多選」といえば、この用語あるいは、この問題については、私が知事よりか1年遅れて市長になったときに、改めて聞かれたりしたんですけれども、私自身は多選というのは、あくまで立候補した被選挙人が有権者から票をいただけるかどうかであって、確実に票を取ってなれるわけじゃないので、被選挙人、立候補者の問題というか、選ぶ側の問題なので、多いか少ないかとか聞かれても何とも言えませんというのは、そういう考え方をずっと貫いているので、知事とはちょっと違うということを御了解いただきたいんです。なので立候補のときから、そういう基本的考え方が違うということ。
ちなみに、そういう意味では、この4期務めてきた知事と比べるとどうかというような御質問になると思うんですけれども、私自身が次の市長選に出るかというかという、これについては前の前かな、記者会見の方で申し上げたんだけど、白紙ですと。現時点では白紙です。あえて言うなら、なぜ白紙かというと、さらに私自身のミリョクとか、行政上の多様性の問題で、そういったもの次第ですと、こう言ったんですね。これでもまだ分かりにくいだろうということで、ミリョクというのは、私自身の知力・気力・体力という、この3つの状況がどうかということをまず考えて、選挙に出るかどうかだと思うし、それから、私のそういった個人情報というか、個人の条件設定プラス市政上のタヨウセイというのは、例えば、私自身に対して評価する側の方が必要であると思うか、あるいは不要であると思うか。つまり、必要性・不要性と。それから、私自身が市政を引き続きやることについて有用性があるか、あるいは無用であるかとかね。
そういったような客観的評価がある程度仕事をやりきったギリギリの段階で判断すべきものだと思っていますので、そういう意味で、現時点では何とも言えませんと思っています。重ねて言いますけれども、多選というのは結果で出てくるものでありまして、立候補した人が勝手に左右できるものではありませんから、「多選自粛」ということもあえて言うならば、自分に自信があって勝てるかも分からないから、私は選挙で投票してもらわないために出ないんだと、こういったごく限られた場合のみ成立する言葉であるし、そういったことをするかどうかは、その行動に合理性があるかどうかということ。そして、合理性があれば、そういうこともあっていいんじゃないかなと、そんな類いの問題じゃないかなと私自身は整理しています。
記者
湯﨑知事が立候補、次しないという表明されてから、知事の方と何か直接お話をされたりっていうのがあったのかというと、もしあれば、差し支えない範囲でどういったお話をされたのかということを、ちょっと教えてもらえれば。
市長
知事との話は携帯にちょっと残っていて、発表直前ぐらいに電話があって、発表されたあとバタバタしていて、メールが来て電話が来ているのというのが分かったのでお話ししたら、新聞で発表したんだけれども、出馬しないことにしたということがありましたので、御苦労さまでしたというようなやり取りをいたしました。
記者
それは、もう発表の日にってことですね。
市長
はい。
記者
核兵器廃絶や核軍縮について、県独自でいろいろ取組もされていまして、平和記念式典の知事挨拶なども、核抑止の虚構性について結構訴える内容であったりしましたけど、知事のこうした取組・姿勢については、どのように評価していましたでしょうか。
市長
これは似たようなことを職員からも聞かれるんですけど、平和についての県と市の取組をどう思うんですかというので。私は、平和の取組について県と市の関係は、あんパンのあんこと外側だと、こういうふうな言い方をずっとしているんです。県知事にも言ってね。市長になってしばらくして、こういう二重行政をどうするかっていうような話をする中で、平和問題についてのあり方で、私なりに、管轄の役割分担は、あんパンのあんこと外側の関係であると、こういうことで整理して一緒にやりましょうと、こう申し上げたんですね。
自分があんパンのあんこだと申し上げたのは、平和というものを自分たちが実感するためには、市民がこれを食べて、あんこを味わって、外側も一緒に食べて、確かに平和はこうだと。要するに、この平和っていうのは、市民社会というか、そこで暮らす方々が実感できるようなものをやる、どうしたらそうなるかということを追求していく上で、この広島っていうのは平和の象徴都市として、市民に向けてメッセージを発信して、こんなふうにしましょうよということで、いろいろな平和行政をやるというのが私のスタンスですと。そういう意味で、パンのあんこを食べてもらうというのが重要なのではないかと。そういったものが、おいしいかどうか、食べようかなというふうなことをやるというのは、人々を引きつけて平和というものについて興味を持ってやってもらうんだったら、あんパンの外側をきれいに作ってもらって、やるというのをやってもらう。「いいと思う。どうぞやってください」と。で、来た人を引きつけて、いろいろな対策とかを行いましょうっていうのが私だと。こんなイメージで話していました。
おおむね、そうなっているような気がしているんです。だから、知事の方がアピールして、政治家にどういうふうにするとかね、こういうものだと。それを分かった上で、我々はどうしようかと。それは我々が思った気持ちを世界に発信する、政治家に届けるというようなことをやるという立場で、自分はヒロシマの平和の取組をやり続けたいなと思っています。
記者
ちなみに、平和記念式典の知事挨拶は、毎年聞いてどのような感想を持っていたりしたんでしょうか。
市長
先ほども申し上げた役割分担を本当にしっかりしているなと思っています。だから、皆さんにこの平和問題についての意味付けとか、問題意識を喚起するという意味での論理構成とかは、確かにしっかりしているなと思う。私はそれを前提に、むしろ市民の方に、さっき言ったあんパンのあんこを味わっていただくには、自分たちはどう考えたらいいのか、どうしたらいいかということを考えていただくことに力点を置いて平和宣言をしてきています。
だから、そのいろいろな方の意見を聞きながら、自分のそういった思いを伝えるための平和宣言にしていますから、市民が作った意見を長崎方式でやってはとか、いろいろな意見があるんだけど、それは自分のやり方じゃなくて、あんパンを作るときの意見を、皆さんからの参考意見をお聞きしながら作っていくやり方を、私が市長をさせていただいている間はやりたいと思っています。
記者
続けて関連なんですけれども、湯﨑知事が不出馬表明されてから、巷間では、ずばり次の市長選に出るのではないかという臆測も飛び交っています。率直にどう受け止められますか。
市長
率直に。ノーコメントです。本人の意思ですからね。私もまだやるかどうか決めていないんだから。決めたときに、そのときの状況がどうかっていうことで。そのときにはもちろんコメントを加えますけど、今は白紙でいいと思います。
西広島バイパスの延伸工事について
記者
話が変わるんですけれど、西広島バイパスの関係で伺うんですけれど、そろそろ本体工事が本格化というか、本体工事が始まるかと思うんですけれど、この間も先日も国交省(国土交通省)と広島市とかを含む会議の方で、本体工事が始まれば、かなり渋滞が予想されるということで市民への呼び掛けなんかもあったわけですけれど、本体工事がいつから始まって、今でもすでに渋滞がかなりあると思いますので、いつから始まってどのような影響が及ぶのかというのは、市民もすごく関心が高いかなと思いますので、分かる範囲で、今、いつぐらいから本体工事が始まるのかという、もし見通しがあればというのと、改めて市民の皆さんへの呼び掛けというか、気をつけてほしいことがあれば教えてください。
市長
国道2号線の西広島バイパス問題は、市長になったときからの大きな課題がようやく動き始めて、そして、我が市の、特に西の方からのアクセスと各デルタ地から外に出ていく上での利便性を格段に高めるとても重要なインフラだと思っていまして、これは国の直轄事業でやっていただけると。
しかしながら、すでに動いている2号線の中にものをつくっていくわけですから、言われたように工事期間中に高架橋を設置する作業等々で現状の交通状況に影響が出ることは避けがたいと。ですけれども、成果が絶大なものがありますから、そういった不便をある程度受用しながらでもいいものをつくるということを皆さんに御理解の上、御協力いただきたいというのが自分の基本的立場であります。
そういう意味では国と連携して、工事期間中の渋滞が生じるとしても、それを最小限に抑えるための対策をしっかり取り組んでいかなきゃいかんというのが基本認識であります。今言われた工事開始とか、むしろそれに伴う規制開始ですね、いつ頃から始まるかということは市民の方も御心配でしょうけれども、それについては、明日、西広島バイパス都心部延伸事業の円滑な推進に向けた官民連携会議というものを開催する予定にしています。そこで関係するお話を国の方からもしていただけるという機会を設けていますので、多分、その場で国の方から今後の見通しは示していただけるんじゃないかなというふうに思います。国の直轄事業ということで御了承いただきたいと思うんですね。
そして、すでに新聞等で書いている、国の方から交通規制の渋滞対策の発表があったと思うんですね。先月の28日かな。
これについては、例えば公共交通を利用してもらいたいとか、時差出勤を心掛けてもらいたい、あるいはテレワークをとか。さらには、迂回ルートも設定するので、手間でしょうけど回ってもらう。迂回ルートをつくってほったらかすとまた渋滞するから、交差点なんかも改良すると。広めに設定して全域でいろいろな対策を講ずるというようなことも発表されていますから、それらをうまく実施して、そして、その規制がかかる場所、あるいは交通規制が出てくる場所が、どんなになるかということをむしろ個人で移動するときに場所を知りたいですよね。それについては、本市とすれば広報紙とか、もちろん新聞広告もさせていただきますし、SNSもやるし、それから、できたらマツダスタジアムとかエディオンピースウイングに試合とかの間で大型ビジョンでも、例えば見て、一般の方が比較的容易にそういう情報を得られるようにするというようなこともやっていきたいというふうに思いますし、明日の会議がどうなるかということはまだ分かりませんけど、いずれにしても、こういった取組を皆さんにするということをしっかりお願いする機会にもなると思うので、官民連携会議、しっかり取材していただいて、取り上げていただいて、みんなに周知することを助けていただくとありがたいなというふうに思います。そんな感じです。
※( )は注釈を加えたものです。
配付資料
-
令和7年度9月補正予算の概要 (PDF 88.3KB)

-
会計別総括表等 (PDF 293.4KB)

-
補正予算の内訳 (PDF 142.3KB)

-
令和7年第3回広島市議会定例会提出案件 (PDF 360.0KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画総務局 広報課報道担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2116(報道担当) ファクス:082-504-2067
[email protected]
