2025年4月25日記者会見「第11回NPT再検討会議第3回準備委員会への出席等について」外5件
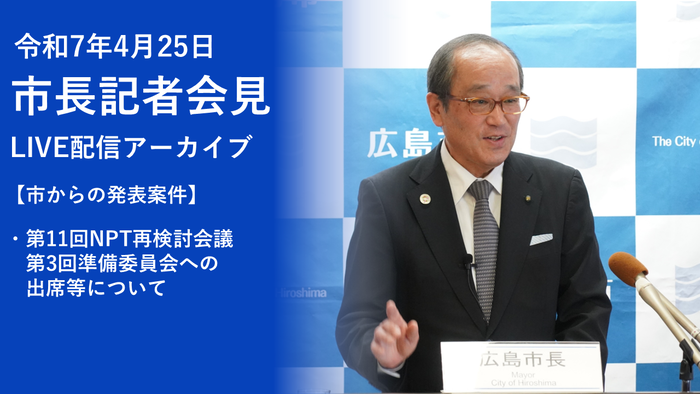
- 日時 令和7年(2025年)4月25日(金曜日)午後1時15分~午後2時00分
- 場所 市役所本庁舎11階第1会議室
市からの発表案件
第11回NPT再検討会議第3回準備委員会への出席等について
市長
この度、第11回NPT再検討会議第3回準備委員会への出席などを目的としまして、4月27日から5月2日までの6日間の日程で、米国・ニューヨーク市を訪問いたします。そのポイントについて話をしたいと思いますので、詳しくはお手元の資料、後ほど御覧いただければというふうに思います。
まずこの準備委員会におきましては、4月30日のNGOセッションに出席いたしまして、スピーチを行う予定にしています。この中で、世界中の為政者に対しまして、概ね次のような訴えをしたいと考えています。
まず、被爆80周年を迎えた現在も地球上には1万2,000発を超える核兵器が存在し、厳しい国際情勢を背景に、NPT(核兵器不拡散条約)の原則に背く核シェアリングなどを肯定的に捉える考え方が広まっていることに対する懸念を表明いたします。
次に、日本被団協のノーベル平和賞受賞に触れ、自らの辛い体験や憎しみを乗り越えて、「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」という願いを人類全体の平和を願う崇高な理念へと昇華させてきた被爆者の想いを原点に平和首長会議が活動しているということを伝えます。
そして、平和首長会議として、争いを生み出す疑心暗鬼を消し去るために、市民社会における平和意識の醸成と、「平和文化」に満ちた世界の創生に向けて全力で取り組んでいく決意を表明いたします。そして、各国政府代表者に対して、平和を願う市民社会の声に耳を傾け、対話による平和的解決に向けた外交政策への転換を為政者に促すように求めて、核軍縮・不拡散措置を確実かつ誠実に実行するように呼び掛けます。
以上がスピーチの概要であります。
その他、現地では、スピーチに加えてできるだけ多くの国連・各国政府関係者等々にお会いいたしまして、被爆者の平和への切なる願いを伝え、NPT(核兵器不拡散条約)体制の中で核軍縮を進展させるための具体的な行動、こういったことを要請するとともに、平和首長会議の取組に対する理解と協力を求めていきたいと考えています。
また、次代の平和活動を担う若者の育成を図るために、今回の準備委員会に、平和活動に取り組む広島県内の高校生8名を「平和首長会議ユース」として派遣し、中満(なかみつ)国連事務次長兼軍縮担当上級代表に約3万4千筆の「核兵器禁止条約」の早期締結を求める署名を届けてもらうことにしています。
併せて、準備委員会のサイドイベントとして、平和首長会議ユースフォーラムを開催し、平和首長会議ユースに加え、世界各地で平和活動に取り組んでいる若者たちによる活動発表や意見交換を行う予定にしています。
また、準備委員会の会場内で、平和首長会議原爆平和展及びこどもたちによる“平和なまち”絵画展を開催するとともに、ヒロシマの原爆被害等を疑似体験できるVRゴーグルの体験ができるブースを設置いたしまして、会議出席者とか国連関係者に被爆の実相や核兵器の非人道性、平和文化の振興に向けた平和首長会議の取組に理解を深めていただいて、核兵器のない平和な世界の実現に向けた気運醸成を図っていきたいと考えています。
さらに、若者に被爆地ヒロシマ・ナガサキの想いを伝える場として、鈴木長崎市長と一緒に国連国際学校マンハッタン校を訪問いたしまして、在校生に対し講演を行い、被爆の実相と被爆者の平和への願いを伝えて、核兵器のない世界の実現への道を共に歩んでほしいといった呼び掛けを行いたいと考えています。
来年開催が予定されております第11回NPT再検討会議の最後の準備委員会となる今回の会議は、核兵器使用の脅威が現実のものとなり、第二次世界大戦後に目指した平和構築体制そのものが揺らいでいるといった状況の中で、各国が集い、対話と協調の道を再び歩み始めることができるかが問われる重要な場となっております。今回の準備委員会が、各国が立場の違いといったものを乗り越えて、分断ではなくて共通の課題に向き合うための足がかりとなって、核兵器のない世界に向けた国際的な合意形成の再構築へとつながる場になることを期待しているところであります。
そして、被爆80周年という節目を迎えた本年、被爆地の市長として、また都市による平和構築を推進する平和首長会議の会長として、平和を愛する人々が望んでいる安全・安心で真に平和な世界の実現に向けて、市民社会の声が国家という城壁といいますか、障壁、こういったものを乗り越えて、しっかりと会議の場に届くようにできればなというふうに考えているところであります。以上です。
記者
スピーチのところで伺います。核抑止力に依存しない対話による外交政策への展開というのを訴えておられます。この間の平和宣言の文案作りのときもあったんですけれども、やっぱり今の国際情勢というのが非常にともすれば核抑止力に依存する方向に傾いているというか、そういった市長の思いがあるんでしょうか。その辺りに込めた思いをよろしくお願いします。
市長
思いは今申し上げたように、核抑止論なるものは、以前も言ったんですけれどもね。今のような状況ですと、破綻しているとね。(破綻しているに)過ぎないし、核によって人を脅して、人というか相手国かな。相手国を脅してコントロールしようという発想は、いわば現核兵器保有国の為政者の方々の多くが有効であるというふうにね、考えておられるようでありますけれども。今度も国連の場に行くんですけれども、国連という組織そのもの、その辺よく考えてみますとね、第二次世界大戦を終えたあとに、この地球上から核兵器をなくすために皆でどうするかという、その動機付けがあってこの国連という組織をつくったわけですね。ですから、その核兵器そのものをなくすということ、それは間違った使い方をして大変な結果を生んだんだから、それをなくそうということでやってきていた。その、いわゆる平和構築体制そのものを、今の戦後80年たって、為政者の方が、それを揺るがすような考え方をしているんじゃないかと。よくよくそこを考えていただきたいというふうに思うんですね。
実際、その戦後の世界は、そういった平和構築ということと同時に、終戦直後にいわば資本主義と共産主義という2つのイデオロギー対立があって、それらが、どちらが地球上のいろいろな各国をコントロールするかということでね、主導権争いが増したと、覇権争いをしたといいますかね。そういった経済的な面を中心にあったと思うんですね。それも今でいう、いわばエネルギーというか石油を巡って、どちらがコントロール権をしっかり立てるかということで、今問題となっているというか、相互関税とかいうのを打ち出して、今までの体制とは違った、今ある方向性とは違った形で問題提起をしているアメリカが、もっともっと国際主義であるとか、多国間協調とか、そういうことをやりながらオイルをコントロールして、世界協調を図るということをやってきたんですよね。
それでそういう意味では、経済争いで優位に立って、1990年代に入って、共産主義体制の経済が壊れたというか、ソ連からロシアに変わったと。そういったところで、ある意味で経済的な争いについては決着がついた。そうしたところが、今度は共産主義じゃなくて覇権主義的な国家というふうになってきた中で、そことの争いをやっていく上では、思想・信条じゃなくて経済関係での争いが中心になってきたからということで、今までの協調主義じゃなくて、自国第一主義というかね、ひとさまの面倒を見るほど余裕はないんだと。単独行動主義、あるいは孤立主義といったような動きを深めてきている中での、そういう立場での軍事ということになってしまったんですね。世界全体の調和を図るという視点で核兵器をなくす、全体をよくしようと言っていたあの意気込みが、今陰りを見せているというふうに、経済戦争を別の形でやっていく、協調ではなくて単独でやっていくと、であればその単独でやるための、自らの力を誇示するということを今以上にやらなきゃいかんみたいな。そういう展開になっているわけでして。
これが事実そういうことを行っているということが本当に人類にとっての理想的な状況か。過去、2度の大戦をやってきてそういったことをやめるようにしていこうという、その今までの努力はどこかに行きかけているわけですからね。そこのところを、為政者に。分かってはいるんじゃないかと思うんですけれども、それができない状況をどう正していくかというときに、私自身は国家的な政治力を行使するような立場にありません。日本国の中の自治体の長として、広島市長という立場でありますのでね。今言ったような気持ちを、むしろ市民に向けて、市民社会の中で、今言ったような思いを共有できるように、そこにヒロシマの心というものをしっかりとつけてといいますか、それを中心に皆さんにお話しして、今のようなあり方はおかしいんじゃないですか、みんなで平和というものを大事にする世の中にしましょう。その輪を広げるということを一生懸命やることで、為政者にこういった思いを届けるということをやりたいと思っていますが、その一環としてこういった形で会議に出て、思いを伝えるということをやっていますしね。各国の為政者などが来たときにも、平和記念公園でこういった思いを伝えるために、慰霊碑参拝などにも御一緒するということをやっているつもりであります。
記者
(4月)30日のNGOセッションでの市長のスピーチなんですけれども、行われる時間が具体的に決まっていましたら教えてください。
市長
行われる時間は、決まっていたかな。午後だっけ。
市職員
15時から始まりまして、予定としましては3番手ですので、恐らくスタートは15時15分とか20分とか、それぐらいになると思います。
記者
何点か質問があるんですけれども、まず1点目なんですけれども、NPT、2回連続で最終文書が採択されていない状況が続いているかと思うんですけれども、改めてそちらの受け止めについて教えていただけませんでしょうか。
市長
NPTそのものは、核兵器保有国、そして、保有していない国、両方の参画を得ながら構成されている、いわゆる唯一の会議といいますか、そういった位置付けですので、この場で核兵器の扱いをどうするかということをしっかりと議論できるはずの場なんですね。そして、この核兵器禁止条約の(第)6条には、いわば核軍縮・不拡散を関係者が誠実にやっていこうという義務があるわけでありまして、その義務履行ができていないということを関係者がどのように受け止めるかということが一番重要なんだと思うんです。
今、申し上げたように、いわば経済戦争ともいわれる状況の中で、自国の経済状況を優先するがあまりに、こういった平和というものを構築する経済システムを、安定的な運用をするためのベースとなる、いわば武力衝突がないように、争いがないようにするというための基本的な条約な部分を度外視してというか、経済の方にかまけて、これらについての履行をやや懈怠するといいますか、それを反映するかごとく、条約を検証して更新する際の検証作業そのものを成就させないというのが、合意文書ができないという、過去2回の経験になっているんですね。ですから、こういった会議を動かしている関係者、皆一同、心配しているんですけれども、決定的な当事者、いわばある意味で国連(国際連合)を主導する核兵器保有国、こういったところが安保理(国連安全保障理事会)じゃありませんけれども、拒否権に近いような形での、合意形成を最終的にできないような状況を設定しているというとこが問題なんだと思うんですね。
そこに、どういうふうに考えてもらうかということを強制力ありませんから、今のそういった対応が、どれほど長い目で、また、大局観的に見て、人類とか地球によくない影響を及ぼしているんだろうかということを分かっていただくようにしていく必要があると思うんです。そのときに、その一番の影響を受けるのは市民社会、地球上の人々一人一人ですから、政治とか経済というのも、国を中心にといいながら、その国の中に住む国民・市民、その安寧秩序を守るための目的なんですね。先ほど申し上げた城壁というか、国という枠組みに囚われすぎて、そこで暮らす人々のところまで思いがいっていない形での国家間の競争がこういった状況を作っているんだと思うので、ぜひ市民社会の声といいますか、一人一人の市民の声にもっと耳を傾けてほしいといったようなことを、繰り返し為政者に届けるということじゃないかなというふうに思っています。
記者
つまるところ、なので、今、為政者たちが自国の経済を優先するがあまりに、平和等に意識を向けず、採択されないのがその現れというふうな認識でよろしいでしょうか。
市長
経済を優先するというけれども、その経済優先なるものは、最終的に国内にある個々の市民社会に還元されなくてはならないんですね。例えば、国家の経済力といいながら、国家の中の特定の富裕層とか、いわゆる、偏った方々への資本蓄積とかっていうふうになっているかも分かりませんね。そういうことに、もっともっと気づくべきじゃないかなと。
そういう意味では、市民社会の総意というものをよく各国為政者、見た上で、国同士の競争、争いといかないでも、競争をやることそのものはあり得るとしても、最終決着点をよく見てやるべきじゃないかということを言いたいんですけれども、聞いてもらえるかどうかは分かりません。市長としては、そういう主張だということであります。
記者
昨年、ノーベル平和賞でしたり、今年、核禁条約(核兵器禁止条約締約国会議)あったりと、招待されていない、また、いろいろスケジュールの都合があったのは重々承知なんですけど、2つのイベントに行かずに、今回、この準備委員会に行かれる意味と、あと、御自身の役割について、どのようにお考えになられるのかについて、教えていただけませんでしょうか。
市長
国際連盟で開かれる核兵器に関わるような会議については、基礎自治体の長でありますから、基礎自治体としての営みというんですか、議会、予算編成から市政運営ということで、いわば、俗にいう公務といいますか、我々として本来の本市がやるべき仕事を第一義的にやるべきかなというか。その日程の中で許されれば時間を確保して、そういった会議に臨むということをやっていますから、TPNW(核兵器禁止条約)の方が行けなかったと。今回は4月議会を終えて6月議会までの狭間ですから、そういう意味では行けなくない。ただ、すぐに準公務で(ひろしま)フラワーフェスティバルがあるもんですから、なかなかタイトな日程ではあるんですけれども、NPTには出るようにすると、そういったことであります。
そして、立ち位置は、今、申し上げましたように、市民の安全・安心を第一義的に確保するためにどういった行政といいますか、政治というか、そういったことをやる。日本国内における、いろいろな統治システムをうまく利用しながらやっていくという立場ですから、そのシステムが機能不全になる。つまり日本国家が戦争状態に陥るとか、そういうことになれば機能不全になりますから、そういったことをしないような社会状況をまず作ってくださいということを、それに関係する方々にしっかり申した上で、そのことを間違いなく多くの国民・市民が望んでいると。そして、平和の状況と真逆の状況を経験した広島市民、被爆者、おってですね。その方々が戦争の結果、原爆投下の結果、どうなったかということをよくよく見ていただくと、今、言った思いがどれほど真剣で、単に自分たちのことだけでなくて、いわゆる人類全体の願いにもつながるんだということをしっかり分かっていただくようにする。きちっとした考え方をする動機付けをするための対応に注力するということをやるのが、自分の使命だというふうに思っています。
実際、この活動をやる上での自分の行動原理の一番大きいところは、広島平和記念都市建設法という法律があって、広島の市長は平和都市建設に不断の活動をしなければならないというふうな規定もありまして、それを実行すべく、今申し上げたような考え方をとって活動しているというところであります。
その他の質問
デンマーク国王の広島平和記念公園訪問について
記者
本日の午前中にデンマークの国王が平和記念公園にいらして、慰霊碑の献花であったり(広島平和記念)資料館の視察などをされたと思いますが、その件に関して市長の受け止めを伺いたいのと、併せて、国王の献花後に市長が説明された内容だったり、他に交わされた会話などがありましたら教えていただきたいです。
市長
今日のデンマークのフレデリック10世国王ですか。非常にお話ししていてフランクなお話ができる方だなというのが第一印象でありましたね。(平和)記念公園、あそこに来る前日は、日本の旅館みたいな温泉に泊まったと。(庭園の宿)石亭とか言っていたかな、廿日市の方で。「温泉いいんです」とかっていうような話とか、「そうですか」とかいう感じで。今回が実は2回目なんでねと。1987年って言っていたかな、っていうような話を向こうからされて、それで「広島にぜひ行きたいということだったんです」ということだったので、「それならば」ということなんですけど、改めて平和(記念)公園の成り立ちとか、この施設群の説明をもう一回しますからということで、一応聞いているし、むしろ一緒に来ている外務大臣にしっかり言ってやってくださいと言われるから、両方来てもらってお話をしたというふうな状況でした。
いつも平和記念公園に来たときに、来る方々への説明は、今の平和(記念)公園の場所というのは原爆投下までは広島の市内の中心街で、旅館、喫茶店、映画館等がある市内一の繁華街で、数にして4,100人ぐらいの方が住んでいたと、そういう地域なんですよと。そこに1945年8月6日8時15分に原爆投下されて、ちょうどこの慰霊碑のところから北東に向かって300メートル、上に600メートルの地点で原爆が炸裂して、地表温度にして3,000~4,000度の高温になり、爆風を吹いて何もかも灰じんに帰すというような状況になって、この地域は大変なことになって、それを市が決断して、復旧するんじゃなくてここをきれいにしようということで、それから5年後にここを公園にするということにいたしまして、2年かかって慰霊碑をつくり、それから、また5年かかって(広島平和記念)資料館をつくって、原爆投下から11年目にしてこの公園がようやく出来上がったと。
そういう意味で、焼けただれたあとに土などを盛ったから、まだこの土の下には遺骨なんかもあると、そういう地なんですよと。そこで慰霊碑に書いてある文面を来た方々にぜひ見てもらいたいと。「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」と書いてあるあの文章は、ここに来たときに棺の中に、今ですと34万4,306人の方の、亡くなった方の名前が入っているのですけど、みんな被爆者でね。原爆が落ちた当時は14万(人)だったんだけど、そのあと放射能を浴びて死んだ方がいて、その数になっているんだけど、その方々が「自分たちのような思いを他の誰にもさせないでくれ」と、そう皆さん言うんです。それが本当にそうだなというふうに思った方は、安らかに眠ってくださいねと。自分たちは戦争とか核兵器使用という、そういう過ちを二度としないと約束していただくことで、その気持ちを慰霊すると。そのために書いてあって、日本語ではそうですけど、下に英文とか各国語で書いてあるんで、ぜひそれを言っていただきたいと。
慰霊碑のあとに、火がともっていますけど、あれはまた、それから(平和記念)公園ができて8年後に日本でオリンピックをやったときに火をあそこにともして、原爆がなくなるまでともし続ける、なくなったときに消すと、そういう誓いをしてもらっていると。こんな場所なので、ぜひこの思いを各国の為政者に、もちろん来る度に言っているので、こういったことをぜひ広く伝えてくださいと言ったら「やりましょう」というような感じで、どうぞじゃあ(広島平和)記念資料館を見に行ってくださいと御案内したというのが朝の展開でした。
8月3日広島電鉄の駅ビル乗り入れ開業について
記者
昨日、広島電鉄が8月3日に新しい駅前大橋線開通することを発表しました。8月6日よりも前にということでこの日程になったというふうに聞いているんですけれども、この開通発表の受け止めと、この開通に向けての期待について教えてください。
市長
(8月)3日というタイミングでいろいろと考えながらやっていただいたんだなということで、配慮していただいたかなと思っています。これ実際、あそこに乗り入れるためには路線を引いた上で運転士の方もトレーニングしなきゃいかんから、日程なかなか確保も大変かなと思っていたけど、8月6日という日が、そのあとに来ているというふうに考えれば、広島駅から(広島平和記念)資料館、平和記念公園に行かれるような方も続々とあったりする中で、今度の(平和記念)式典は、駅から電車を使って来たというような方々がおられるとすれば、ある意味で、80年というこの歳月の中で、被爆直後の市内の公共交通が途絶えた中で、関係者が、一生懸命頑張って、直ちに走らせたという、そういう歴史を持つ電車、それに乗って平和記念公園へ行ったというようなことになりましょうから、ある意味で、ヒロシマの思いを受け止めていただけるいい素材になったんじゃないかなというふうに思います。
職員研修資料での教育勅語の使用について
記者
今年度の新規採用職員研修のことですけれども、昨年4月も同じような質問でしたが、教育勅語を引用されて、日本国憲法の前文なども引用されていますが、去年と資料は踏襲されていると思いますが、今年はどういったような説明を実際されたのかお教えいただけますか。
市長
一語一語同じとは思いませんが、研修の考え方は終始一貫しておりまして、教育勅語についての私の受け止めを皆さんに聞かせると、こういう展開でしています。そのやり方は役人となって、役人としての物事の考え方、そして、私は、実は温故知新というのを座右の銘にしていまして、過去のことをよく勉強して、そして、いいところを磨きをかけてよくするというふうなことをやっているんですよということを言いながら、こういう文章がありますと。この文章は、教育勅語といわれるもので、明治憲法のもとで作られたものであって、現行の憲法では、天皇という地位が、いわゆる国政を総覧するような立場ではないので、到底、こういったものは、もう、現行の憲法では認められないし、できるものじゃないんだけれども、意見によっては、「教育勅語はええと」というふうなことを言う方もおるんですよと。そういった方々に、今は、もう、日本国憲法で否定されているものだから、使ってもいけないと、よくないんだと言う方がおられるんだけれども、いいということを言われる方がいる、そういう方に対しての自分としての判断の仕方は、新憲法のもとで、これは、到底、認められるものじゃないというふうな事実なんだけれども、いいという方については、そこに書いてある内容について、今でも、いいというふうに言えるものがあるんじゃないかと、そういうふうに言っているというふうな受け止めをして、両方の意見をちゃんと聞くということをやっていますと。こういうのを参考にして、皆さんも温故知新ということをやってみてください。こんな流れで話をしています。
記者
日本国憲法前文も去年から引用されていますけれども、その上で、なお、やめるべきだという批判もあって、文書で抗議文出されたりしたことも直前にあったかと思いますが、こういうリアクションに関してはどのように受け止められていますか。
市長
私の、今の教育勅語に関する考え方、内容を説明しているのに、私の説明の仕方を止めろというふうなことにしか受け止められませんからね。私自身としては、職員に対する知識、働き方についての自分なりのノウハウを伝授するやり方として、先ほど申し上げた温故知新を大事にして、いろいろな対立する物事を考えたときに、それを自分なりに整理して位置付けるということを紹介しているわけですから。私の考え方、納得いただいていないなら、納得いただく他ないかなというふうに思っていますね。
記者
なかなか分かってもらえないので、これ以上対話のしようも…。
市長
対話というか、言うべきことは言っているわけですからね。他の場面では、いろいろな意味で思想・信条の自由だから、言いたいことは言わせろとかいう主張もされるようなところでしょうからね。お互い様ということでよく考えていただきたいと思いますね。
記者
今ほどの質問に関連してお伺いしたいんですけれども、市長は、就任翌年から研修で教育に関する勅語の一節を使用しているというふうに認識しているんですけれども、当初から、様々な意見があるというものの例えとして、教育勅語を使っているんですか。そうではなくて、当初は、教育に関する勅語の一節が、市長の思いとして評価できる。だから、研修でも使用している。どちらになるんでしょうか。
市長
最初の方ですね。私が市長になって、多くの当時のマスコミの方が、この市長は前の市長と比べて右なのか左なのかという探りを入れるためにいろいろな質問をされたんですよ。私は、極端な例で言ったら、「私は自民党ではありませんと。濁らない市民党です。」というようなことも言っていましたし。
それから、さらに、厚生労働省という役所で働いていて、公務員の時代、自民党の先生とも、社民党の先生とも、含めて野党の先生方とお話するというふうなときに両方の話を聞いて、行政としてどう処理するかと、そういう立場でやってきたんでってなこと言うんですけどね。その上でどっちですかって、こう聞くわけですね。そんな中で、典型的な憲法改正をどう思いますかとか、それから、今みたいに教育勅語をどう思いますかというふうなことを聞かれたんで、それについて、今みたいなこと言うんですけれども、なかなか収まらんと。あとは、被爆者の援護についてをどう考えるかということで、こうだと言ったら、それは、いろいろありまして。で、その中で、きちっと使えるもんとしてっていうのを、この憲法の条文にも関わるしということだったので、教育勅語を使って、こういうふうに考えているよということを言うようにしてきたんです。
記者
なので、当初は、教育に関する勅語が、市長として評価しているものとして、研修でお話されていたのか、当初から様々なものの見方があるよという例えで使用しているのか、どちらなんでしょうか。
市長
今の質問ですと、今度は後者ですよ。
記者
後者なんですか。分かりました。その上でお伺いしたいんですけれども、この問題が広く報道された昨年度は、令和6年度ですか、市長自身は、過去の発言と比べて、ちょっと後退したんじゃないかと。ちょっと回りくどい表現としてお話しされているんじゃないかというような見方もあるんです。それは批判を受けたから、ちょっと回りくどい表現として、様々なものの見方があるという、その例えとして使用したのではなくて、当初から。
市長
当初から、もう一遍言いますよ。いろいろ意見があって、教育勅語そのものをどう受け止めるかといったときに、教育勅語そのものは、現行憲法下では成り立たないものであるということは自明の理なんですけれども、それでもいいし、そういうものを復活すべきだとかいうぐらいのこと言う方がおるわけです。ですから、そういう方々の意見にすれば、その中で全部が悪いと言う方もおる。いや、一部がいいと言う方、いや、全部がいいと言う方もおると。そういう中で私の整理とすれば、教育勅語というそのものは現行憲法では認められないものであるけれども、「復活しろ」とか、「ええ」とか言われるんであれば、その方々の思いは、個々の部分、いいものがあると、そういうふうに受け止めていくということにしようとそういうふうにやっていますよということを、皆さんに紹介して、私はそういうふうに受け止めていますということで。
記者
様々な評価があるものの例えとしてお話されているということですよね。であれば、もっと別な例えがあるようにも思うんですけれども、その上で、あえて教育に関する勅語の一節を使うっていうのを、その理由についても教えてください。
市長
私、先ほど言ったように、実際に憲法改正とか、教育勅語について、市長になって真剣に議論した方がおられますからね。そのときに考えた私にとって好事例だと。憲法そのものについて深く考える、天皇制についても言及されているし、戦争という要素も入っていたしということなんです。
元市議らによる住民訴訟について
記者
昨日、提訴された住民訴訟について、現段階で、もしお尋ねできることがあればお聞きしたいんですけれども。
2021年の(旧広島)商工会議所ビルと(旧市営)基町駐車場の財産交換について、差額があるにもかかわらず、ほぼ等価で交換して市に損害を与えたんではないかということで、それを、その損害を取り戻すように訴える内容なんですけれども、現時点で担当課の方は訴訟前の住民監査請求の段階では、事務は適正だったというふうに言っているんですけれども、市長として現時点で、こうお考えであるとか、対応の方針があればお聞きできますでしょうか。
市長
まだ担当から上がってきてないし、もの見てないからあれなんですけど、ただこの経過に関しましては、元市議という方も市議であるときにこの案について、賛否を問うて、議決に加わっておりましてね、そのときは反対だったんですけれども、議会そのものではきちっと説明し、了解を得ているという手続き論を、私は前提に考えていけばいいというのは、基本的立場です。
そしてさらに、この方そのものは、住民訴訟の前に住民監査請求も出しておられましてね、議員辞めてから。議員時代に少数意見で通らなかったということを、前に御納得いただけないということで、引き続きやっておられるんでしょうけれども、これに関わる手続きとして監査請求のときにも、財産交換に関わる基本的な手続き、説明いたしまして、この方の請求そのものは却下であるとか、棄却であるとか、手続き的に、まず、訴える期間をどうかしているんじゃないかとか、内容的にも正しくないんじゃないかということで、両名、却下、棄却という形で処理されています。それが納得いかないということでの、今度の提訴ということでありますから、市とすれば、今まで申し上げてきたスタンスで対処することになるんじゃないかなというふうに思っています。
米国関税措置について
記者
トランプ関税についてお伺いしたいんですけれども、まだちょっと先を見通せない中だとは思うんですけれども、市の方で相談窓口も設置されたかと思うんですが、その利用状況と今後の対応方針など、分かる範囲でお伺いできますでしょうか。
市長
はい。これについては、一応、窓口などを設けて御相談できるようにしていますけれども、具体的に今、どこっていう話で御相談などを受けているっていう状況にはなっていません。ですから、関係者の方も、今のアメリカと日本国政府の交渉をしっかり見ながら、どう対処するかっていうようなことを考えておられるというふうに思うんです。その典型として、まず、市内であれば、一番影響を受けそうなマツダがありますけど、こちらの方では、この影響を受けるかも分からないということで、用意周到な体制をしようということで、関税のその対応チームを立ち上げて対処しておられる。
そのときの方針としても、まずは、値段が上がったとしても売値を抑えるということでしょう。原価低減であるとか、固定費の削減っていうようなことの自助努力をする方策を考えると同時に、売り上げが減っても、販売店とか従業員にそのしわ寄せが行かないように、あるいは、それを最小限に抑えるようにするための方策という。そのための支援策は、国の方で臨時救済の資金、必要になればということで、低利で、お金を貸す用意もあるというようなことを今、盛んに言っていますからね。そういった対応をされていると思うんです。そういったことを踏まえながら、マツダとも連絡を密にしながら、もし、市として対応できるようなことがあれば、可能なかぎりの協力をしようというスタンスで対応しています。実際、マツダが困れば、ぐるっと回って、翌年度以降になるかも分かりませんけど、税収などに響いてまいりますからね。我が市のとても重要な課題にもなるということでありますので、はい。
※( )は注釈を加えたものです。
配付資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画総務局 広報課報道担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2116(報道担当) ファクス:082-504-2067
[email protected]
