2025年9月26日記者会見「協同労働インターンシッププログラムの実施について」外6件
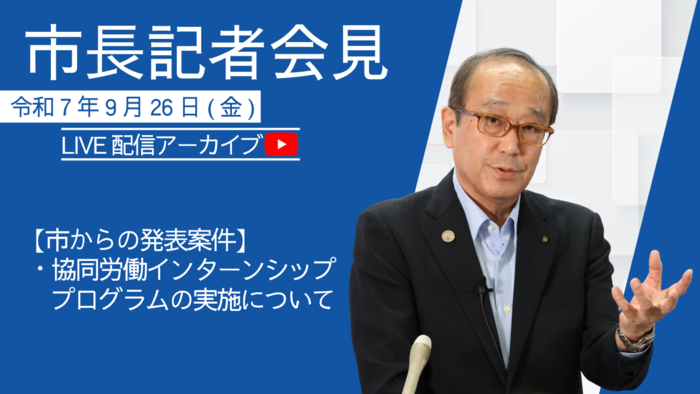
- 日時 令和7年(2025年)9月26日(金曜日)午後2時30分~午後3時15分
- 場所 市役所本庁舎11階第1会議室
市からの発表案件
協同労働インターンシッププログラムの実施について
市長
それでは、「協同労働インターンシッププログラムの実施について」の説明をしたいと思いますが、その前に、我が国におけます「協同労働」の歴史というかそういったものについて少し触れておきたいと思います。
世界に目を向けてみますと、その歴史は古くて、19世紀の産業革命時代に欧米で生まれたというのが、協同労働でありまして、その後発展しながら着実に市民権を獲得してきたとそういったものだと思っています。
日本においては、高度経済成長期以降、労使関係の対立を始めとした、利益追求型の働き方、これに綻びがでる、顕在化するといった中で、労働者一人一人が主体的に経営といったものにも参加できるような働き方、すなわち協同労働が注目されるようになったというふうに受け止めています。
海外での成功事例などを踏まえて、1990年代に、それまで法定化されていなかった協同労働といったことについて、日本国内でも法定化の動きが始まりまして、相当長期にわたって侃々諤々の議論が行われた末に、2020年に、協同労働の理念を一定の要件を満たす団体に法人格を与えるという「労働者協同組合法」の法案が国会に提出されて、全会一致で成立すると、そういった経過があります。
この間には、私が市長になったというものでありますけれども、この法律は2年後に施行されまして、それから来月1日でちょうど3年になると、そんな時点であります。本市におきましては、法律の制定より前に、全国に先駆けて、2014年から協同労働促進モデル事業というものを実施いたしまして、今年の4月には、協同労働団体の立ち上げであるとか運営、こういったものの支援拠点となります広島市協同労働支援センターを開設するなどいたしまして、協同労働の普及・促進に力を入れて取り組んできているところであります。
現在の日本の労働環境において、非正規雇用であるとか、障害のある方の雇用の確保等々、様々な問題が生じておりますけれども、この「協同労働」これは、会社や団体などに所属しながらも、経営者や上司から指示を受けて働く、いわゆるビジネス的な働き方といったものとは少し異なっておりまして、自分たちで何をすべきかを考えて実行に移すことできる。そういう意味では非常に納得感の高い、納得度を持って働くことができるという、いわば「根源的な働き方改革」をするための仕組みではないかと思っています。これが普及することによって、働く人がそれぞれに、労働条件を自分で決めることができるし、そして、できる範囲の中で働くという選択も可能になるといったものだと思います。
また、協同労働、これは成熟期を迎えた社会におきまして、利益をひたすら追求するという「競争社会」だけではなくて、持続可能性のあるものを追求する協調型の社会での働き方を実現可能とするものであろうかと思います。この働き方をより多くの方に知っていただいた上で、実際にそれに参画いただければというふうに思っているところであります。
今日は、その実現のための取組ということでの御紹介をさせていただきます。資料を御覧ください。
協同労働について、より多くの方にその仕組みを知っていただき、実際に参画していただくようにするために、本プログラムでキャリア研修、そして現地のインターンシップといったものを実施いたします。
これらをとおして協同労働に参画する具体的なイメージ。これを持っていただくことで、将来的な協同労働団体の立ち上げにつながる機会の創出、あるいは知見といったものの形成を図っていきたいと考えます。
実施内容としては、まず「キャリア研修」として、協同労働ガイダンス、そしてグループワーク、これを行います。協同労働への理解を深めるとともに、自己のスキル、自分の技能ですね、これや経験、これをまず棚卸しをして、協同労働、あるいは地域貢献に活かせる技能スキル、こういったものを探求することになります。
次に「現地インターンシップ」として、協同労働団体の視察と意見交換を行って、協同労働団体で活動する方との交流、こういったことをとおして、その働き方であるとか価値観、さらには地域課題といったものへの理解を深めるとともに、自分のスキルなど、協同労働への活かし方といったものを考えてもらうようにします。
これらの取組は、10月から11月にかけて、市内の民間企業の従業員、こういった方々に参加いただきたいと思います。
この機会を通じて、参加者の皆さんに協同労働の仕組みを知っていただいて、興味を持っていただく、そして実際に協同労働に参画していただきたいというふうに思っています。
以上が、協同労働インターンシッププログラムの概要であります。よろしくお願いします。
記者
今御紹介があった協同労働についてなんですけど、市としても先駆けて普及に取り組んできたということで、今いろいろおっしゃっていたんですけど、対等であったりとか、そういう何か一番の市長が考えるメリットというか、良さみたいなところっていうのを改めて教えていただきたいのと、農作業であるとか子どもの居場所づくりとかっていうふうな35団体がすでにあるということなんですけど、どういった分野でこれから広がっていけばいいなとかっていうのがもしあれば、お願いします。
市長
メリットというか、個々のメリットと全体的なメリットといいますかね。これが普及されることのメリットというのは両方あると思うんですけれども、全体的な位置付けからすると、例えば地域の担い手不足ですね。いろいろな問題について、それを解決するための担い手がいないという社会問題が大きくなる中で、地域にとってその担い手を確保するときに、働き手を今までの労働形態で確保しようとなるとなかなかうまくいかないという実態もあると思うんですね。
そうすると、例えば民間企業で働いている現役世代でありながらこの協同労働団体に参画することで、その団体そのものが地域貢献活動を行うという組織であれば、そこで地域の担い手にもなれると。こういったことができると思うんですね。しかも、参画の仕方が、この団体全体でどういったことをするかというのを決めるときに自らも参画して、こんな仕事をしたい、しようと、こんなふうなことがありますので、様々な団体があればいろいろな形での働き方ができるし、自分の持っている技能・技術をうまく発揮するということができるというふうに思うんですね。
そういう従業員を持っている企業にとっては、例えば自分のところで働いている従業員が地域に出て積極的に働くということを認知する、いわゆるSDGsじゃないですけれども、そういう世界全体のことを考えながら、かつ、CSRやら企業の社会的責任も果たすことを許す企業であるということを宣伝できるといいますかね、実際に認知していただく。
そうなれば、地域、顧客、そういったところとの連携も深められるといいますか、多様な働き方を認める企業だということで、企業としてのPRにもなるというようなこともあるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。いずれにしても、多様な働き方ということ、いろいろな意味で可能になる働き方だと思っていまして、とりわけまちづくりとかっていう視点で、地域貢献型の働き方とは極めて親和性が高いんじゃないかなというふうに思っています。
個人のキャリアを考えたときに、どの年代でそういう働き方をするかについての結構柔軟性がありまして、企業の中でキャリア形成をしながら働くと、趣味を生かして時間をうまく有効活用していくっていうような人にもうまくフィットするし、企業群でぐっと働くということを引退する過程にあって、例えば地域で貢献しようかというふうになったときに、定年後の働き方を少しでも定年前から、そういったグループに入って仕事をしながら関係者と地ならしをして、うまく生活環境を組み替えていくとか、そんなことも可能になるというふうに思っていまして、いわば、資本主義の中での大きな労働を支える、この労働システムをある意味で補強、補完できるような働き方というものにならないかなというのが自分のイメージです。
その他の質問
宿泊税について
記者
広島県の宿泊税の関係で伺います。先日、県の方が宿泊税を徴収した場合の市町への税収配分の方針案というのを公表しました。宿泊者数に応じて配分するものと、市町からの事業提案を受けて、県がこれを審査して、それに基づいて配分するものに大きく分かれるかと思うんですが、まずこの広島県の方針について、市長としての受け止めをお願いします。
市長
よく考えておられるなというふうに思います。それを前提に、我が市としてどういった対応をすればいいかなというのがこれからの課題ですし、それをやるための詳細というか、それをもう少し確認できたらなというふうに思っています。
記者
宿泊者数の人数でいくと、広島市が県内で6割ぐらいを占めているかと思うんですけれど、これは仕組みによっては10分の6を広島市が受け取れない可能性もあるのかなというふうに思うんですけれど、その辺りで一番観光客を受けている市として、税収配分が少なくなるとか大きくなるとかっていうことに関しての懸念とかっていうのはありますか。
市長
その懸念はありません。というのは、見るかぎり宿泊割合分という形での交付金の配分と、それから提案分という配分があって、提案というかアイデアがしっかりしていればそちらの方にたくさん出すと。(観光客が)入ってくる割合で配るのは全体の10パーセントということですからね。こちら(宿泊割合分)の方はとにかく取る方の割合において、全体の額を押さえて使ってくださいよと。こちら(提案分)の方はアイデア次第で、地域限定のアイデアですしね。うまく使ってもらう、いいアイデアがあれば、そちらに税源を使おうというふうに調整されていますからね。むしろ提案型のところでしっかりお金を引き出して使えるようになればいいんじゃないかなと思っていますけどね。
記者
最後に、今の段階でこういう提案をしようとか、こういう考え方があるというのは、今ありますでしょうか。
市長
少なくとも示された基準というかアイデアの中で、要件として書いてある言葉もあったんですけれども、単一の市町では完結しない課題、こういったものの解決に向けてアイデアを出せばというようなことが書いてありましたので、ここのところを例えば膨らませて、単一の市町では完結しない課題ですから、当然関連する近隣の市町と連携してアイデアを出すような課題を捕まえてきて、それに対する施策を一緒になって考えるというふうなことがあるんじゃないかと思うんですね。
そういう意味では、近隣の市町でも今みたいな思いを持っている方あると思うんで、早急に相談してでも、どんなふうにしようかということを協議しながら、早期に県の方で制度の詳細を示してもらうというふうにして、使える財源はしっかり使っていきたいというふうに思います。
記者
本当に最後に、次もし財源が今度入ってくると思うんですけれど、金額はともかくとして入ってくると思うんですけれど、使い道の部分で今何か考えられていることってありますか。
市長
使い道の部分は、元々この観光政策ということですから、観光政策に絡む。今ですと、広島市とはいわない、県でもいいんですけれども、近隣市町含めて観光客の方がなるべく長く滞在していただくとか、夜しっかり宿泊していただくとか。それと、来る方々を長く滞在していただくためのいろいろな取組を一緒になってやる、それに必要な経費をこういった税金を使って確保していく。しかも近隣の市町と一緒になってこの地域をぐるっと、お客さんが回っていただけるような対策とか施策を考えて、それに必要な財源確保として要求していくというようなことがあるんじゃないかと思うんですけど、抽象的ですけどそういう感じですね。
勝手踏切について
記者
広島市安佐南区祇園の勝手踏切では、来週30日に立入防止柵が設置され、封鎖されます。改めて、受け止めをお伺いします。
市長
勝手踏切は前の会見のときにも申し上げたんですけれども、歴史が鉄道敷設される以前から地域の方々が生活道で暮らしていると、そこに後で鉄道を敷くようになって、鉄道軌道法でそういったとことクロスするのはいかんよということになったんですけれども、いかんせん人の通りの方が先にありましたから、鉄道をあとでやるというのはなかなか難しい。
そうすると、使っていた方々が納得度、というか納得するということをした上で、規制するというのが筋だろうということで処理をずっといろんな形でしてきたものだと思うんですけれども、今回、その事故等あったことを受けたりとか、地元の方の理解がしっかり進んで、じゃあ閉鎖していいですよということになったということでありますので、ある意味でそういう関係者の御協力、御理解がいただけたということで、非常に喜ばしいなというふうに思っています。
観音地区下水道工事施工に伴う道路陥没事故について
記者
本日で西区で起きた道路陥没の事故から1年がたちました。まず、これについて、現在も工事が続いていて、避難者の方もまだいらっしゃるような状況ですが、これについて市長の受け止めをお願いいたします。
市長
はい。これはまずもって、おっしゃったように、非常に御迷惑をかけている課題であるというふうに思っています。実際、昨年の9月26日発生ですから、1年経過ということでありまして、大変に御迷惑をかけているなというふうに思っていますけれども、思いつつも対処を、これからの対応をしっかりしていかなきゃいかんというのは当面の課題です。
事故当初、避難を呼びかけた46世帯、人数にして86名の方々、これらについて、そのうちの35世帯の方に関しましては、ある意味で帰宅できた方と、それから転居を終えた方という形で、なんとか事象自体は、なんとか終息に向かっていると思いますけど、残った世帯がまだ11世帯あります。その11世帯のうちの8世帯ですかね。こちらの方は、自宅そのものが損傷しているとか、建物がまだ復旧工事できていないということで、そちらに帰る予定ですけれども、まだ仮住まいという形であります。まだこれも完全決着でないと。あと残り3世帯の方は、転居先ですね、市営住宅などを含めて、鋭意調整中で、なんとか転居先を見つけていただくというようなことをやっています。
そういう意味では、長期の御不便をおかけして申し訳ないなと思っているんですけれども、可能なかぎり、元の生活に戻っていただくようにしていきますし、工事の受注者と連携しながら、引き続きしっかり対応していきたいというふうに思っています。
記者
工事につきましては、現在、新しい下水道管の敷設であったり、来月からは、その調査に向けた工事っていうのも始まるというふうに伺っておりますが、工事の進捗については、こちらについては順調に進んでいるという受け止めでしょうか。
市長
はい。手順を定めて、順調かつ確実に進めているというふうに御理解ください。私自身も陥没したときに早くできるんじゃないかなと希望的観測のもとに、コメントを加えたりしていたんですけれども、しかし、いったん沈んだところを原因究明ができてない中で、上部から修復しながら、修復作業で土地を固めた上で、現場に行ってその原因を調査して、そして、それに基づく対応策を考えて、さらにもう一回、本来の下水管をつくっていくという手順を今度確実にやるとすると、一個一個の作業をきちっとやらないといかんと。こういうことだという説明を担当者から受けていまして、今そのものは傷んだ下水管などの代替する施設をきちっと整えると。
その工事のために、その周辺のところ、地盤沈下収まっているようですけれども、その関係で、まだちょっとカチッと収まってないかも分からないということで引き続き調査しながら、代替の措置をした上で、そして、その沈下を防いで、直接の損傷現場をまた別途、地下相当の部分にありますから入り込んで、入るために人が接近するための、また操作をしなきゃいかんのでね。そういったことをやることで時間がかかるという説明を聞いています。
埋め戻しなどの作業っていうのは10月までですけど、それらの作業をやるための究明のための作業となるともう少し時間がかかって、原因究明までは今言った作業を踏むと2年ぐらいかかるんじゃないかという説明を受けていますから。それから究明してまた新しくやっていくということですからね、もう3年は遅れているということになるかなというふうに思っています。
記者
私も現場周辺を取材させていただいたときに、やはり工事まだ現在も続いておりますし、これからも続くっていうところで、まだ交通規制も続いているようなところで、やっぱりその先行きが見えないことへの不安みたいな声も住民の方からは伺いました。
やはり、住民の方、求めているのはそういった情報なのかなというふうにも感じたんですけれども、そういったその情報提供の面で、市としては、これからどういうふうに対応を取られていく考えでしょうか。
市長
今申し上げたように、直接被害を受けた方々とは接触しながら、次の居住先を探すという中でお話を聞けば、説明できているわけですけれども、それ以外、その周りの方々、ずっと閉鎖されて、そこが通れないって一体どうなっているんだろうってことを思われる方おられましょうから、そういった方々には、今回1年たつということで報告させていただきましたけれども、私が申し上げたようなことをもう少し刻み刻み、周辺の方々にも知っていただくと、進捗状況をもう少し丁寧に引き続きお知らせするということをやることで御了解いただけないかなというふうに思っていますけどね。
記者
それは具体的には例えば説明会であったり、どういったような手段が考えられますか。
市長
その対象者がなかなか限定的なこういう皆さん方、マスコミを通じて正確な内容を発表するというようなこともありましょうし、御近所の方で付近の方々で、情報を得たいという方がおられれば、そういった方々に向けての情報提供、少し工夫した方がいいかなというふうに思いますけどね。
記者
ありがとうございます。ごめんなさい、最後に一点。今回の市議会の中で、費用面についても出てきたと思います。まだこれから物価高騰もある中で、もしかしたら、またこのお値段というところが膨らんでくる可能性もあるかなと思いますが、この辺りの費用分配も含めて、どういった御対応を検討されていますでしょうか。
市長
本当に想到でしかやっていません。専門の方々の話で事故現場を撮られていた写真で、機械のせいなのか、操作のせいなのか、地形的な状況なのか、いろいろな要素があるということですし、かつ、そういった操作がうまくいかなかったこと、直接の破損状況などをまず見るということをやらないとできないということと、そして破損したことに伴う原因究明で、その責任といいますか、どうなるかによって、それに関わる費用負担も、問題になってまいりますので、それらが今申し上げたように、きちんとやるために2年ぐらいかかりそうということなので、それが終わってからということにしていただけないかと思うんです。
いずれにしても費用負担については、きちんとした原因究明をしてからやると。その間の必要となる費用等について、避難されている方への手当は今、施工業者から出していただいていますから、それらを精算して市が持つのか、業者が持つのかと、そういったことをその後、やっていくということにしたいと思っています。
記者
陥没事故に関連してお伺いします。市長がおっしゃられている、およそ原因究明に向けて2年かかるのではないかと、で、元々の下水工事に関しても3年以上増える見通しであるという、この遅れについて…。
市長
遅れはもう、事故が起こって1年たちますから、これから2年でやると単純に少なくとも足せば3年は遅れてしまうんではないかということ。
記者
大切な工事が事故によって遅れてしまうということについての市長の受け止めをお聞かせいただきたいと思います。
市長
これは、やはり最初に、こういった下水道を完備するということは、我がデルタ市街地における豪雨災害とかで、大量の雨が降ったときの水処理で陥没(冠水)するところをなくしていくという、そういう目的で始めて、その計画内に収まるのがいちばんだったんですけれども、出っぱなしのところ、工事を始めてすぐのところで、こういった事故になりましたので、予定どおり進まないっていうことは非常に残念なことでありますけれども、現場の担当者から聞くと、最善を尽くした作業をやってくれていますので、ぜひ、被害者の方々への救済ということを着実にしながら、遅れてはいますけれども、原因究明を可能なかぎり早くして、それを踏まえた適切な対策を早く考案するというか、企画立案することで、初期の目的に向けた、年月は多少かかったとしても、確実な工事をやっていただくということを期待しています。やらなきゃいかんと思っています。
トランプ大統領の広島訪問について
記者
トランプ大統領が日本を訪問するという報道があったかと思うんですが、その件に関して伺います。かねてから、広島、アメリカに限らずですけれども、各国の為政者に広島訪問を促されてきたかと思うんですけれども、今回、トランプ大統領が日本に訪問するに当たって、広島訪問への期待とかがあれば教えてください。
市長
大統領訪問に関しては、もう既に今年の1月に駐日米国大使館に行きまして、当時の臨時代理大使のキャサリン・モナハンさんに、長崎の市長と一緒になって、是非、大統領の訪問ということでお願いをしておりますので、その考え方は変わっておりません。
最新情報ですと、今言われたように、訪日の可能性があるということですので、政府間の日程調整等の状況を見ながら、要請するかどうかを検討するということになろうかと思いますけれども、いずれにしても来ていただくという方針は変わっていないし、その背景、気持ちは、今の国際情勢、混迷を極めていますから、そういった中で、この核兵器使用のリスクが高まっている、そのことと、核兵器を使うと、被爆の実相、こんなになるんですよということを、是非とも、我が地を訪問して見ていただいて、そういったことをしないようにしようという決意を固めるといいますか、そういった絶好の機会にしていただけるようにしたいなというふうに思っています。
記者
改めて被爆地訪問を要請されるかどうかは、この日程とかを見て、要請するかどうかを検討するという。
市長
そうですね。日程調整の中で、全然来るスケジュールがありませんというのも空振りしてもいかんですし、もし、予定があってどこかというようなことであれば、是非ということを付け加えて言えばいいし、元々臨時代理大使にチャンスがあれば、是非来てくださいということは伝えていますので。そういうふうに思っていますけれども。
新アリーナの建設を求める署名について
記者
今日、(広島)ドラゴンフライズさんからも出たんですけれども、新アリーナについて10万筆の書名を集めたということがございましたが、その件について市長の受け止めを、ひと言お願いします。
市長
署名活動というのを経験したのは、サッカースタジアムのときも、これはもっと多かったのですけれども、経験したんですけれども。それだけの署名が集まるということは、ファンの方が多くおられて関心があるという証しであることは間違いないというふうに思っています。
それを受けて市としてということですけれども、これは、こういった署名活動が成されている今の状況もしっかり把握した上でやらなきゃいかんと思うんですけれども。多分、この運動は新しいアリーナを実現するためにということで、今までの事例研究とか課題なんかを整理して、勉強しようじゃないかということを関係者の中でやっている中で、そういったことを応援しながら実現させてほしいという気持ちの高まりがあるということを、みんなに示したいということで出されていると思うんですね。
実際にそういったことを踏まえて、要請をしたいというふうな申し入れを受けていますからね。そのときに改めてその話をきちんと聞いて、意見交換するということにしていきたいと思いますけれども、私自身は、そういったその皆さんの思いをしっかり受け止めながら、まちづくりをやっていくのはある意味で本務ですからね。本務を果たすために、どういった内容の要請なのか行政として、あるいは市として、どんなことができるか、何が必要かというようなことをそういったお話の中で整理して検討していきたいというふうに思っています。
アストラムラインの延伸について
記者
アストラムラインの延伸計画で伺います。昨日から、沿線住民向けの説明会が始まりました。私も行ってきたんですけれども、もちろん一定に期待の声はあるんですけれども、一方で費用対効果がやっぱりどうなのかと、概算の建設費が3割ぐらい上振れしたものですから、さらに物価高騰で高くなるんじゃないかとかいう思いもあって費用対効果、採算性なんかを疑問視するような声が結構出ています。
市としてのアストラムラインを広域公園前(駅)から西広島(駅)まで延ばすことによる最大のメリットというか、巨額の事業費をかけてもやる意義というか、その辺を確認させていただきたいのと、あとは、費用を多分、事業認可とかそういったところに向けて精査をされていると思うんですけれども、どの辺りのタイミングで示していきたいのかという、その2点をお願いします。
市長
今言われたように、アストラムラインの延伸、非常に関心が高いというふうに受け止めていますので、費用対効果とか、どんなふうになるかという、これから起こりうることに関する問題、それに関しての関心、結論を聞きたいということなんでしょうけれども。それ自身、少なくとも費用とかなんかについては、どれくらいかかるかは現時点では確定できていないから、おおむね今までの中で概算が出ていますけれどもね。それが減っていくだろうということは、誰しもなかなか想像できないから、どれくらい増えるかということになっていくでしょうから。私自身としては、ここで改めていろいろなことを御心配いただいている方に、アストラムラインの意義というか、それあえて強調させていただきたいと思うんですね。
アストラムラインの延伸については、これまでも公表していますけれども、この事業は2036年、令和18年ですからね。今、令和7年でしょう。だから、これから11年かけてでも完成させたい事業ですよという、そういう意味では大型の事業というふうに受け止めていただけると思うんですね。
この大型の事業を市としてやりたい、議会にも諮って着実に歩を進めているというふうに思っていただきたいんですけれども、そういった事業に着手しているのは、そもそも、本市としてこのアストラムラインのその位置付けは、1990年、平成2年に、西風新都のまちづくり、これを本格的にスタートしているんです。その西風新都のまちづくりも、あの地域に人が住んで、働いて、学んで、憩うという、こういう複数の機能を備えた都心をつくろうということで、事業に入る。
そのまちづくりを支えるということと、まちができたときに、デルタ市街地とこの西風新都を結んで循環型の公共交通をそこにつくらないとまちがつながらないでしょ。ですから、その手段として、まず公共交通ということで、アストラムライン。ダジャレで、「トラム」というのと「明日」を掛けて、「明日」と「トラム」で、未来に向けての新しい交通だということでやり始めたんですよね。ところが、その途中でどうも資金調達に、今言われたように、資金がどうなのかというのが当時あって、調達難だと、しかし、造らないかんということで、多分やぶかたなく、今の広域公園前の駅でストップして、あそこにスタジアム造りましたから、そこまで機能するんでとりあえずいいだろうということで、作業を中断したという経過があったんですね。
私自身は2011年に市長になりましたから、そういった経過を知って、しかも(広域)公園前の駅からもレールは出ているんだけど途中でちょん切れているわけですよ。完成していないんですよね。ですから、こういった大型の事業について、志半ばで止まっているというものを、どういうふうにするかということを考えて、2013年、平成25年に、改めて西風新都の都市づくりの計画を見直したんですね。
そこでビジョンを作って、その中で、そこにもう一つ、今までは「住み、働き、学び、憩う」と4つの基本的な機能をその地域に与えるというまちづくりだったところに、「護る(防災)」そういった概念も入れて、まちづくりをやるということで見直して、そして、2030年には人口6万7,000(人)、それから21世紀中頃に8万(人)。以前は10万(人)ということを言っていたんですけどね。人口が減るというようなことがあるから少し落とした上で、しかし、やろうという計画を作り、議会でも認めていただいた上で、西風新都のまちづくりに取り組んでいるんですね。そういたしますと、この、今申し上げたように、4つのコンセプト、基本機能にもう一つ加えて5つの基本機能を備えたまちづくりというのは、これが進めば、本当にデルタ地にある市街地と高台にある副都心ということで、災害などのときにも代替機能を持たせることができる場所なんですね。そこを軌道で結ぶという、循環型のものにするという、その対象なんですね。そういう意味では極めて重要なツールであるし、今申し上げた最初のまちづくりをやっていく上で不可欠な要素だと思っているんです。そういう効果をねらいたいと思っているんですね。
ですから、それには大きなまちをつくるわけですから、金目がかかること自身あり得ることで、それをいかにうまく調達して、どれぐらいの年限でうまくお金を投入しながら事業展開するかということが、ここが私にとっては大きな課題だというふうに思うんです。
こうした視点に立って、広域公園前駅からJRの西広島駅までつなぐと、延伸すると。そうすると、あそこではJRの山陽本線とつながれるから一本化すると。この軌道型の、いわゆる大量かつ適性で定時制が保たれた軌道があそことの間でできますから、旧デルタ市街地と新しい副都心が結ばれるし、さらには、ここのJRを使って、新しい広域都市圏なんていうのもやろうと考えていますから、山陽本線と一体となって、大きい循環型の公共交通体系が既存のものを使って出来上がる。そういう意味では、近隣の各市町との結びつきも広がるということで、いろいろな意味で、ヒト・モノの流通も加速化するための基盤が整うというのが効果だし、ねらいだというふうに思っています。
そして、広域公園前の駅から西広島駅ができたとすると、多分そこから16分ぐらいで行くという見込みになっていますから、この16分の結ばれる間に、今ある西風新都内で開発されている五月が丘団地であるとか、それから、石内東の産業団地、そういうところで住んだり、あるいは、通勤したりしている方々がこのモノを利用するようになれば、どうでしょう、利便性向上いたしますよねというふうに思っているわけであります。
そして、便利だなということで企業進出も促すかも分からないし、団地なんかが新しくできる予想もある。そういうことを見込んで、言いましたように、21世紀中頃には8万人になっていくんであろうという、そういう大きな夢を立ててまちづくりを進めていると。重ねて言いますけど、その一環であるし、基本的な、不可欠な作業だというふうに思うんですね。だから、この延伸事業、あえて言えば、我が市におけるまちづくりにおいて、多大かつ多面的な効果・効能が期待できるものだと私は信じています。
そして、あと、費用、これについては、2015年、平成27年6月の事業化判断をした以降、物価高騰などがあったことを踏まえて算出して、約760億円になるということになりましたから、昨年の2月に、この数字を公表したものであります。
今申し上げたように、物価高騰等がそれからあったことを加味してあって、今でも物価高騰続いていますからね。そうすると、これから作業十何年かけてやらなきゃいかん中で、費用が固定しているということは多分ない。先ほど言ったように、上がる可能性があるわけでありますので、この事業について、今後とも着実かつ確実にやっていこうとするならば、そのためには、今後の社会経済情勢の変化などを踏まえた上で本事業が本格化するまでに、さらに必要額がどれぐらいになるかということを当然精査しなきゃいけないというふうに思っていますけれども、この話については、今、いろいろな準備をしています。
そして、いろいろな情報を出していただいていますけれども、これについて地域の方々、住民の方々、今申し上げた話、そうだなということで納得度を高めていただければいただくほど、この作業が早くなってまいりますからね。そういう意味で、正確な額も出せるように、それまでできないうちに次の作業をっていうことになると、手順がテレコっていいますか、十分な了解も得ないで大方の工事するということについてどうかという方は、問題意識が大きくなってまいりますので、その辺を考えながらしっかりやっていきたいというふうに思っています。
記者
最後の費用のところですね。事業が本格化する前に、精査して示したいということでよろしいですか。具体的なタイミングとかっていうのは、今の段階では…。
市長
それは分かりません。皆さんの納得度が高まって、いいなと言われたら、こうこうこうでこういうふうにかかりますよということを改めて御説明して、事業に入るというふうにしたいと思います。
※( )は注釈を加えたものです。
配付資料
-
協同労働インターンシップの実施について (PDF 435.8KB)

-
広島市協同労働促進事業のご案内「まちしごと わたしごと」 (PDF 7.1MB)

-
協同労働インターシップ周知用チラシ (PDF 804.2KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画総務局 広報課報道担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2116(報道担当) ファクス:082-504-2067
[email protected]
