2025年8月1日記者会見「令和7年平和宣言について」外2件
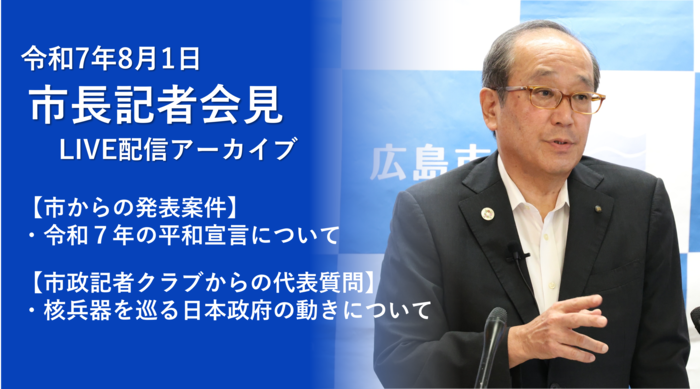
- 日時 令和7年(2025年)8月1日(金曜日)午後2時00分~午後2時47分
- 場所 市役所本庁舎11階第1会議室
市からの発表案件
令和7年平和宣言について
市長
それでは、令和7年の平和宣言について説明をさせていただきます。
ロシアによるウクライナ侵攻の長期化、あるいは中東情勢の悪化、こういったことによりまして、罪もない多くの人々の命が奪われ、核兵器を含む軍事力の強化による威嚇や暴力行為によって、国家間の問題解決を図ろうとする為政者の存在が、平和な世界の実現を困難なものにしております。
このような状況だからこそ、次代を担う若い世代が先導して、「平和文化」の振興に取り組むことで、核兵器廃絶への思いを市民社会の総意として、全ての為政者に対し、対話を通じた信頼関係に基づく安全保障体制を構築するように促すべく、被爆者の平和の願いであります「ヒロシマの心」を国内外の多くの人々に強く訴え掛ける平和宣言にしたいと考えました。懇談会のメンバーの皆様からいただいた貴重な御意見等を踏まえて、推敲を重ねて作成したところであります。また、平和宣言を引き続きより早く届くようにするとともに、若い世代を含めて、世界のより多くの人に共有してもらえるように発信といったことにも力を入れたいと考えています。
それでは、お手元の資料を御覧いただきたいと思います。
まず1の「宣言作成の基本姿勢」について説明いたします。平和宣言の作成に当たりましては、これまでと同様に「被爆者の思いを伝える」ことを主眼に置きながら、「平和宣言に関する懇談会」での意見を踏まえて起草をいたしました。
構成要素としては、「被爆の実相」、「時代背景を踏まえた事項」、「核兵器廃絶に向けた訴え」、「被爆者援護施策充実の訴え」、「原爆犠牲者への哀悼の意」、「平和への決意」の6つを盛り込んでおります。
そして、市民レベル、国家レベルのいずれにおいても、自分よりも他者の立場を重視する考えを優先することが大切であるという認識の下、為政者と若者をはじめとする市民社会が起こすべき行動を強調し、広く理解してもらうため、できるだけ分かりやすい展開になるように努めたところであります。
次に、2の「宣言の骨子」を説明いたします。まず、宣言の冒頭で被爆者の体験記を用いながら、生き延びた被爆者の後悔の念や、核兵器廃絶を決して諦めない被爆者の思いを紹介し、被爆者の体験に基づく平和への思いを伝えていくことが、ますます大切になっていることを訴えています。
次に、ロシアによるウクライナ侵攻や混迷を極める中東情勢を受けて、世界で軍備増強の動きが加速しており、自国を守るためには核兵器の保有もやむを得ないという考え方が為政者の中で強まりつつあること、また、そうした状況は、国際社会の平和構築のための枠組みを揺るがすものであることを指摘いたします。
そして、若い世代には、安全保障や核兵器のあり方は、非人道的な結末をもたらし得る課題であることを自覚した上で、核兵器廃絶への思いを市民社会の総意にするための活動を先導することを期待するとともに、「平和文化」の振興は難しいことではなく、自分たちが日常生活の中でできることを見つけて行動してほしいと訴えます。
その上で、広島市は、「平和文化」に触れることができる場を提供し続け、また、平和首長会議の会長都市として、世界の加盟都市と連帯し、「平和文化」を世界中に根付かせることにより、核抑止力に依存する為政者の政策転換を促していくことを宣言いたします。
さらに、世界の為政者に対しては、安全保障政策そのものが国家間の争いを生み出すものになっていないかと問い掛け、広島を訪れて被爆の実相を確かめ、対話を通じた信頼関係に基づく安全保障体制の構築に向けた議論を開始すべきではないかと呼び掛けます。
また、日本政府に対しては、国際社会の分断解消に向けて主導的な役割を果たすとともに、核兵器禁止条約の締約国となることは、被爆者の願いに応え、「ヒロシマの心」を体現することに他ならないと指摘して、第1回再検討会議にオブザーバー参加することを求めます。また、被爆者の苦悩に寄り添い、在外被爆者を含む被爆者支援策を充実することを強く求めます。宣言の骨子は、以上のとおりです。
最後に、3の「宣言の発信」についてであります。平和を願う「ヒロシマの心」を引き続きより早く届くようにするために、英語版の平和宣言の動画を、式典における平和宣言直後に広島市公式YouTubeチャンネルで配信いたします。
また、若い世代を含めて、世界のより多くの人に共有してもらえるよう、平和首長会議加盟都市やICANなどの関係者、式典に参列した大使などに上記動画について情報提供をして、周知を依頼するとともに、平和文化アンバサダーによる発信のほか、本市公式SNSによる事前告知やプッシュ配信なども実施いたします。さらに、動画のリンクを二次元バーコードにして掲載した平和宣言文を平和記念資料館に配架するとともに、各国の駐日大使館や国連代表部等に送付いたします。
説明は以上です。なお、参考資料として、宣言で参考にした被爆体験記を書かれた御本人及び御家族のコメントを付けておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。以上です。
記者
今の平和宣言の骨子をお聞きして、この近年というか、ここ1年でも相当、世界情勢が悪化していると思うんですけど、そういったところに対しての危機感であったりとか、去年との宣言と比較して、そういう危機感であったりとか、あとは若い人に対して身近な行動から、生活の中で行動を起こしてほしいといったところ辺りを今年の新しいところかなと思ったんですけれども、いろいろ6個ぐらい骨子(の構成要素)がある中で、特にこの中で市長が強く訴えたいところというのがありましたらお願いします。
市長
まさに、今言われたように、国際情勢、ある意味で混迷を極めているという中にありまして、国という単位で、いわば、各国が軍備の増強に走るといいますか、そちらの方にすごく状況が加速しておりまして、そうすると必然としてというか、その流れの中で、自分たちの国を守るためには、核兵器保有もやむを得ないという考え方を、為政者の中で強めているという状況があるように思えて仕方ありません。
こうした事態そのものを少し客観視いたしますと、いわば、第二次世界大戦を終えた直後からの国際社会の動き、すなわち、平和構築のための枠組みを作っていこうという大きな流れ、あるいは、ここまで作り上げてきた枠組みを揺るがす事態が発生しつつあるというふうに考えています。そういう意味では、今こそ改めて、第二次世界大戦直後は深く反省した方々がたくさんおられて、時代が経って、それを自ら反省した方々とは代替わりをしてきている、そういった中で、改めて過去の悲惨な歴史から得た教訓なるものを生かすということを、もう一回やっていただきたいというふうに思うんですね。とりわけ為政者の方ですね。そのために、為政者そのものはそういった発想でおられますから、その考え方そのものが、本当にいいんだろうかということを考えていただける動機付けをやっていくためには、いわば、市民社会、その中でも次代を担う若い世代が、しっかりとした考え方、つまり、核兵器廃絶への思いといったものを自分たち、みんなが持っていますよということを示せるようなこと、それが自分たちの日常生活の中からにじみ出るような行動をするとかといったことをできるようにしていく必要があると思うんですね。
そういう意味で、平和文化の振興というのを国境を越えて広める、そういったことをしっかりやりましょうということを、宣言を通じて訴えたいと思いました。ただ、分かりやすくするためにということも注意しながらやりましたから、今言ったような説明の仕方までは十分いっていないかも分かりませんけれども、おおよそそのようなところであります。
折しも、今言ったようなことを、ある意味で、もう少し分かりやすく説明するというような場面に出くわしまして、それは先月開催されましたインターハイ(全国高等学校総合体育大会)の総合開会式、見させていただいたんですけれども、これはまさに高校生ですから、次の時代を担う若い世代が集まっての開会式なんですけれども、そこで高校生が演奏とかダンスをやって、選手に応援を届けるという公開の演技をするという場面があったんですけれども、そこで公開演技の流れは、相手に勝つために必死になっている選手、それぞれ各県から代表が来て、日本でトップになりたいというか、優勝したいということで必死になって競っている選手が、実は自分たちが争い合っている相手は、いわゆる、敵ではなくて仲間であるということに気づくまでの心の葛藤を表現するものだったんですけれども、非常に分かりやすくやってもらいました。
そこでのもう一つの主張は、大切なことは過去の自分というものを乗り越えることで、競い合ったのちに、相手方と仲良くできる、いわゆる絆をつくることができると、こんな話でありました。相手の存在を否定するのではなくて、技を競う中で自分自身に磨きをかける、自分の技量を高めるということを通じて最後は仲良くすると、これがスポーツなんだと。こんなものでありまして、スポーツの意義を伝える中で、まさに平和文化を象徴するような取組というか、説明だったなと思っていまして、多くの高校生、見たと思うんですけど、こういったことを通じて、最初に言いましたように、次の世代が何を大事にするかということを、しっかり考えてもらいたいと思うんですね。
加えて、今言ったことを広めながら、世界の為政者に対しましては、ぜひ広島を訪れて被爆の実相を確かめるということ、そして、その際、しっかり考えていただきたいのは、安全保障政策ということを考える際に、自国のことのみに専念するのではなくて、対話ということを通じた信頼関係に基づく安全保障体制の構築、そのための議論を開始するというふうなことをしていただきたいと思いまして、このことをしっかり呼び掛けたいと思いますし、本市は、その際、為政者の政策転換というものを促すための、いわば、環境づくりですね。平和首長会議の加盟都市と一緒になって連帯しながら、平和文化を世界中に根付かせていく中で、そういう環境をつくるという決意を、しっかりと示していきたいというふうに思っています。
記者
今、自国中心ではなくて、世界との対話が大切というふうに、それを世界に呼び掛けたいと思っているというふうなお話をされていたかと思うんですけれども、世界情勢が悪化している中で、この我が国日本でも核が安全保障を守るんだという考え方をする為政者が、だんだん増えているかと思うんですけど、自国にはどこの部分を一番訴え掛けたいとか、そういった点っていうのはございますでしょうか。
市長
今言われたのは、直近の選挙などで特定の党が発言した内容等を踏まえてのことだと思うんですけれども、私自身としては、今言った話の基本は、国会議員を選ぶ側にいる市民社会、この市民社会において平和文化を守るといいますか、平和文化を大事にするということがしっかり根付いているとすれば、そういう主張をしたとしても支持が得られないわけですから、どうでしょう。その発言があったとしても問題ないというふうに、ある意味で受け止めていいんでしょうけれども、問題なのは市民社会の中でも、「あっそうかな」と、「そうじゃないんだろうか」と思うような状況があるからこそ、皆さんが心配されているというふうにも受け止められるんですね。
だから、核兵器はなくすべきである。決して、武力によるいかなる侵攻もやめるべきだと、そういった理想を市民社会の総意にするための取組、これを今以上にやらなきゃならんと。これがある意味で十分に行き渡っていないというふうに考えていいのかも分からないんじゃないかと思うんですね。具体的発言そのものは、マスコミ等の記事でしか知っていないために十分承知はしてないんですけれども、間違いなく平和文化というものが、私に言わせれば、まだまだ根付いていないという状況の中でそんな意見が出てくると、皆さんがそっちに行き、その為政者がその支持を得たと勘違いしているというか、そう思ってどんどんその政策を進める政治環境が出来上がっていくと。そういう流れが恐ろしいというふうに思うんですね。
そういう意味では、そういうことを考えながら思ったときに、以前、平和宣言でガンジーの言葉を引いたりしたんですけれども、改めてガンジーの言葉の中で、こういったことに対しては、「人間は非暴力によってしか、暴力から逃れられない」という言葉を言っていたのを覚えておりましてね。こういったことを思い出さずにはおられないなと、そんな心境であります。いずれにしても、今みたいな「人間は非暴力によってしか、暴力から逃れられない」というような気持ち、「そうだな」と、「間違いない」というふうに思っていただけるようにするためには、いろいろな機会を捉えて、多くの方に例えば被爆地に来ていただいて、被爆の実相なるものをしっかり自分自身で確認していただいて、その上で言ってきております「ヒロシマの心」というものを自分のものにするといいますか、そういったことをしていただきたい。そのための行動を今まで以上にしっかり広島市としては、やっていかなきゃいけないんじゃないかなと思っています。
記者
被爆80年となる今年、改めて被爆体験の継承というのが課題になっていると思いますが、今年、まず平和宣言に被爆体験を盛り込んでおられるその意図と、今年引用された被爆体験がどういった部分を重視して選ばれたものなのかを、いま一度教えていただいていいでしょうか。
市長
あくまで被爆体験を記述するというか、平和宣言に取り上げるのは、被爆の実相というものを自分事として考えていただけるような動機付けをするためにという目的なんですね。そこで、いろいろなパターンがありまして、今回は、まずは被爆当時に自分自身が肉体的な苦しみを味わったんだけれども、実は、それ以上に傷ついた方々を助けられなかったという、そういった慚愧に堪えないといいますかね、そういった気持ちを持っていて、ずっと後悔し続けている方とかもおられますね。
それから、自分自身被爆者ということに基づく社会的な差別を味わう。そして、ある意味で心の中でいろいろな傷つくという状況をずっと重ねてきているということも、もし自分が味わうとどう思うでしょうかということを考えていただきたいから、言葉そのものは、今回自分の言葉ということでありますように、そういう話を紹介するというパターンで書かせてもらいました。
今までのパターンの中では、さっき申し上げたようにガンジーの言葉を引くとか、そういった事象を踏まえて、どう考えたかという方々のお話も紹介する意味で、著名人の言葉も引いたりしたんですけれども、今回はそういったことも踏まえながら、もう一回改めて直接の被爆者となった方々の心の面と、それからそれを乗り越えて、その後頑張るぞという「ネバーギブアップ」というようなことを言われた方という時間的な経過も踏まえて、心の変遷がありながらも頑張ってきた方々というのがおられるんですよと。だから、自分たちがどのパターンに当たるかもよく考えていただきながら「ヒロシマの心」というものを自分のものにしてもらえるようにという気持ちを込めて、被爆体験者の体験記の引用をしたというふうにしております。
記者
関連して、さっき市長がおっしゃった「ネバーギブアップ」の言葉なんですけれども、坪井(直)さんの言葉としても有名ですけれども、それを今回盛り込んだ意図というのはどういったところになるんでしょうか。
市長
これは坪井さんの中で、今申し上げた社会事象ですと、国同士が争っていて武力を用いて相手を威嚇しないと、現状自分たちの国家はどうなるんだろうということを言われる方が結構いて、そういうのを若い人に聞かせると、「ああ、そうか」と。社会の中で一定の地位がある方々、政治というようなことに携わっている方々がそう言うんだから、それは本当じゃないかと思わざるを得ないような状況設定もありますけれども。だけど、そのこと自身が本当に、いいんでしょうかということを考えていただくときに、まず対話を重ねるという中で、いろいろな意見があっても、相手の意見をもちろん聞くんですよ。聞いた上で、でもあるべき理想の姿はこうなんだと。そして相手を押し込めるんじゃなくて、自分たちの主張をこっちの方が正しいんじゃないですかということを諦めることなく「ネバーギブアップ」ですね。諦めることなくきちんと伝えていく。そして、そのあるべき姿をなるべく多くの方に伝えていくという努力をするという、そういう示唆に富んだ言葉だというふうに思いましたのでね、若い方々、こういった対処方法をしっかり身につけていただきたいなという思いで引用したものであります。
記者
先ほどインターハイのくだりがあったので、繰り返しになってしまうかもしれないのですが、今年の宣言で特に若い世代に訴えたいことというのをお願いできますでしょうか。
市長
言葉を変えれば若い世代というのは、戦争ということを自ら直接経験していない方々を中心に考えております。そして、広島の若い方々はある意味で平和学習ということについて、原爆の実相などに触れる機会も、国内の他の地域の方々よりかは多いから、一定程度御理解がいっているというふうに思うんですけれども。ただ、いかんせんそういったことについての関心が薄れているんじゃないかというような御指摘もあるとおりであります。
そういうことについての問題意識を含めて、きちんとした被爆の実相を伝える方々が高齢化して、十分そういうことを伝える機会がなくなっている中で、もちろん、伝える側のしっかりした伝達方法について、支援体制をしっかり組むということは重要なんですけれども、それを受け止める側の心構えをしっかりしていただかないと、「ヒロシマの心」、被爆の実相を踏まえた伝えるべき価値あるものの伝承作業というものが、十分にいかないということになりますから。若い方が改めてそういう取組をすることは、スペシャルなことではなくて、日常生活の中でできる様々な行動の中で、これを貫いている平和ということを、「ヒロシマの心」を貫いている考え方をいろいろな形で自ら確認して、それを生かすための行動をやり続ける中で、直接戦争体験、被爆体験をしていなくても、そこから生まれてきた大事な価値観なり考え方を自分たちのものにしていってほしいということを強く言いたいんですね。字数があればいくらでも今みたいなことを繰り返しお話ししたいんですけれども、それを感じていただくための構成をどうしようかということで、今回みたいな展開になっているということです。
改めて言いますけれども、仮に今、核兵器が要るというようなことを言って為政者の立場で主張される方がいたとしても、どんどん1年、2年、3年で、時間が経っていきますよね。そうすると、若い方々はどんどん世の中を支えるメンバーになっていくわけですから、そういったことを社会に出るまで、ある意味で白紙の状態という、白紙ではないかもしれませんけれども、社会に出ている方よりかは比べれば白紙の状態ですから、そういった方々が「ヒロシマの心」をしっかりと受け止め、数的にも増えていけば、市民社会の中でこちらの考え方がある意味主流になるというか、言い方がおかしいですけど、多くの方が支持する意見になれば、確実に世論というか、物事の判断方法は変わっていく。それを政治家として受け止めるときに、それに反する受け止め方ができないようになるんじゃないかと、それぐらいのことをイメージしながら、若い世代がとにかく早くたくさんそういったことを受け止めるようにしてもらいたいというふうに思っています。
この平和宣言と同時にもうひとつ、平和学習ということを市の政策としてしっかりやっていき、多くの方を広島に招いて勉強してもらうということにも同時に着手していますからね。いわば、そういったことをやりますよということを、平和宣言でも感じていただくというふうになればなというふうに思っています。
記者
先ほどの質問に関連して、ちょっと平和宣言から離れるかもしれないんですが、若い世代への発信、特に先ほど市長のお言葉の中にも平和学習、多くの方を招いて、要は来ていただいて学んでいただくということを念頭におっしゃったと思うんですけれども、先般の参議院選挙の出口調査で、NNN系列さんとNHKさんと読売新聞さんが合同でされた出口調査の結果を見ますと、もう若い世代で圧倒的に先ほどからちょっと話題になっております、核抑止ということを比較的肯定されている考えの政党の候補者を支持される方が圧倒的に多いと。具体的に言うと49歳以下は選挙区での出口調査ベースですけれども、一番獲得票率が高かったのがその政党の候補者だったという現実があります。特に若い世代は46.6パーセントなので本当に半分近くの方がそういうことを主張されている候補に投じるという投票行動をされたように思います。先ほど、平和学習のことをおっしゃっていたんですけれども、これは広島選挙区での出口調査の結果なんですけれども、こと被爆地広島における地元の子どもたちの学びの中に、今後特に取り組んでいきたいこと、今足りないものがあるとしたらどんなことがあるというふうに市長は認識されていますでしょうか。
市長
まず後半の方、足りないものがあるうんぬんについては、今一生懸命、今までの平和学習のあり方というものをしっかりとチェックしながら、より多くの方に平和について考えていただく動機付けなり方向性をしっかりするためにということで、平和記念資料館なども来館者が増えているという事実はありますから、その中で子たち向けの資料館を見るためのコースを別途設定して、大人が見る際には怖いとか嫌だなというようなことがないとしても、お子たち向け、初めてそういうのを見るときに衝撃が大きくて、それ以上お勉強するのがどうも怖いとかいう方がいるというようなことも聞いたりする。それをまずしないための工夫をするということで、今、コース設定などもやっていますから、それはひとつ、これから平和学習をやっていく上での工夫の一例だというふうに思ってください。そして、多くの子たちがきちんとそういった気持ち、考え方を受け入れられる環境づくりを設定するということをやりながら、かつ、来ていただく範囲をこれからもっと積極的に増やそうということで、国の支援などを受けて平和学習のための修学旅行とかあれば、来るための費用負担を軽減してでも国の支援を受けた国家としてもしっかり認知した上で広島に行って学習してもらうようにする。これがうまくいけば、国を挙げて広島の地における平和学習をやっているよ、ということを多くの方に認知してもらおうという取組をしています。これは、こういった考え方をもっと広く知っていただくということをやりたいと思いますね。
そして、そういった中で、それがまだ十分というか知られていない、広島固有というぐらいの話だと。国内全部見てもこんなふうに平和学習をしている都市はないと。その中で、今の世界情勢に関わる、いわばマスコミ情報といいますか、SNS等を通じての世の中の情報が比較的簡単に若い世代の方々に入ると。そうすると、その起こっている事象についての情報は入るんですけれども、それを解決するための方策について、より根源的な問題提起をして、こういった形で問題解決を図ろうというような議論提起ではなくて、今起こっている事象を安易に解決するために、逆に自分たちが困っている立場だったらこういったことをなくせばいいじゃないかとかね。つまり、その対立する構造に入っているときの犠牲者側と相手側について両方の立場をしっかりと調べて、それらを比較してどうするかというような議論展開をするんじゃなくて、この事象の中で自分は犠牲者になっていると。それを跳ね返すためにはこうだと。一方的な主張について書くと、両方比較するような情報提供がないために、「ああ、こうすればいいんだ」ということで、いわば何とか主義といいますか、自分本位というか、そういった展開をする情報に、ある意味で多くの方が乗りやすいんですよね。複雑に考えなくていいから。だから、今言われたようにアンケートを取れば解決できるんだったらそれでもいいじゃないかというふうになっているんじゃないかと。ですから、それについては先ほど申し上げたように、いわば自分本位、自分だけのことで考えるんじゃなくて必ず相手のことも考えて、実際に起こっている事象っていうのは絶対悪と絶対正義がぶつかって生じているんじゃなくて、いろいろな利害調整、歴史、宗教、様々な背景があって混乱が生じているわけですから、それらを総合的にきちっとファクトファインディングした上でどういうふうな対処をしていくべきかという、そういう議論をすると。そのためには、立場の違う、価値観の違う人たちとしっかり対話しないといけないんですけれども、対話抜きで一方的な判断・情報をもとに自らを正義とし、対抗する相手を悪と見立てて、処理方針をあるいは処方箋を出すということ、それ自身は鮮やかな答えになるんでしょうからね。いいかなというふうに安易に賛成する方が出ているんだと。そういうこと自体を改めるということをもっとやっていただきたいんです。自分本位ではなくて、よくよく相手のことも考えるということが必要じゃないですかということを平和宣言の中でくどく言わせていただいているというふうに思っています。
記者
市長はいつも「ヒロシマの心」ということをおっしゃっていて、これは長くずっと核兵器の廃絶と世界恒久平和を願う心だというふうに理解しているんですけれども、この「ヒロシマの心」の中には状況によっては、あるいはやり方によっては、核兵器の力に何らか頼るというような考えというものは基本的に入ってくる余地はないものだという認識でおられるという理解でよろしいでしょうか。
市長
はい。先ほどガンジーの言葉を引用したとおりですね。暴力というものを使って非暴力の状況をつくるということはできない。これは真理だと思っています。
市政記者クラブからの代表質問
核兵器を巡る日本政府の動きについて
記者
核兵器を巡る日本政府の動きについてお伺いします。
日米両政府の外務・防衛当局者が参加する拡大抑止協議において、米軍による核使用のシナリオを議論していたこと、及び自衛隊と米軍が昨年実施した台湾有事の机上訓練では、自衛隊が核の脅しで中国に対抗するよう米側に求めていたことが明らかになりました。核兵器のない世界を追求する日本政府のこのような姿勢について、市長の受け止めをお聞かせてください。
市長
報道されている内容、本市というか私、直接、事実関係を把握しているわけではありませんけれども、世界の安全保障環境が今まで一転、一層厳しさを増すといった環境の中で、戦争を仕掛ける動機付けをさせないためにという、その大義名分を持って、核兵器の使用を前提とした威嚇を行うというふうな行為を、そういうふうに受け止められる行為は、いわゆる核のタブーを脅かして、そして核兵器の使用可能性を高めるだけではないかなと、私は受け止めています。
そうした中で、先ほども言ったんですけれども、改めて、ガンジーのことについて言及しますと、ガンジーは終戦の翌年、ですから、1946年かな。メッセージを出していまして、そのことを今、もう一回ここで紹介したいと思いますけれども、どういうふうに言ったかというと、「原子爆弾という究極の悲劇から正しく導き出される教訓は、ちょうど暴力が対抗する暴力によって無くされることがないのと同じように、原子爆弾が対抗する原子爆弾によって無くされることはないだろうということであります」と。そしてそこで、「人間は非暴力によってしか、暴力から逃れられないのです。」こういう言い方をしていて、私自身は、これは心理を突いているなというふうに信じています。ただ、この暴力行為に対しては、例えば、ハンムラビ法典、イスラム教につながることですね。「目には目を、歯には歯を」という考え方があって、これを、やっぱり人類としては受け継いでいるわけですから、こういうのもありだということになりますよね。刑罰を作るときなんか、こういった考え方でやりますでしょう?もう一方、そのキリスト教、マタイの福音書で、山上の垂訓、ここでは、「あなたの右の頬を打つ者には、左の頬をも向けなさい」という考え方。これも、価値観として、皆さんに共有されているのもあるじゃないですか。そうすると、宗教という形を通じてですけれども、いろいろな価値観、現にありまして、どっちが正義で、どっちが悪ということなく、両者共存しているわけですね。
だから、こういった考え方に基づく処理を我々、それぞれの行動を取る場面でどう採用するか、よく考えなければいけないと。それ抜きに簡単にこっちの主義でいけばいいじゃないかと、こっちの主義でいけばいいじゃないかと言えないんですね。まずそれが基本にありますということです。ですから、いろいろな考え方をちゃんと自分なりに確認した上で、物事を判断していただくということがとても重要と。で、その上で、原子爆弾に関しては、先ほど言ったように、ガンジーの言った考え方が自分としては、現時点では、あるべき姿ではないかなと思っているということであります。
その他の質問
参政党議員の「核武装は安上がり」発言について
記者
先ほどから、関連して質問が出ていますけれども、前回も少し話がありましたが、東京都選挙区で当選した参政党の候補が、選挙期間中、核武装について安上がりだと発言したり、今朝の毎日新聞の報道によりますと、参議院選で当選した125人のうち、アンケートで、日本が核武装をするべきだと答えた人が8人いて、参政党の候補議員は(そのうち)6人だったと。広島の選挙区の候補者に関しても当選はしませんでしたが、核兵器の保有については、抑止力として持った方がいいんじゃないか、持つべきではないかという発言、我々も取材をしていまして、こういう核兵器を日本が持つということを現実的な選択肢としてあり得るんじゃないかという考え方を結構持たれているようですけど、この考えについてはどういうふうに感じますか。
市長
繰り返しになりますけども、一つ、直接触れているわけではありませんけれども、核武装は、まず、事実関係、ファクトファインディングですね。安上がりであるというのは、私自身の勉強の成果として決して安上がりではないというふうに思っています。なぜかというと、実際に1945年8月9日以降、戦争において核兵器、武力行使として使っていないわけです。そうすると、核兵器を持っている国は使わない武器を少なくとも今時点、80年間持っているでしょ。どんなものだって作ってしまうと、機能劣化といいますか、起こりますよね。そうすると、どこかで手を加えて、修繕しなきゃいかん。そうすると、その費用っていうのは、結局研究者もいる、維持するためのいろいろな機材もいる。そうすると、使いもしない、使うことすらできないものを維持するためのお金っていうのはバカ高いものになるんですね。
だから、核兵器を持っている国で、もしお互いに抑止力うんぬんということを言わないようにして、両方が、そういう経費負担を図る、数を減らせば、それだけ負担が軽くなりますからね。そのお金をそれぞれの国家の福祉予算とかに回せるというぐらいの行動ですから、核武装にかかるお金は決して安くありません。高いはずです。それは事実だと思います。
それはそれとして、安いからうんぬんという話は、まず全然、的外れだと思った上で、かつ、核兵器を持つということで、つまり、暴力を後ろに、背後に控えることで、相手を威嚇して、物事をコントロールしていこうというのは、一過性の脅迫行為として、何らかの効果はあるかもしれませんけれども、人間として、この地球上で、いろいろな営みを継続していく上で、一過性の脅しは、長期にわたる人間関係をうまく構成するためには機能しない。そうすると、いかに無駄なことかと。混乱を生じる可能性すらあるというふうに思うわけです。
そういう意味では、人間は非暴力というか、知恵をちゃんと使って、暴力から逃れるようにするということが正しいんじゃないかというふうに言い続けたいし、そう言っている方、今言ったような核武装は安上がりだから、やってもいいという考え方を持っている方には、そうではないんじゃないですかということをしっかり伝えられるようにしたいと。そういう意味では、この「ヒロシマの心」を共有していただく方をうんと増やすという中で、そういった方々にも、しっかり考えを点検してもらいたいというふうに思いますね。
※( )は注釈を加えたものです。
配付資料
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画総務局 広報課報道担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2116(報道担当) ファクス:082-504-2067
[email protected]
