感染症情報/梅毒
梅毒とは
梅毒は、性的な接触(他人の粘膜や皮膚と直接接触すること)などによってうつる感染症です。原因は梅毒トレポネーマという病原菌で、感染すると全身に様々な症状が出ます。
早期の薬物治療で完治が可能です。検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を起こすことがあります。時に無症状になりながら進行するため、治ったことを確認しないで途中で治療をやめてしまわないようにすることが重要です。感染しても終生免疫は得られず、再感染する可能性があります。
感染経路
主な感染経路は、感染部位と粘膜や皮膚の直接の接触です。具体的には、性器と性器、性器と肛門(アナルセックス)、性器と口の接触(オーラルセックス)等が原因となります。また、妊娠している人が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児に感染し、死産、早産、新生児死亡、奇形が起こることがあります(先天梅毒)。
症状
感染後3~6週間程度の潜伏期を経て、経時的にさまざまな臨床症状が出現します。その間症状が軽快する時期があり、治療開始が遅れることにつながります。
|
病型 |
臨床症状 |
|---|---|
| 早期顕症梅毒(1期) | (感染後約3週間) 初期には、感染がおきた部位(主に陰部、口唇部、口腔内、肛門等)にしこりができることがあります。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることもあります。痛みがないことも多く、治療をしなくても症状は自然に軽快します。しかし、体内から病原体がいなくなったわけではなく、他の人にうつす可能性もあります。感染した可能性がある場合には、この時期に梅毒の検査が勧められます。 |
| 早期顕症梅毒(2期) | (感染後数か月) 治療をせずに3か月以上経過すると、病原体が血液によって全身に運ばれ、手のひら・足の裏・体全体にうっすらと赤い発疹(バラ疹)が出ることがあります。発疹は治療をしなくても数週間以内に消える場合がありますが、抗菌薬で治療しない限り、病原菌である梅毒トレポネーマは体内に残っており、梅毒が治ったわけではありません。 |
| 晩期顕症梅毒 | (感染後数年) 皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生することがあります。また、心臓・血管・脳などの複数の臓器に病変が生じ、場合によっては死亡することもあります。 |
| 先天梅毒 | 妊娠している人が感染すると、胎盤を通して胎児に感染し、死産・早産・新生児死亡・奇形が起こることがあります。 |
治療方法
抗菌薬による治療を行います。
予防方法
感染部位と粘膜や皮膚が直接接触しないように、コンドームを使用することが勧められますが、コンドームに覆われない部分の皮膚などでも感染が起こる可能性があります。皮膚や粘膜に異常があった場合には、早めに医療機関を受診しましょう。また、梅毒に感染していたとわかった場合、周囲で感染の可能性がある方(パートナー等)も検査を行い、必要に応じて治療を行うことが重要です。
保健センターの無料・匿名の梅毒検査
広島市の保健センターでは、梅毒検査を無料・匿名で行っています。検査は予約制です。予め、検査を希望される保健センターに電話またはWebで予約してください。
-
梅毒検査
(健康推進課)
参考
広島市における発生状況
2026年第6週(2月2日~2月8日)に、1件の報告がありました。
2026年の累計報告数は、8件(男性5件、女性3件)です。
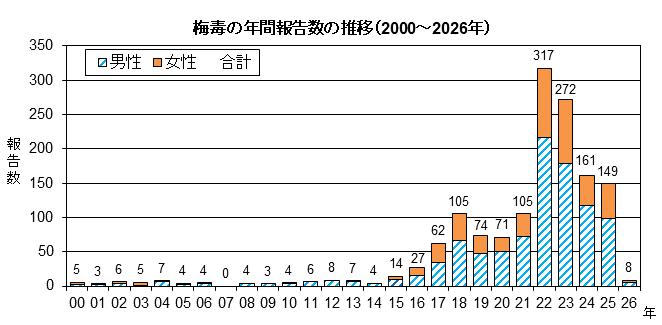
性別報告数
過去5年間に報告された926件のうち68.6%が男性でした。
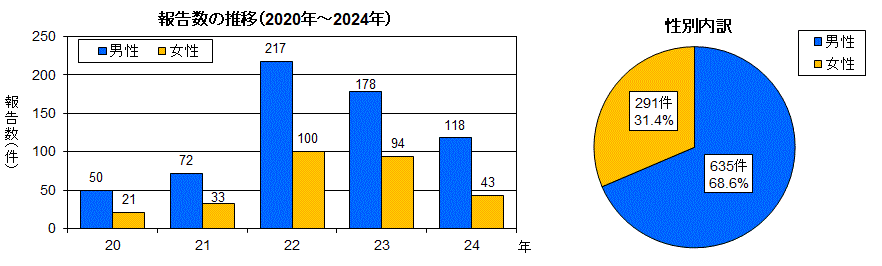
年齢階層別報告数
男性は20~50代、女性は20代が多くなっています。
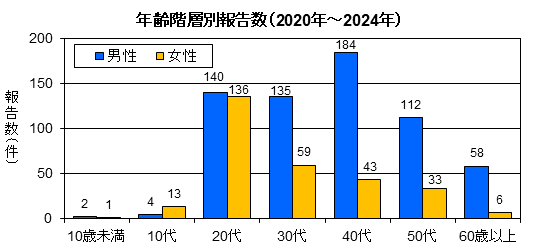
感染経路別報告数割合
過去5年間に報告された926件のうち、性的接触が92.5%を占めていました【図1】。
そのうち、男性、女性とも8割以上が異性間の性的接触でした【図2】。
また、2024年に報告された性的接触147件のうち、男性、女性ともに57.1%に6か月以内の性風俗産業の利用歴または従事歴がありました【図3】。
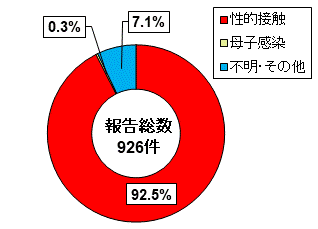
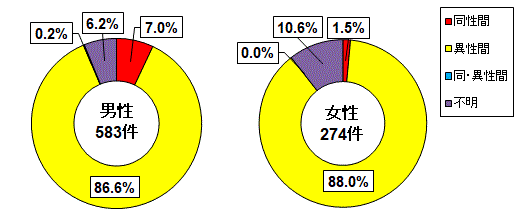
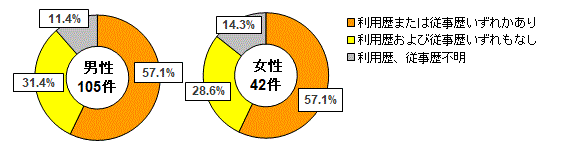
病型別報告数割合
男性では、早期顕症梅毒1期が最も多く、次いで早期顕症梅毒2期が多くなっています。女性では、早期顕症梅毒2期が最も多く、次いで無症候が多くなっています。
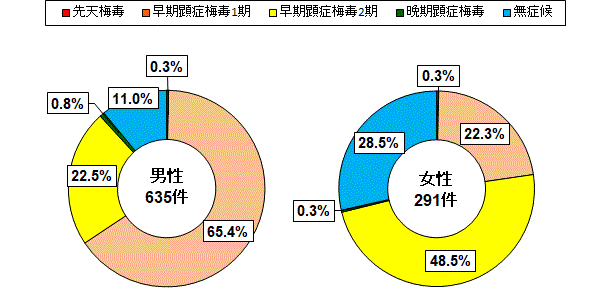
※ 小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局衛生研究所 生活科学部
〒733-8650 広島市西区商工センター四丁目1番2号
電話:082-277-6575(生活科学部)
ファクス:082-277-0410
[email protected]
