社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のご案内
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
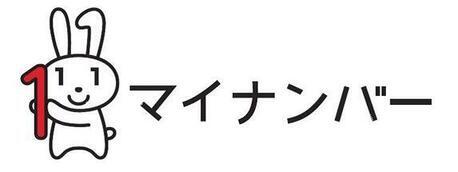
※ マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!!
内閣府のコールセンターや消費生活センターなどに、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
国の関係省庁や地方自治体が、電話等でマイナンバーや口座番号、資産の情報などを聞いたり、金銭を要求することはありません。
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
(主な相談窓口)
- 内閣府 マイナンバー総合フリーダイヤル 電話 0120-95-0178
- 消費者ホットライン 電話 188
- 最寄の警察署か110番
- 個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口 電話 03-6457-9585
詳細は総務省ホームページをご確認ください。
マイナンバー制度
マイナンバー制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。
国の機関や他市町村等との情報連携が可能になることで、窓口での各種申請手続の時に必要となる添付書類が削減されるなど、市民の皆さんの利便性の向上や行政事務の効率化が図られます。
マイナンバー制度の最新の情報や詳しい内容は、デジタル庁「マイナンバー(個人番号制度)」のホームページをご覧ください
他市町村や国の機関との情報連携の本格運用が平成29年11月13日から開始されました。詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。
なお、情報連携により添付書類が不要となる手続は、法律(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)等で定められた手続に限られ、それ以外の手続では、引き続き添付書類が必要となります。
マイナンバー(個人番号)
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の分野で、法律や条例で定められた行政手続でマイナンバーが必要です。
雇用保険や健康保険等の手続、確定申告等の税の手続などで、申請書等へマイナンバーを記載することになります。
詳細については、各制度の担当部署へ直接お問い合わせください。
マイナンバーの提供を求められる主なケース
|
提供を求める者 |
提供する必要のある者 |
|---|---|
| 勤務先 |
|
| 契約先 (契約先企業、講演等の主催企業 など) |
報酬、料金、契約金を受け取る方 など (例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料 など) |
| 不動産業者等 (不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人) |
不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方 |
| 金融機関等 (銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社 など) |
そのため、金融機関から、預貯金口座をお持ちの方に対して、マイナンバーの届出の協力依頼があります。 なお、預貯金口座への付番に係るマイナンバーの届出は任意とされています。 |
| 税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合 | 社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方 (例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等) |
区役所や市税事務所などでの申請等にマイナンバーが必要となる主な手続は、次のとおりです。
医療保険
|
区分 |
主な手続 |
担当課 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 |
|
各区保険年金課 |
| 後期高齢者医療 |
|
各区福祉課 |
介護・福祉・年金
|
区分 |
主な手続 |
担当課 |
|---|---|---|
| 介護保険 | 要介護認定・要支援認定の申請、被保険者証・負担割合証等の再交付の申請、居宅サービス計画等作成依頼(変更)の届出 | 各区福祉課 |
| 介護保険 | 負担限度額認定の申請、高額介護サービス費等の支給申請、福祉用具購入費の支給申請、住宅改修費の支給申請 | 各区福祉課 |
|
福祉 |
|
各区福祉課 |
| 福祉 | 障害児入所支援給付費の支給申請 | 児童相談所支援課 |
| 福祉 | 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金などの請求 | 各区保険年金課 |
| 福祉 |
|
各区生活課 |
| 年金 | 被保険者資格の取得、保険料の免除申請、年金給付の請求など (いずれも基礎年金番号による手続も可能) |
各区保険年金課 |
子育て
|
区分 |
主な手続 |
担当課 |
|---|---|---|
| 給付・届出 |
|
各区福祉課 |
| 給付・届出 | 保育園・認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・幼稚園への入園申込み、変更届など | 各区福祉課 |
| 給付・届出 | 小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請 | 各区福祉課 |
| 給付・届出 | 母子健康手帳の交付申請(妊娠届出) | 各区地域支え合い課 |
暮らし
|
区分 |
主な手続 |
担当課 |
|---|---|---|
| 市営住宅 | 市営住宅への入居申請など | 各区建築課 |
税金
|
区分 |
主な手続 |
担当課 |
|---|---|---|
| 市民税 |
|
各市税事務所・各税務室・財政局税務部市民税課 |
| 軽自動車税 | 軽自動車税減免申請書の提出 | 各市税事務所・各税務室 |
| 固定資産税 |
|
各市税事務所・各税務室 |
※上記の手続以外にも、マイナンバーが必要となる場合があります。詳しくは、それぞれの担当課へお問い合わせください。
通知カード
マイナンバーを証明するための通知カードは、令和2年5月25日で廃止されました。
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。マイナンバーカード(顔写真付き)が廃止となるわけではありませんのでご注意ください。
また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請を行うことができます。
通知カード廃止後のマイナンバー(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)は、マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」で証明することができます。

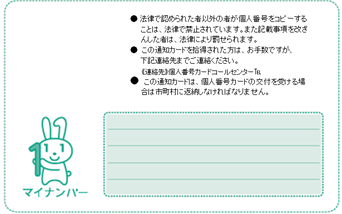
マイナンバーカード
平成28年1月以降、希望者からの申請によりマイナンバーカードを交付します。(通知カードは回収します。)
マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、ご本人の顔写真が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、国税の電子申告や証明書のコンビニ交付サービスなどに利用できます。
初回交付は無料、再交付手数料は1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)で、有効期間は、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。
なお、マイナンバーカードを取得される方は、交付時に住民基本台帳カードを回収します。
申請は、通知カードとともに送付する「個人番号カード交付申請書」に記名押印し、顔写真を貼付の上、返信用封筒で送付してください。また、スマートフォン等によるオンライン申請もできます。
※返信用封筒をなくされた場合には、「マイナンバーカード総合サイト」に利用可能な封筒様式がありますので、ご利用ください。
顔写真は、サイズ縦4.5cm×横3.5cm、正面、無帽、無背景のもので最近6ヶ月以内に撮影したものを使用してください。
なお、顔が横向きのもの、無背景でないもの、帽子・サングラスをかけたもの、正常時の顔貌と著しく異なるものなどは無効となります。また、写真修正ソフト等を利用した写真は使用しないでください。


- ※マイナンバーカードに関する情報については、以下のリンクをご覧ください。
- ※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、マイナンバー総合フリーダイヤル(電話0120-95-0178)及び個人番号カードコールセンター(電話0570-783-578(有料))において、24時間365日受付しています。
マイナポータル
マイナポータルとは、マイナンバーカードとカードリーダーを使って、自宅のパソコン等からアクセスすることによって、マイナンバー制度で行う行政機関間での情報連携の記録や行政機関等が保有する自己情報の確認などができる国が運営するオンラインサービスです。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
個人情報保護対策
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む個人情報を不当に提供することは、処罰の対象となります。
平成27年10月5日(月曜日)に、個人情報保護委員会に、特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うための、「マイナンバー苦情あっせん相談窓口」が設置されました。
- 電話番号 03-6457-9585
- 受付時間 9時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く)
特定個人情報保護評価
地方公共団体等がマイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとするときは、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられており、利用方法や漏えい等のリスク対策について自己評価を行い、公表します。
また、評価の対象となる事務ごとに、対象人数等に基づく「しきい値判断」の結果に応じて、「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」を実施します。
- ※特定個人情報保護評価の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。
- ※「しきい値判断」フロー図については、下記ダウンロードをご覧ください。
特定個人情報保護評価書案に対する意見募集
全項目評価の実施に当たっては、事前に公表のうえ、市民の皆様からの意見をお伺いします。
※現在、意見募集している特定個人情報保護評価書案については、以下のリンクをご覧ください。
特定個人情報保護評価書の公表
本市が実施した特定個人情報保護評価の評価書を公表します。
※公表している評価書については、以下のリンクをご覧ください。
事業者の皆さまへ(事業者の方もマイナンバーを取り扱います)
平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。
- 源泉徴収票の作成手続
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
- 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成 など
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があり、漏えい事案等が発生した場合には、個人情報保護委員会への報告などの対応が必要となります。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
関連情報
法人番号
平成27年10月以降、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号は、国税庁「法人番号公表サイト」で公表され、どなたでも自由に利用できます。
※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。(法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。)
法人番号の詳細は、以下のリンクをご覧ください。
なお、広島市の法人番号は、「9000020341002」です。
国の関連ホームページ
-
マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)(外部リンク)

-
社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁)(外部リンク)

-
マイナンバー制度(厚生労働省)(外部リンク)

-
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部リンク)

-
マイナンバー(個人情報保護委員会(PPC))(外部リンク)

マイナンバー総合フリーダイヤル
※マイナンバーカードに関するお問い合わせ、マイナンバーカードの交付申請に関するお問い合わせについては、「マイナンバー総合フリーダイヤル」をご利用ください。
日本語窓口
0120-95-0178
平日9時30分~20時00分 土曜・日曜・祝日9時30分~17時30分(12月29日から1月3日を除く)
外国語窓口
0120-0178-26(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
平日9時00分~20時00分 土曜・日曜・祝日9時00分~17時30分(12月29日から1月3日を除く)
※ 詳細は以下のリンクをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
企画総務局 区政課区政係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎9階
電話:082-504-2888(区政係)
ファクス:082-504-2069
[email protected]
