平成26年度 建設工事等に係る入札・契約制度の見直し(平成26年9月1日以降適用)
平成26年(2014年)8月1日
建設工事等に係る入札・契約制度について、「適正価格での競争の促進」及び「価格と品質が総合的に優れた内容の契約の実現」の観点から見直すことにより、地元事業者の育成と雇用の確保を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とします。
※印刷される場合及び参考資料はこのページの下にあるダウンロードファイルをご利用ください。
建設工事に係る見直し
1 最低制限価格及び調査基準価格の水準について
国が示す算定式に準じて最低制限価格及び調査基準価格の算定方法を下記のとおり見直し、その水準を引き上げます。なお、( )内の算定式で得た値(最低制限価格基準額及び調査基準価格基準額)は、入札書比較価格(予定価格(税抜))の70%(下限)から90%(上限)の範囲内とします。
最低制限価格の算定方法
現行
直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費×0.3)×0.95×偶発値×1.08
見直し後
直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費×0.55)× ×偶発値×1.08
調査基準価格の算定方法
現行
直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費×0.3)×偶発値×1.08
見直し後
直接工事費×0.95+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.8+一般管理費×0.55)×偶発値×1.08
2 低入札価格調査制度における総額失格基準について
設計金額3億円以上の工事について、国の特別重点調査の算定式に準じて総額失格基準の算定方法を次のとおり見直し、その水準を引き上げます。
また、設計金額1億円以上3億円未満の工事の総額失格基準の水準については、下記イメージ図のとおり1億円で見直し後の最低制限価格の水準に一致し、3億円で国の特別重点調査の水準に一致するよう逓減する仕組みにすることにより、最低制限価格との整合を図ります。
なお、総額失格基準の適否の判断は、競争入札参加資格確認と並行して行っていましたが、今後は、開札時にその適否を判断し、入札参加者に入札額の総額失格基準への適否が確認できるよう「保留通知書」に記載し、総額失格基準未満の価格の入札参加者に対しては資格確認を行わないことにします。
イメージ図
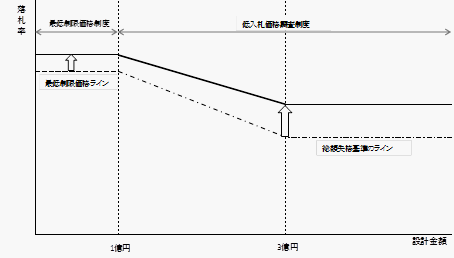
総額失格基準の算定方法
(1) 設計金額3億円以上の場合
現行
A×0.75+B1×0.75+B2×0.35+C×0.35+D×0.35
見直し後
A×0.75+B×0.70+C×0.70+D×0.30
(2) 設計金額1億円以上3億円未満の場合
現行
A×a+B1×b1+B2×b2+C×c+D×d
(係数の算定式)
a=0.9025-0.1525(K-100,000,000)/200,000,000
b1=0.855-0.105(K-100,000,000)/200,000,000
b2=0.855-0.505(K-100,000,000)/200,000,000
c=0.76-0.41(K-100,000,000)/200,000,000
d=0.285+0.065(K-100,000,000)/200,000,000
(a,b1,b2,c,dは少数第5位を切り捨て第4位までの値とする。)
見直し後
A×a+B×b+C×c+D×d
(係数の算定式)
a=0.95-0.20(K-100,000,000)/200,000,000
b=0.90-0.20(K-100,000,000)/200,000,000
c=0.80-0.10(K-100,000,000)/200,000,000
d=0.55-0.25(K-100,000,000)/200,000,000
(a,b,c,dは少数第5位を切り捨て第4位までの値とする。)
上記算定式のK,A,B,B1,B2,C及びDは、次の数値である。
K:設計金額(税込み)
A,B,B1,B2,C,D
|
A |
B |
B1 |
B2 |
C |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
直接工事費等 |
共通仮設費等 |
共通仮設費等 |
共通仮設費 |
現場管理費等 |
一般管理費等 |
参考
|
区分 |
内容 |
|---|---|
|
直接工事費等 |
直接工事費
|
|
共通仮設費等 |
共通仮設費
|
|
現場管理費等 |
現場管理費
|
|
一般管理費等 |
一般管理費 契約保証費が別にある場合は、一般管理費に加える。 |
3 建築一式工事に係る市内本店業者への下請発注の義務化について
建築一式工事では、技能労働者の不足が主たる原因となって入札不調が頻発していることから、入札不調の対策として、技能労働者が広く求められることができるよう、設計金額1億円以上6億円未満の工事を対象として実施している市内本店業者への下請発注の義務化を当分の間、建築一式工事に限って解除します。
4 社会保険・雇用保険への加入強化について
技能労働者の処遇改善を図ることにより、建設現場の担い手不足が改善され、建設業界の健全な発展に資するよう、新たに「社会保険・雇用保険への加入及び保険料の完納」を個々の工事の競争入札における入札参加条件に加え、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法により加入が義務付けられている事業者について、適正に加入し、規定の保険料が納付されていることを確認します。
資格確認の際の必要書類等の詳細は、別紙「社会保険・労働保険加入等に係る体系図及び確認書類」のとおりです。併せて、平成27・28年度の建設工事競争入札参加資格の要件にも、新たに「社会保険・雇用保険への加入及び保険料の完納」を加えます。
建設コンサルタント業務等に係る見直し
5 市内本店業者に限定した競争入札の対象範囲について
市内本店業者の受注機会を建設工事並みに拡大するため、市内本店業者に限定する競争入札の対象範囲を設計金額1千万円未満から1千5百万円未満へ拡大します。
6 最低制限価格制度の対象範囲について
市内本店業者に限定した競争入札の対象範囲の拡大に併せ、最低制限価格制度の対象範囲を設計金額1千万円未満から1千5百万円未満に拡大します。
7 最低制限価格の水準について
建設工事と同様に国が示す算定式に準じて最低制限価格制度の算定方法を下記のとおり見直し、その水準を引き上げます。なお、地質調査業務以外に係る業務について、( )内の算定式で得た値(最低制限価格基準額)は、入札書比較価格(予定価格(税抜))の60%(下限)から80%(上限)の範囲内とし、地質調査業務については、同様に入札書比較価格(予定価格(税抜))の3分の2(下限)から85%(上限)の範囲内とします。調査基準価格の算定式には変更がありません。
最低制限価格の算定方法
(1) 土木関係の建設コンサルタント業務
ア 間接経費に「その他原価」、「一般管理費」を用いる場合
現行
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)×0.95×偶発値×1.08
見直し後
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)× ×偶発値×1.08
イ 間接経費に「技術経費」、「諸経費」を用いる場合
現行
(直接人件費の額+直接経費の額+技術経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)×0.95×偶発値×1.08
見直し後
(直接人件費の額+直接経費の額+技術経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)× ×偶発値×1.08
(2) 測量業務
現行
(直接測量費の額+測量調査費の額+諸経費の額×0.4)×0.95×偶発値×1.08
見直し後
(直接測量費の額+測量調査費の額+諸経費の額×0.4)× ×偶発値×1.08
(3) 地質調査業務
現行
(直接調査費の額+間接調査費の額×0.9+解析等調査業務費の額×0.75+諸経費の額×0.4)×0.95×偶発値×1.08
見直し後
(直接調査費の額+間接調査費の額×0.9+解析等調査業務費の額×0.75+諸経費の額×0.4)× ×偶発値×1.08
(4) 建築関係の建設コンサルタント業務
現行
(直接人件費の額+特別経費の額+技術料等経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)×0.95×偶発値×1.08
見直し後
(直接人件費の額+特別経費の額+技術料等経費の額×0.6+諸経費の額×0.6)× ×偶発値×1.08
(5) 補償関係コンサルタント業務
現行
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)×0.95×偶発値×1.08
見直し後
(直接人件費の額+直接経費の額+その他原価の額×0.9+一般管理費等の額×0.3)× ×偶発値×1.08
8 参考:低入札価格調査制度における総額失格基準について
最低制限価格制度の対象範囲の拡大により、下記イメージ図のとおり低入札価格調査制度の対象範囲が設計金額1千万円以上から1千5百万円以上に変更となることから、総額失格基準の算定方法を下記のとおり変更します。
イメージ図
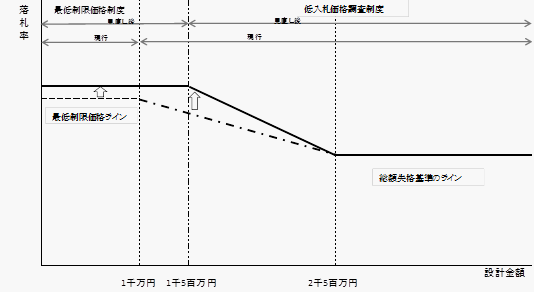
総額失格基準の算定方法
(1) 設計金額1千万円以上(改正後:1千5百万円以上)2千5百万円未満の場合
|
区分 |
総額失格基準額(税抜) |
|---|---|
|
測量 |
A×a+B×b1+D×d1 |
|
地質 |
A×a+B×b2+k1×g+k2×h+D×d1 |
|
建築 |
A×a+B×b1+C×c1+D×d2 |
|
土木 |
|
|
補償 |
A×a+B×b1+C×c2+D×d3 |
係数
- a=0.950-0.350(K-10,000,000)/15,000,000
- b1=0.950-0.350(K-10,000,000)/15,000,000
- b2=0.855-0.255(K-10,000,000)/15,000,000
- c1=0.570-0.270(K-10,000,000)/15,000,000
- c2=0.855-0.555(K-10,000,000)/15,000,000
- d1=0.380-0.080(K-10,000,000)/15,000,000
- d2=0.570-0.270(K-10,000,000)/15,000,000
- d3=0.285+0.015(K-10,000,000)/15,000,000
- g=0.7125-0.1125(K-10,000,000)/15,000,000
- h=0.7125-0.4125(K-10,000,000)/15,000,000
(a,b1,b2,c1,c2,d1,d2,d3,g,hは少数第5位を切り捨て第4位までの値とする。)
|
区分 |
総額失格基準額(税抜) |
|---|---|
|
測量 |
変更なし |
|
地質 |
変更なし |
|
建築 |
変更なし |
|
土木 |
変更なし |
| 土木 |
変更なし |
|
補償 |
変更なし |
係数
- a=1.00-0.40(K-15,000,000)/10,000,000
- b1=1.00-0.40(K-15,000,000)/10,000,000
- b2=0.90-0.30(K-15,000,000)/10,000,000
- c1=0.60-0.30(K-15,000,000)/10,000,000
- c2=0.90-0.60(K-15,000,000)/10,000,000
- d1=0.40-0.10(K-15,000,000)/10,000,000
- d2=0.60-0.30(K-15,000,000)/10,000,000
- d3=0.30
- g=0.75-0.15(K-15,000,000)/10,000,000
- h=0.75-0.45(K-15,000,000)/10,000,000
(a,b1,b2,c1,c2,d1,d2,d3,g,hは少数第5位を切り捨て第4位までの値とする。)
(2) 設計金額2千5百万円以上の場合
現行の算定方法から変更はありません。
|
区分 |
総額失格基準額(税抜) |
|---|---|
|
測量 |
A×0.6+B×0.6+D×0.3 |
|
地質 |
A×0.6+B×0.6+k1×0.6+k2×0.3+D×0.3 |
|
建築 |
A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3 |
|
土木 |
A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3 |
|
補償 |
A×0.6+B×0.6+C×0.3+D×0.3 |
上記(1)、(2)の算定方法のK,A,B,C,D,k1及びk2は、次の数値である。
K:設計金額(税込み)
A,B,C,D,k1,k2
|
分類区分 |
直接費等A |
直接費等B |
間接費等C |
間接費等D |
|---|---|---|---|---|
| 測量*1 |
直接測量費*4 |
測量調査費 |
諸経費 |
|
| 地質 |
直接調査費 |
間接調査費 |
解析等調査業務*5 |
諸経費 |
|
解析(*5の内訳) |
解析費等(k1) |
― |
諸経費等(k2) |
― |
| 建築*2 |
直接人件費 |
特別経費 |
技術料等経費 |
諸経費 |
|
土木*3 |
直接人件費 |
直接経費 |
その他原価 |
一般管理費等 |
| 土木*3 |
直接人件費 |
直接経費 |
技術経費 |
諸経費 |
| 補償 |
直接人件費 |
直接経費 |
その他原価 |
一般管理費等 |
- 道路環境調査(現地調査)、洪水痕跡調査、河川水辺環境調査、水質採水作業、水文観測、交通量調査等の業務を含む。
- 工事監理業務、耐震診断関連業務等の業務を含む。
- 道路環境調査(既存資料調査)等の業務を含む。
- 業務によって、直接調査費、直接業務費、直接採水費、直接費と呼ぶ。
- 解析等調査業務の歩掛は土木関係コンサルタント業務による。
実施時期
上記の建設工事及び建設コンサルタント業務等に係る見直しについては、平成26年9月1日以降に入札公告等を行うものから適用します。
ただし、緊急性の高い、市内本店業者への下請発注の義務化の解除(建設工事の3)については、平成26年7月1日以降に入札公告等を行うものから適用しています。
その他のお知らせ
建設工事
1 随意契約対象工事における一般競争入札の試行の廃止
設計金額100万円以上予定価格250万円以下の工事について、一部に導入していた一般競争入札の試行を廃止し、平成26年9月1日以降に入札公告等を行うものの契約方式は以下のとおりとします。
|
契約方式 |
対象工事 |
|---|---|
| 随意契約(見積合せ) | 予定価格250万円以下の工事 |
| 競争入札 | 予定価格250万円を超える工事 |
建設工事・建設コンサルタント業務等
2 平成27・28年度建設工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請
(1) 新規・一斉更新の申請受付
申請受付は、平成26年11月頃を予定しています。申請時期等の詳細については、「ひろしま市民と市政」(広報紙)やホームページでお知らせするとともに、平成25・26年度分の資格を認定されている業者の方へは電子メールでもお知らせします。
なお、今年度は、一斉更新受付の年に当たるため、平成26年度の建設工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請の追加受付は2回目(申請期間7月14日~7月18日)で終了しました。
(2) 建設工事競争入札参加資格の要件の設定
建設工事競争入札参加資格の要件に新たに「社会保険・雇用保険への加入及び保険料の完納」を加えました。健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が義務付けられている事業者について、当該保険への加入と保険料の納付に未納がないことを確認します。
加入については、原則、提出される経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」、「雇用保険加入の有無」の欄により確認します。
- いずれも「有」となっている場合は、当該通知書とともに日本年金機構若しくは健康保険事務組合が発行する直前2年間について未納がないことの証明書(証明日が競争入札参加資格審査申請書提出日から3か月前の日以降のもの)または過去2年間の保険料の領収書の写しのいずれかにより、保険料の納付に未納がないことを確認することになります。
- いずれかが「無」になっている場合は、建設工事競争入札参加資格の認定ができませんので、入札参加資格申請の手続き開始までに「無」となっている保険への加入手続きを行ったうえで、必要書類を整え当該申請を行ってください。
このほか、必要書類等詳細は、別紙「社会保険・労働保険加入等に係る体系図及び確認書類」のとおりです。また、「平成27・28年度広島市建設工事競争入札参加資格審査申請の手引き」に記載(予定)しますので、必ずご確認ください。
(3) 建設工事競争入札参加資格の認定に係る広島市評価事項について
広島市評価事項の詳細については、公告するとともに本市ホームページ、広島市建設工事競争入札参加資格審査申請の手引等に記載します。
問い合わせ先
広島市財政局契約部工事契約課
電話 082-504-2280(直)
Eメール [email protected]
関連情報
ダウンロード
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
財政局契約部 工事契約課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(15階)
電話:082-504-2280(代表) ファクス:082-504-2612
[email protected]
