「水の都ひろしま」構想 概要版
平成15年1月国土交通省・広島県・広島市
「水の都ひろしま」構想とは
太田川と瀬戸内海の存在は、広島市の大きな個性であり、また快適な環境の源となっています。その魅力をより一層引きだしていくためには、「水の都」づくりという方向で市民・企業・行政それぞれの努力を計画的に結集していく必要があります。
このため、平成2(1990)年3月に国・県・市の3者が協力して、広島市の太田川デルタを対象に「水の都整備構想」(以下「整備構想」といいます)を策定し、水の都づくりのための共通のよりどころとしてきました。
整備構想策定後10余年の間の努力の結果、現在では都心部を中心に美しい水辺が形成されつつあります。しかし策定当時と比較すると、社会経済の状況や市民ニーズなどが大きく変化してきています。水の都づくりにおいても、これまでのように、護岸や緑地などの整備を着実に進めていくことにあわせて、既に整備された河岸緑地などの利用を活性化させて、川や海を市民により身近なものにしていくことが重要になってきました。

そこでこれまでの実績を踏まえ、時代の変化にあわせて整備構想を見直し、新たに「水の都ひろしま」の実現に向けて取り組むための“よりどころ”として、この構想を策定しました。引き続き、市民や企業の新たなアイデアや意見を求めながら取り組みます。
「水の都ひろしま」構想の目的は、以下の3点です。
- 水辺等における都市の楽しみ方の創出
- 都市観光の主要な舞台づくり
- 「水の都ひろしま」にふさわしい個性と魅力ある風景づくり
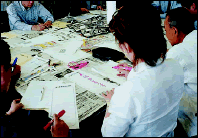

この構想は、これまでの水辺の整備にくわえて、水辺の活用や活動を円滑かつ効果的に進めるためのネットワークづくりなど、ソフトな取り組みを重視しています。また、市民の主体的な水辺活動について新たなアイデアを喚起する役割も期待しているところから、具体的な事業に展開しにくい内容や、実施主体が明確でない内容についても、取り組みとしてとりあげています。
構想策定の経緯
「水の都ひろしま」構想は、市民と行政の協働で策定することを基本としました。このために、平成12(2000)年度から3回の市民ワークショップおよび市民フォーラムを実施しながら平成14(2002)年5月に新・水の都委員会が構想(原案)をとりまとめました。さらに、この構想(原案)に対する市民のアイデアや意見などを踏まえたうえで、平成15(2003)年1月に「水の都ひろしま」構想を策定したものです。
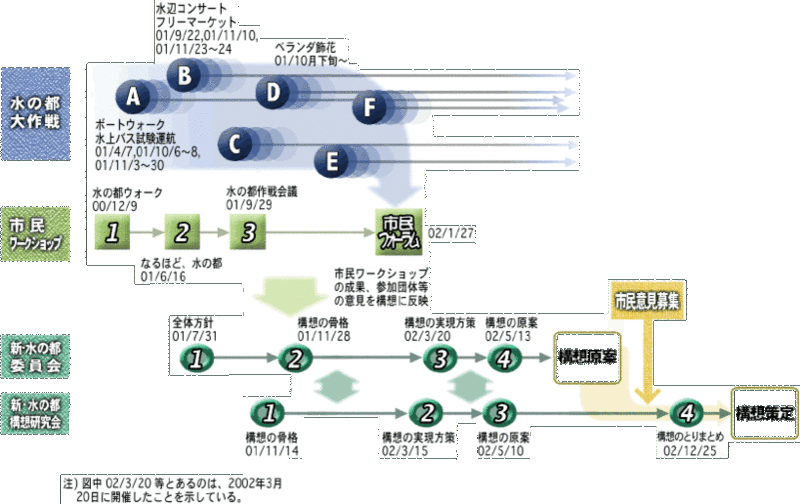
- 水の都大作戦:市民主導の社会実験(イベント)による水辺活用に関する効果の検証やニーズ測定を行い、より良い展開方向を提案しました。
- 市民ワークショップ:市民自らの体験や学習を通じて、水の都にふさわしいこれからの暮らし方や水辺の使い方の提案をとりまとめました。
- 新・水の都委員会:市民団体や経済団体の関係者と学識経験者で構成し、水の都大作戦や市民ワークショップの成果を反映させ、「水の都ひろしま」構想の骨格や方針の原案を提案しました。
- 新・水の都構想研究会:国・県・市の関係者で構成し、新・水の都委員会の構想原案を踏まえ「水の都ひろしま」構想をとりまとめました。
1 水の都ひろしまの特性
歴史
都市づくりは水辺づくりであった
太田川デルタでは、16世紀末の毛利氏の築城以降、干拓と築堤という水辺との関わりの中で都市づくりが進められました。
「都市づくりは水辺づくりであった」と言えます。
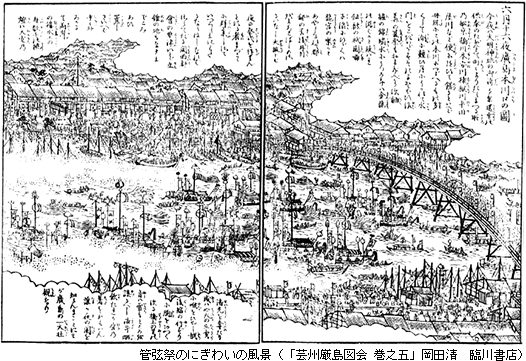
水辺はにぎわいの場所であった
水辺は昔から、人々の暮らしや遊びの場として賑わっていました。
水害の歴史を繰り返してきた
太田川は水害の歴史を繰り返し、大規模な河川改修や高潮対策事業を進めて今日にいたっています。
水面
干満による潮位の変化が極めて大きい
干満による潮位の変化が極めて大きく、舟運などの障害になっている一方、水辺に変化のある景観をもたらしています。
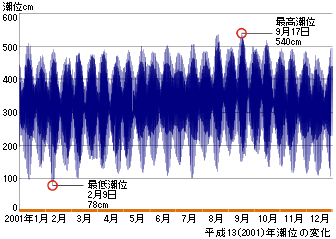
都市河川としては良好な水質を維持している
太田川は都市を流れる河川としては良好な水質を保っています。
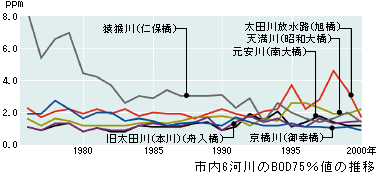
河川が市街地の高温化の緩和に貢献している
河川上で吹く海風が市街地のヒートアイランド現象の緩和に貢献しています。
広島の海や川では漁業が営まれている
広島の海や川では漁業が営まれており、身近に海や川での営みを感じることができます。

空間
水辺に多くの都市機能や観光・文化施設が立地している
都心部が河川に囲まれていることから、中心商店街や、駅、観光施設、文化施設などが多く水辺に立地しています。
これらを活用して、水の都らしいにぎわいを創出できる可能性があります。

水辺は街の際になっている
川沿いの建物の正面が道路側に向いていることや、河川が区の境界、町の境界、学校区の境界などコミュニティ境界となっていることから、水辺は街の「際(きわ)」として意識されてきました。
変化に富んだ水辺がある
それぞれの水辺は、水に親しめる場所、眺望の良い場所、歴史的遺構のある場所、橋のある場所、分流点と合流点、漁業の風景など変化に富んだ表情をもっています。
多くの個性的な橋がかかっている
広島の市街地を流れる6本の河川には約80の橋が架かっています。
個々の橋は歴史を感じさせる橋や、シンボル性の高い橋などがあり、市民に親しまれています。
また、路面電車の走る橋が6橋あり、路面電車が川を渡る風景が広島の風情を感じさせます。

水辺の歩行者空間が豊かである
水辺には豊かな緑地のある歩行者空間が連続して確保されており、快適に川沿いを歩くことができます。
水辺に接する敷地も多い
水辺の土地利用は、水辺、緑地、道路などの配置によっていくつかのタイプに分類できます。この中で水辺に接する緑地や宅地は、水辺と緑地や建物との一体的な活用が可能であり、このような可能性を有する敷地も多くあります。
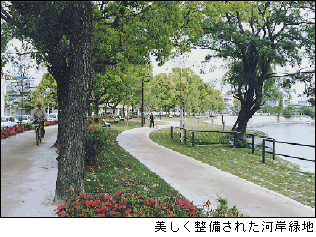
水辺の景観づくりを行ってきた
広島市においては、リバーフロント協議制度などによって、美しい水辺の景観づくりを進めてきました。
都市
市街地に占める水面の面積が大きい
太田川デルタでは市街地に占める水面の面積の比率が約13%と大きく、特に川幅の広い河川の多いことが特徴です。
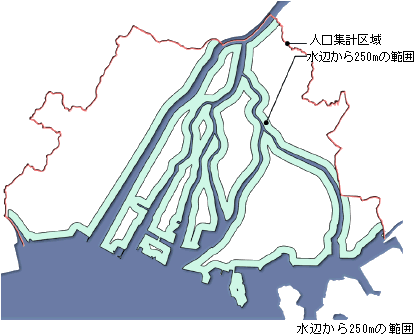
水の都としての全国的な認知度が低い
これだけの条件を備えていながら、広島は「水の都」としての全国的な認知度は高くありません。
全体人口の4割弱が水辺に居住している
デルタ市民のうち、4割弱が水辺の近くに居住しています。
注)デルタ人口を図の区域と仮定し、水辺から250mの区域に暮らす人口を試算するとデルタ人口の4割弱となる。250mは街区公園の誘致距離を目安として設定。
水辺利用
水上交通の気運が高まりつつある
海と川とを一体化させた水上交通の気運が高まりつつあります。
水辺は憩いの場として使われている
水辺は散策や休息、スポーツ、レクリエーションなどの場として日常的によく利用されています。
最近はオープンカフェなどの利用も見られるようになりました。

水の都広島の課題
本構想の目的にてらして、総括すると、以下の課題が指摘できます。
- 水の都としての特性が生活スタイルに生かされていない
- 水の都にふさわしい水辺空間の整備がまだ充分ではない
- 水辺利用に対応した仕組みやネットワークづくりが必要である
2 水の都をつくるための基本方針
水の都づくりの目標
広島は水の都としての優れた条件をもっており、その条件を生かしていくための課題を踏まえ、長期的な水の都の将来像として、次のような目標を掲げます。
- 市民が自ら水辺に深く関わって暮らし、水の都に住み、働き、憩う中で、水辺における豊かな思い出をもつことができること。
- 水辺がそのような舞台となるために、水辺自体が安全で気持ちよく、楽しい場所となっているだけでなく、暮らしの中心である街なかとのより密接な関係が確保されていること。
- そのような暮らしや場所づくりを支えるために、水辺を使ったネットワークや水辺利用のためのルールなど、水の都ならではのシステムをもっていること。
3つの柱
この目標を実現するために、次の3つの柱を設けます。また、この3つの柱に基づいて20の方針を示します。
1 つかう 市民による水辺の活用
市民がそれぞれの立場で主体的に水辺を活用して、水の都らしい生活を楽しむように、また楽しめるようにしていきます。同時に、観光をはじめとした都市活動の中で、水辺を役立てていくことにも積極的に取り組みます。
- 水辺を晴れの舞台にしよう
- 水辺を暮らしの中に取り入れよう
- 水辺で学ぼう
- 率先して環境に配慮しよう
- 水辺を飾ろう
- 水の都の風物詩をつくり育てよう
- 街の元気につなげよう
- 観光資源として活用しよう
2 つくる 水辺空間の整備とまちづくりとの一体化
水辺が気持ちよく、楽しく、美しく、安心できる場所となるよう、必要な整備を進めます。また、水辺が都市の空間構成の中でより重要な位置を占められるよう、まちづくりと一体となった取り組みを進めます。
- 個性的な水辺をつくろう
- 誰もが楽しめる水辺にしよう
- 泳げ遊べる水辺にしよう
- 水辺の景観を美しくしよう
- 水辺に行きやすく、水辺を歩きやすくしよう
- 水辺と街を一体的にデザインしよう
- 街の中で水の都を感じられるようにしよう
3 つなぐ 水辺のネットワークと水の都の仕組みづくり
水辺の活動や施設などを相互につないで、「つかい」「つくる」取り組みがより円滑に幅広く展開できるような、水の都にふさわしいシステムをつくりだします。このために、水上交通による物理的なネットワークをつくる一方で、行政や市民活動団体を横につなぐ社会的なネットワークをつくり、PRや流域連携、ルールづくりなどのための横断的・組織的な仕組みづくりを進めます。
- 水上交通ネットワークをつくろう
- 水の都をPRしよう
- 流域全体で取り組もう
- 水の都のルールをつくろう
- 水の都を盛り上げる組織をつくろう
1 つかう 市民による水辺の活用
水辺を晴れの舞台にしよう
水の都にふさわしく、式典やプライベートなセレモニー、パーティなど人生の大切なワンシーンを水辺で開催できるようにします。
取り組み
- 水辺のセレモニーやパーティーの企画・商品化
- 水辺を晴れの舞台とするための環境整備
(2) 水辺を暮らしの中に取り入れよう
日常的な暮らしの中で、散歩や休憩など何気ない楽しみの場、憩いの空間として大いに水辺を利用します。
取り組み
- 水辺の日常的利用支援事業
- 水辺に日常的に訪れる仕掛けづくり
- 水辺を憩いの場とするための環境整備

(3) 水辺で学ぼう
水辺を使って、誰でも、いつでも、どこでも学べるようにし、学んだことが評価されるようにしていきます。
取り組み
- 水の都に関連した学習プログラムの開発
- 川の先生・海の先生の育成
- 水の都フィールドミュージアムの推進
(4) 率先して環境に配慮しよう
人間だけでなく生きものすべてにとっての水の都であることをめざし、市民の環境意識を高めながらデルタの環境を保全・再生していきます。
取り組み
- 都心部における自然環境の保全
- 川や海の環境保全に関する市民の参加
- 水辺の環境についての情報発信
- 水循環への配慮
- クリーンアップイベントの開催

(5) 水辺を飾ろう
水辺に暮らす人が、自分たちの家や庭、公共空間を美しく飾ることによって、水辺の価値を高め、市民や観光客に華やかな風景を提供します。
取り組み
- 住民や企業による水辺建物の装飾
- 水辺の里親制度(市民による緑地管理)の実施
- デコレーションイベントの実施
(6) 水の都の風物詩をつくり育てよう
水の都らしい風物や行事を水辺で行うことにより、豊かな水の都の文化を育てるとともに魅力的な観光資源にしていきます。
取り組み
- 水の都に関わるイベントや行事のアピール
- イベントや行事への水の都らしさの取り入れ
- 新しい水の都の風物詩づくり
- 水辺に風物詩をつくり育てるための環境整備
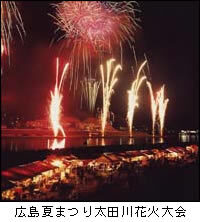
(7) 街の元気につなげよう
商店やレストランなど、街の活動が顔を出し、水辺がにぎやかで活気のある場所となっていくようにします。
取り組み
- 水辺への商業施設の誘導
- 商店街による水辺の活用と川の駅の設置
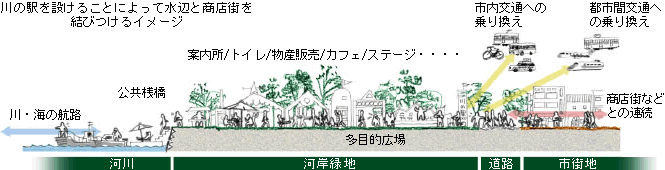
(8) 観光資源として活用しよう
水辺を広島の都市観光資源としてもっと活用し、既存の観光資源にも水辺の魅力をつけ加えて、「水の都ひろしま」の都市イメージを発信していきます。
取り組み
- 水の都観光の企画・商品化
- 新しい観光資源の開拓
- 海の観光拠点づくり
- 水の都に関わる観光情報の提供
- 水の都に関わる観光受け入れ機能の強化
2 つくる 水辺空間の整備とまちづくりとの一体化
個性的な水辺を作ろう
それぞれの水辺の特徴を生かして、広島ならではの自然、歴史、文化が感じられるような水辺にしていきます。
取り組み
- 場所に応じた水辺の名所づくり
- 橋の名所づくり
- 市街地内での新しい形式の水辺の創出
- 自然豊かな水辺づくり
- 漁業との共生
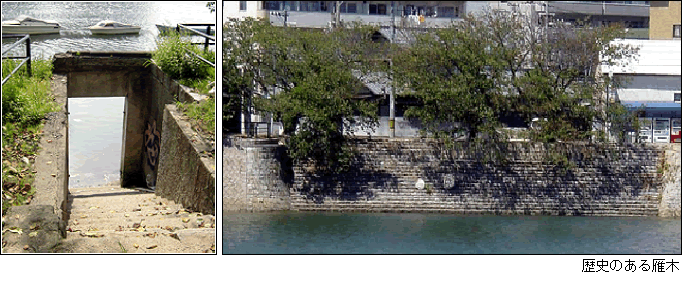
(10) 誰もが楽しめる水辺にしよう
子どもも高齢者も障害者も、誰もが行け、集い、楽しみ、交流できるような開かれた水辺づくりを行います。
取り組み
- 重点地区におけるユニバーサルデザインの導入
- 保健・福祉的な視点での水辺利用の促進
- 公開空地の水辺への誘導と積極的な活用の推進
- 水辺に直接面した民間施設の公益的な空間づくりの推進

(11) 泳げ遊べる水辺にしよう
容易に水面に近づくことができ、安心して泳げ、安全に楽しく遊べるような水辺をたくさんつくります。
取り組み
- 子どもが泳げ遊べる川づくり
- 海と遊べる環境づくり
- 水辺での遊びを推進するための環境整備
- 水質・底質の改善
(12) 水辺の景観を美しくしよう
水辺の建物、環境デザインの質を高め、水辺においてより美しく水の都らしい景観づくりを進めます。
取り組み
- リバーフロント建築のデザイン・美化
- 水辺の構成要素のデザイン・美化
- 夜の風景づくり
- 港の景観計画の策定

(13) 水辺に行きやすく、水辺を歩きやすくしよう
街と水辺を結ぶ、あるいは橋による分断を補完する歩行者動線を確保することにより、どこからでもすぐ来られて、どこまでも安心して歩いていけるような、快適な歩行者空間をつくります。
取り組み
- 水辺の歩行者空間の連続性の確保
- 水辺に隣接する街区内へのフットパス*づくり
- 水辺の歩行者系ネットワークの確立
- 水辺沿いの快適な歩行者環境づくり
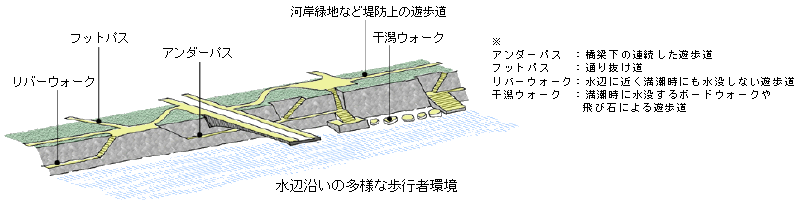
(14) 水辺と街を一体的にデザインしよう
水辺と街の要素とを一体的に調和のとれた関係となるように配置し、公園や街並みなどがもっと水辺の魅力を受けられるように、またそれによって水辺の空間がより利便性が高く拡がりをもてるようにします。
取り組み
- 水辺と一体となった民間施設・公共施設のデザインの促進
- 水辺と街を分断する車道のあり方の工夫
- 風の道を生かした建築物の誘導
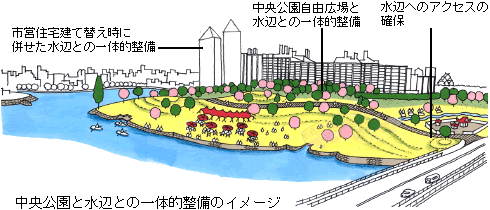
(15) 街の中で水の都を感じられるようにしよう
水の豊かさ、身近さが街にいても感じられ、水の都らしい雰囲気が街中にあふれるようなまちづくりを進めます。
取り組み
- 市街地と水辺をつなぐ整備
- 水のギャラリーの設置
- 水の都としての特徴の体系的な収集整理と学習
- 市街地における水辺の実況中継
3 つなぐ 水辺のネットワークと水の都の仕組みづくり
(16) 水上交通ネットワークを作ろう
水辺の様々な都市機能や観光施設を相互に航路でつなぎ、市民や観光客が利用できるように、水上交通のネットワークを充実させていきます。
取り組み
- 水上バス・タクシーの運航
- ネットワークの要となる公共桟橋の整備
- 広島の条件に適合するオリジナル船の開発
- 安定航路確保のためのしゅんせつや橋梁桁下空間の確保

(17) 水の都をPRしよう
太田川デルタを「水の都」として堂々とPRしていきます。
取り組み
- 水の都キャンペーンの実施
- 水の都の情報誌の発行とホームページの運営
- 水の都風土記(ライブラリー)の編纂と展示
(18) 流域全体で取り組もう
水の都を支える上流・中流域の地域づくりを下流のデルタ地域の住民がサポートするなど、流域全体の視野をもった地域連携の取り組みを積極的に進めます。
取り組み
- 上・中流域の農山村との交流
- 流域全体としての取り組み

(19) 水の都のルールを作ろう
水辺利用の基本的なルールを明解にし、積極的に普及させ、誰もが容易に水辺を活用できるようにしていきます。
取り組み
- 水の都にふさわしい市民のマナーの普及
- 水辺空間利用のルールづくりとその普及
(20) 水の都を盛り上げる組織をつくろう
多様で活力のある市民活動やそれらをサポートする市民組織を育成し、市民主体の水の都づくりを継続的に進めていく。
取り組み
- 水の都に関わるNPOや市民活動組織の育成
- 水の都を推進する組織づくり
3 水の都の実現方策
取り組みの方向性
水の都を実現するために、次の方向性を基本とした取り組みを進めます。
- 水辺の利用に関する様々な「社会実験によって先導する」
- 市民・企業・行政が「協働で取り組む」
重点的な取り組み
(1) 水の都のモデル地区・モデル事業の設定と実験的な取り組みの推進
水の都づくりに戦略的に取り組むために、水の都の推進にとって効果が高く、可能性も高い地区または事業を、モデル地区またはモデル事業として設定して、実験的な取り組みを進めていきます。
モデル地区、モデル事業は今後、必要に応じて設定していくものとします。
ア モデル地区の設定
モデル地区として、次の4地区を設定します。
- 猿猴川広島駅南口周辺地区(猿猴川分流点~平和橋)
- 京橋川右岸地区(縮景園~鶴見橋)
- 旧太田川(本川)(三篠橋~西平和大橋)・元安川(相生橋~平和大橋)地区
- 太田川放水路地区
イ モデル事業の設定(候補)
- 泳げ遊べる川づくり
- 河川プールの実験
- ヘドロ除去・砂の投入による川床の美化
- 干潟や砂浜の保全による良好な生態環境の創出
- カヌーを水辺へ降ろせるような護岸整備
- 水辺のユニバーサルデザインの導入
多くの人が訪れる水辺、高齢者や障害者の利用を想定すべき水辺などにおけるバリアフリーの推進、サインの整備、障害者用トイレの設置など - 水上のにぎわい施設の設置
- 水上レストラン、水上ステージ
- カヌーの利用を容易にする護岸等の整備
- 水辺へのにぎわいの誘導
- 夜間照明など、水辺の空間演出
- 水辺のにぎわい基盤施設の整備
- 水上交通の運航
- 水上バス・タクシーの運航
- 雁木へのボート接岸を容易にする施設の設置
- 海と川のレクリエーションの振興
マリーナやボートパークの整備 - 水の都の森づくり
植樹による河岸の名所づくり(京橋川河岸におけるハナミズキの植樹など)
(2) 水辺空間利用のルールづくりとその普及
ア 水辺空間利用に関するルールの整理
堤防や河川敷、護岸、雁木、桟橋、水面、船舶、橋梁など水辺の公共空間の利用にあたっての基準や運用などについて、市民にわかりやすく整理を行います。
イ 積極的なルールの普及
整理されたルールを、水辺空間を使う立場である市民や企業に積極的に知らせ普及させる取り組みを行います。
(3) 水の都のための展開と組織づくり
ア 主体的な展開のための実践組織の設置検討
水の都を活性化させる事業に主体的に取り組むために、新たな市民中心の組織の設置を検討します((仮称)水の都協会)。
イ 総合的な水辺空間整備・利用のための企画・調整組織の設置
水辺空間の総合的、一体的な整備を進め、効率的な管理を図るために、河川や港湾管理者(国、県)と広島市を中心とした企画・調整組織を設置します((仮称)水の都調整会議)。
市民・企業・行政の役割分担
市民、企業、行政が協働で取り組むことは、本構想の基本的な考え方です。それぞれの役割を適切に分担しながら、20の基本方針に掲げた取り組みや重点的な取り組みを効率的に進めていきます。
4 モデル地区計画
モデル地区計画の趣旨
モデル地区については、次の趣旨で計画を立案します。
- 20の基本方針を目に見える形で集中的かつ早期に実現させ、その効果を市民が享受できるようにすること(看板の役割)
- モデル地区以外の地区における水の都づくりの展開に対して、先導的な役割を果たすこと(先導の役割)
- 直ちに全面展開することが難しいような新たな制度運用、整備内容について、地区を限定して実験的に取り組めるようにすること(実験の役割)
計画内容は、各地区における水の都づくりの長期的な方向性とアイデアを示すこととします。したがって、実現のための具体的なプログラムは必ずしも想定していません。モデル地区については、平成15年度から都市再生プロジェクトの一環として、社会実験の取り組みが予定されているところであり、今後の具体的な実施内容とその工程については、市民や企業の新たなアイデアや意見を求めながら、実現へ向けた検討を進めていきます。
モデル地区は、今後必要に応じて設定していくものとします。
モデル地区の設定
モデル地区は、計画立案の趣旨から、次のような観点で設定します。
- 看板の役割、先導の役割からみて、効果の大きい地区であること。
- 先導的・実験的な取り組みにあたって、その可能性が高い地区であること。
- 水辺の公共空間の活用を進める必要性が高い地区であること。
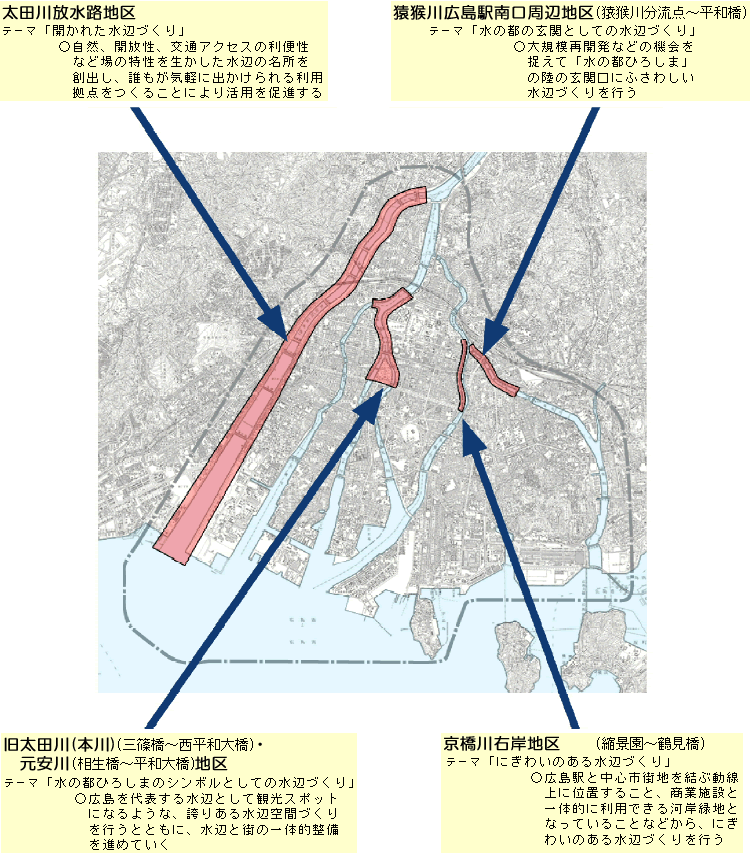
注)モデル地区の位置
猿猴川広島駅南口周辺地区(猿猴川分流点~平和橋)
テーマ 「水の都の玄関としての水辺づくり」
大規模再開発などの機会を捉えて「水の都ひろしま」の陸の玄関口にふさわしい水辺づくりを行う
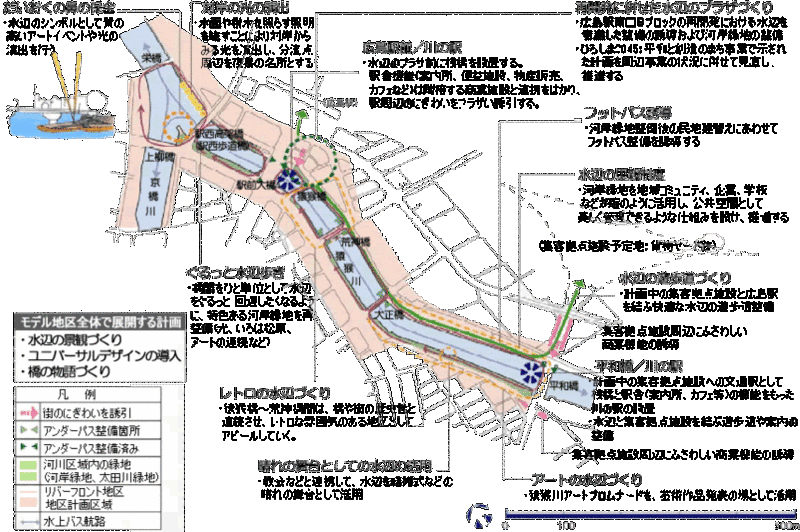
京橋川右岸地区(縮景園~鶴見橋)
テーマ 「にぎわいのある水辺づくり」
広島駅と中心市街地を結ぶ動線上に位置すること、商業施設と一体的に利用できる河岸緑地となっていることなどから、にぎわいのある水辺づくりを行う
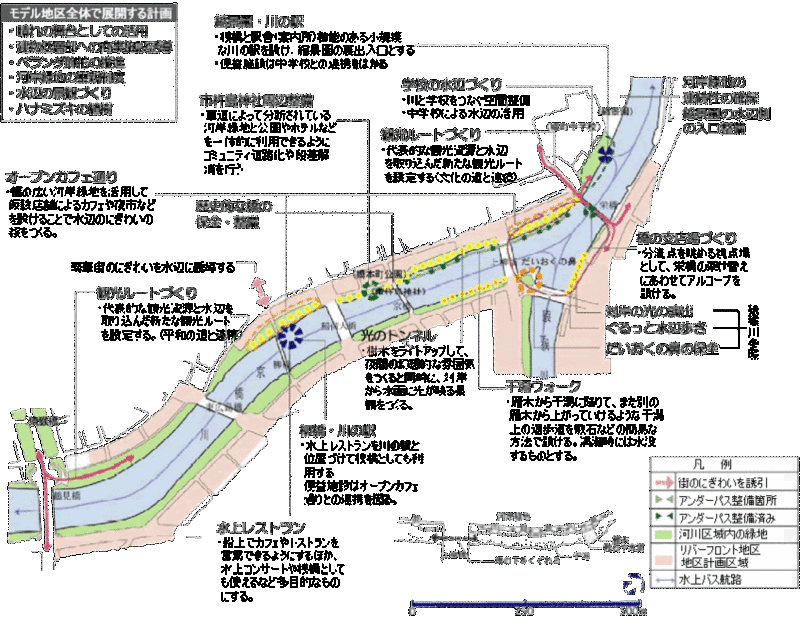
旧太田川(本川)(三篠橋~西平和大橋)・元安川(相生橋~平和大橋)地区
テーマ 「水の都ひろしまのシンボルとしての水辺づくり」
広島を代表する水辺として観光スポットになるような、誇りある水辺空間づくりを行うとともに、水辺と街の一体的整備を進めていく
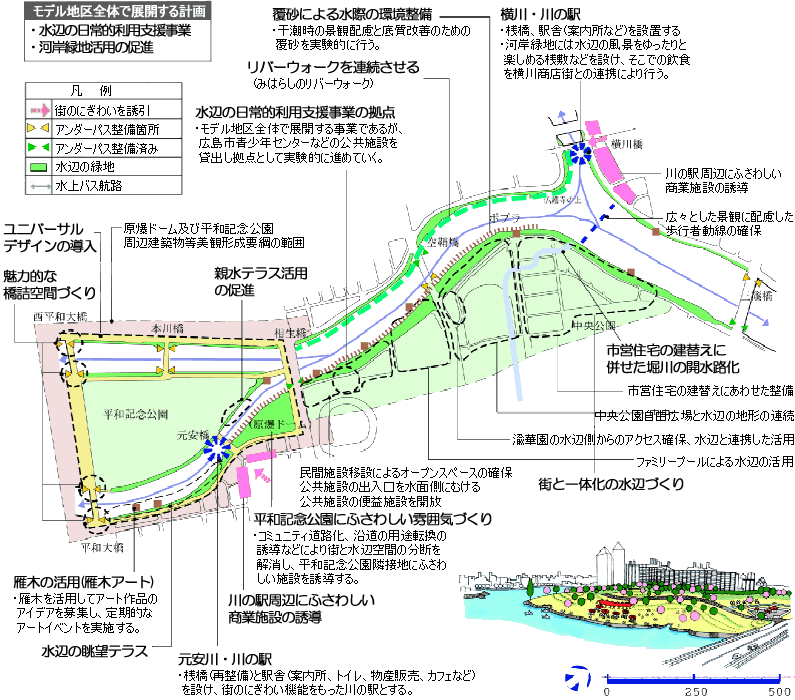
太田川放水路地区
テーマ 「開かれた水辺づくり」
自然性、開放性、交通アクセスの利便性など場の特性を生かした水辺の名所を創出し、誰もが気軽に出かけられる利用拠点をつくることにより活用を促進する
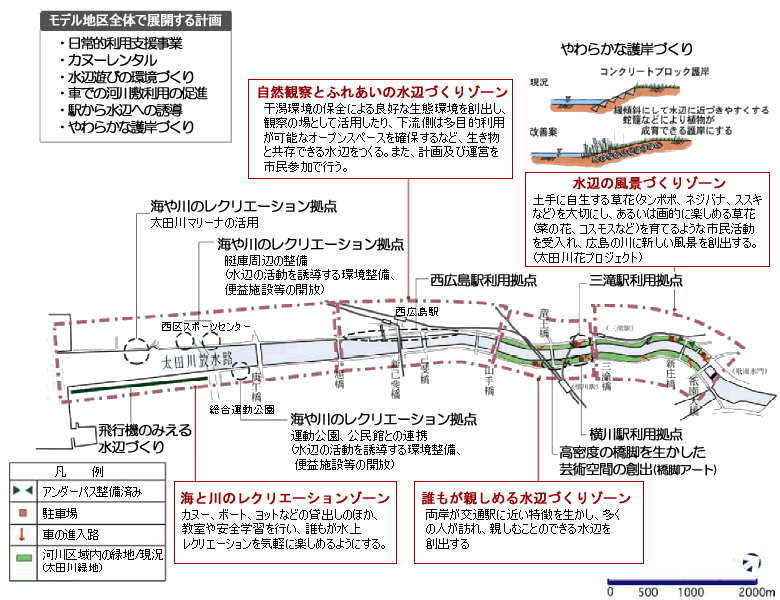
このページに関するお問い合わせ先
経済観光局 観光政策部 おもてなし推進担当
電話:082-504-2676/ファクス:082-504-2253
メールアドレス:[email protected]
このページに関するお問い合わせ
経済観光局観光政策部 おもてなし推進担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2676(代表) ファクス:082-504-2253
[email protected]
