すすめよう 仕事と生活の調和
仕事と生活の調和ってなに?
年齢や性別を問わず誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、自己啓発など様々な活動を自らの希望するバランスで行うことができる状態のことです。
このことは、「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある社会を実現する上で大変重要です。
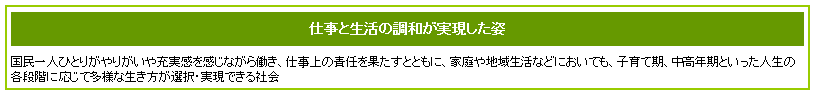

男性も女性もあらゆる世代の誰もが仕事や子育て、介護、自己啓発、地域活動など様々な活動を自分の希望するバランスで展開でき、「仕事」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらします。
→多様性を尊重した活力ある社会
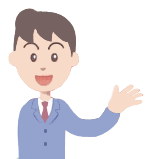
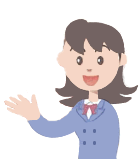
なぜ今、仕事と生活の調和が必要なの?

少子高齢化、人口減少を迎え、これまでの働き方では、個人、企業・組織、社会全体が持続可能なものではなくなる恐れがあります。
個人、社会全体、個々の企業・組織それぞれにとって、仕事と生活の調和の推進は極めて重要な課題となっています。
1 個人にとっての必要性 → 希望するバランスの実現
- 仕事と家庭の両立が困難
- ライフスタイルや意識の変化
- 両立希望に反して仕事中心になる男性
- 家庭責任が重く希望する形で働くのが難しい女性
- 自己啓発や地域活動への参加が困難
- 長時間労働が心身の健康に影響
→希望するバランスの実現のために必要
2 社会全体にとっての必要性 → 経済社会の活力向上
- 労働力不足の深刻化
- 生産性の低下・活力の衰退
- 少子化の急速な進行
- 地域社会のつながりの希薄化
→経済社会の活力向上のために必要
3 個々の企業・組織にとっての必要性 → 多様な人材を生かし競争力を強化
人材確保競争の激化
→多様な人材を生かし競争力を強化するために必要
- 従業員の人生の段階に応じたニーズへの対応(若年層、子育て層、介護層、高齢層)
- 意欲や満足度の向上
- 心身の健康の維持
- 女性の活用
- ワーク・ライフ・バランスは経営戦略の重要な柱:「明日への投資」
- 中小企業にとっては特に大きな意義
「『ワーク・ライフ・バランス』推進の基本的方向(平成19年7月 男女共同参画会議・仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)に関する専門調査会)」より
仕事と生活の調和を進めるには?
社会全体で意識改革を

仕事と生活の調和を実現するためには、市民、企業、行政が連携し、「男は仕事。女は家庭」といった性別による固定的な役割分担意識の解消や、働き方の見直しなど、社会の意識改革に取り組むことが必要です。
広島市の取組 仕事と生活の調和を推進している民間事業者を表彰
広島市では、仕事と生活の調和の推進や女性の能力発揮、職域拡大などに積極的に取り組む市内の民間事業者を公募・選考し、男女共同参画推進事業者として市長表彰を行っています。
また、受賞された事業者については、市の広報で広く市民にPRするとともに、優遇措置を受けることができますので、ぜひご応募ください。
(募集期間は1月~3月です。詳細はホームページでお知らせします。)
受賞事業所に対する優遇措置
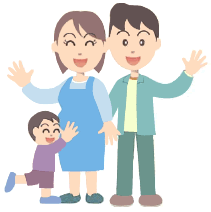
- 入札制度等における優遇措置
- 競争入札参加資格審査申請業者(建設工事、建築物清掃及び常駐警備)の等級区分の決定の際に加点
- 総合評価方式による競争入札の際に加点
- 男女共同参画・子育て支援資金による中小企業に対する低利融資
仕事と生活の調和について、あなたの考えや職場の状況はどうですか。
Q1あなたの考え方はどうですか
- 子育ては男女が共に行うものなので、育児休業は男性が取っても女性が取ってもかまわない
- 男性が育児休業などで仕事を中断しても、昇進面などでできるだけ不利益のないようにすべきである
- 育児休業制度などを利用することは、必ずしも会社にとってマイナスではない
- 生活との調和が図られることによって仕事に対してもやる気が出る
- 「男は仕事、女は家庭」といった性別で役割分担を固定する考え方は改めるべきである
Q2あなたの職場の状況はどうですか
- 社員の希望に応じて育児休業が取得できる
- ノー残業デーの導入など時間外労働削減のための措置が行われている
- 時短勤務、フレックスタイム制、隔日勤務など多様な働き方ができる
- 育児休業制度などを利用しやすくするための研修や情報提供が行われている
- 配転を決める際には、社員の生活面について配慮されている
- 経営者や管理者が従業員に仕事と生活の調和を進める働きかけを行っている
男性も女性も仕事と生活を上手に調和させていきたいですね。


広島市からのお知らせ
事業所向け男女共同参画支援講座

男女共同参画に関する理解を深め、男女ともに働きやすい雇用環境づくりができるよう、事業所の職場研修のお手伝いをします。
このページに関するお問い合わせ先
市民局 人権啓発部 男女共同参画課
電話:082-504-2108/ファクス:082-504-2609
メールアドレス:[email protected]
このページに関するお問い合わせ
市民局人権啓発部 男女共同参画課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2108(代表) ファクス:082-504-2609
[email protected]
