低炭素建築物新築等計画の認定制度
1.制度の概要
都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定します。
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
広島市の区域において認定申請する場合の窓口は、都市整備局指導部建築指導課となります。
※広島市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱を一部改正しました。(令和6年4月1日)
※低炭素建築物新築等計画認定申請手数料額を改定しました。(令和7年4月1日)
※広島市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱を一部改正しました。(令和7年4月1日)
2.認定のメリット
低炭素建築物新築等計画の認定を受けて低炭素建築物の新築等を行なった場合、次のメリットがあります。
税の特例(住宅のみ)
- 住宅ローン減税制度における所得税の減税が一般より多く受けられます。
- 保存登記及び移転登記にかかる登録免許税の税率が引き下げられます。
【認定低炭素住宅に対する税の特例】については、認定低炭素住宅に対する税の特例(国土交通省)をご覧ください。
【所得税(国税)】については、住所地を管轄する「税務署」又は「広島国税局」へお問い合わせください。
【住宅用家屋証明書】については、住宅用家屋証明書について知りたいのですが。(FAQID-9999)をご覧ください。
容積率の特例
容積率を算定するための床面積について、低炭素化に資する施設(蓄電池等)に要する部分の床面積(低炭素建築物の延べ面積の20分の1を上限)を算入しないことができます。
【容積率の特例】を活用する場合は、円滑な認定審査を行うため、後述する審査機関への事前審査前に、不算入床面積の適用範囲となるかどうかについて、広島市(建築指導課)と協議をしてください。協議の際には、必要書類一覧表(当該設備の概要・位置、当該床面積の算定根拠が分かる資料等)を持参してください。また、建築物全体の床面積について、別途、確認申請を提出する指定確認検査機関等と協議しておいてください。
3.認定までの主な流れ
広島市への認定申請に先立ち、審査機関が実施する技術的審査(事前審査)を受けてください。
- 申請者は、審査機関(「4.審査機関について」を参照)に技術的な基準の事前審査を依頼してください。
- 基準に適合している場合は適合証が交付されます。
- 申請者は、申請書と「1.」で審査機関が技術的審査を終了した旨が確認できる押印された添付図書に、「1.」で交付された適合証(副本には適合証の写し)を添付した正本及び副本(計2部)により、広島市(建築指導課)に申請します。
- 認定申請を受けた広島市(建築指導課)は、適合証等の必要書類を確認し、基準に適合している場合は認定通知書を申請者に交付します。
認定後の手続きについては、「10.認定後の手続き等について」をご覧ください。
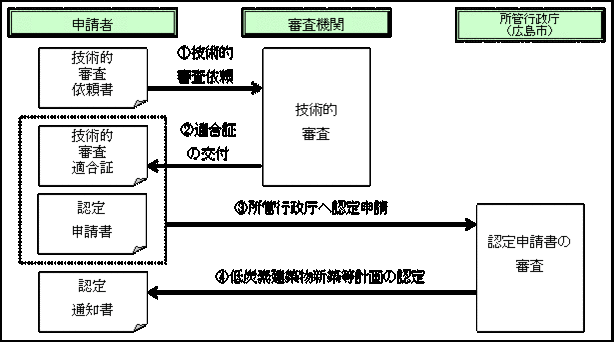
4.審査機関について
広島市が定める「審査機関」とは、業として、建築物を設計し若しくは販売し、建築物の販売を代理し若しくは媒介し、又は新築の建設工事を請け負う者に支配されていないものであって、法第53条第1項の低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号のすべてに掲げる基準に適合するかどうかの技術的審査を行う機関をいいます。
次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める機関により技術的審査を受けてください。
住宅部分に係る申請の場合
登録住宅性能評価機関
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
非住宅部分に係る申請の場合
登録建築物エネルギー消費性能判定機関
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
広島市内に事務所を置く技術的審査実施機関は、次のとおりです。業務範囲等の詳細については、各機関に直接お問い合わせください。(平成30年4月1日時点、50音順)
- 審査機関
- 株式会社ジェイ・イー・サポート
- 所在地
- 広島市中区八丁堀15番8号 三菱UFJ信託銀行広島ビル6F
- 電話
- 082-836-3300
- 審査機関
-
株式会社西日本住宅評価センター
広島支店
- 所在地
-
広島市中区本川町二丁目6番5号 相生橋KMビル4階
- 電話
- 082-532-6045
- 審査機関
-
ビューロベリタスジャパン株式会社
- 所在地
- 広島県広島市中区胡町4-21 朝日生命広島胡町ビル2F
- 電話
- 082-543-6000
- 審査機関
-
日本ERI株式会社 広島支店
- 所在地
- 広島市中区上八丁堀14番4号 JEI広島八丁掘ビル3階
- 電話
- 082-211-5500
- 審査機関
- ハウスプラス中国住宅保証株式会社
- 所在地
-
広島市中区国泰寺町一丁目3番32号 国泰寺ビル1階
- 電話
- 082-577-5638
- 審査機関
- 株式会社広島建築住宅センター
- 所在地
- 広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル3階
- 電話
- 082-228-2220
審査機関については、以下のホームページからも検索ができます
-
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(外部リンク)

(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 ホームページ) -
登録住宅性能評価機関(外部リンク)

(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 ホームページ)
5.認定基準等の概要
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準等に適合していなければなりません。
|
項目 |
概要 |
|---|---|
| 1.建設場所 | 市街化区域内 |
| 2.申請ができる人 |
|
|
項目 |
概要 |
|---|---|
| 1.定量的評価項目 |
一次エネルギー消費量の算定については、「Webプログラム」がご利用できます。
Webプログラムについては、住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(独立行政法人建築研究所)のページをご覧ください。 |
| 2.選択的項目 |
|
| 3.基本方針 |
低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)に照らして適切なものであること。
平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号 第4.(2)3に規定する「都市の緑地の保全への配慮」抜粋
都市の低炭素化を促進する上で、都市の緑地を保全することが重要であることに鑑み、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合していない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合には認定は行わないことを基本とする。
平成24年12月4日現在、広島市に設けられた「都市の緑地の保全への配慮が必要な区域等」は、以下のとおりです。
|
| 4.資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
-
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(独立行政法人建築研究所)(外部リンク)

-
設計内容説明書(基本的方針用) (Excel 39.0KB)

-
ひろしま地図ナビ【都市計画情報】(外部リンク)

6.必要な図書
- 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条第1項に規定する図書
- 広島市長が定める図書
必要書類一覧表により、図書等の確認を行ったうえで、申請してください。
7.各種様式
1.省令により定められている様式
- 省令様式第五(認定申請書)(令和7年3月31日まで) (Word 120.0KB)

- 省令様式第五(認定申請書)(令和7年4月1日以降) (Word 126.0KB)

- 省令様式第七(変更認定申請書)(令和7年3月31日まで) (Word 40.0KB)

- 省令様式第七(変更認定申請書)(令和7年4月1日以降) (Word 40.0KB)

2.広島市が定める様式
- 要綱第02号様式(軽微変更該当証明申請書) (Word 37.5KB)

- 要綱第06号様式(工事完了報告) (Word 38.5KB)

-
(記入例) (PDF 115.6KB)

- 要綱第07号様式(新築等状況報告) (Word 35.5KB)

- 要綱第08号様式(取下届) (Word 37.0KB)

- 要綱第10号様式(取りやめ届) (Word 37.5KB)

-
(参考様式)設計内容説明書(基本的方針用) (Excel 39.0KB)

-
(参考様式)低炭素建築物変更説明書 (Word 48.0KB)

8.申請窓口
広島市役所本庁舎6階 建築指導課
電話:082-504-2288
ファクス:082-504-2529
9.申請手数料
広島市都市計画関係手数料条例の中で、都市の低炭素化の促進に関する法律における認定申請について徴収する手数料を定めています。
条例本文は、「広島市例規類集」により、“広島市都市計画関係手数料条例”と検索してご覧ください。
(申請手数料は、こちら(低炭素建築物新築等計画認定申請手数料一覧(令和7年4月1日改正) )をご覧ください。)
10.認定後の手続き等について
1.計画を変更しようとする場合
認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更する場合、軽微な変更を除き、「変更認定申請」の手続きが必要になります。
また、増築、改築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修を行う場合、竣工後であっても、軽微な変更を除き、「変更認定申請」の手続きが必要になります。
工事完了時に、変更認定申請が必要であることが判明し、改善を求められても従わない場合、認定を取り消されることがあります。このため、計画を変更する場合は、変更の手続き(「変更認定申請」又は「軽微な変更」)について、以下の手続きにより、建築指導課にご相談ください。
- 軽微な変更とは(施行規則第44条)
- 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
- 変更の手続きの流れ
- 低炭素建築物変更説明書及び変更しようとする全ての図書等を作成し、建築指導課にご相談ください。
- 変更によって、交付された適合証が有効であるかどうか(技術的審査の基準に関係あるかどうか)を、「審査機関」と1.と同じ図書で協議してください。
- 2.の結果を建築指導課にお知らせください。
- 2.の内容について確認した後、変更の手続き(「変更認定申請」または「軽微な変更」)を決定します。
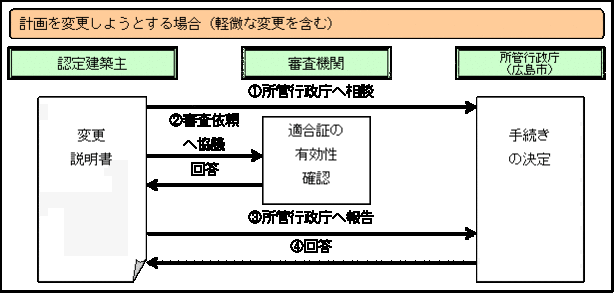
1.工事が完了した場合
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了したら、速やかに工事完了報告(記入例)を提出してください。
その際、工事が完了したことを確認できるよう、建築基準法に基づく検査済証の写し及び2面以上の建築物の外観写真(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真のみ)の添付をお願いします。
※外観写真は2面すべての開口部(窓、ドア等)の位置と大きさが確認できるものを添付してください。隣地との間隔が狭いなど、外観写真の撮影が困難な場合は、室内側から開口部を撮影し、図面等で撮影箇所を示すなどしてください。
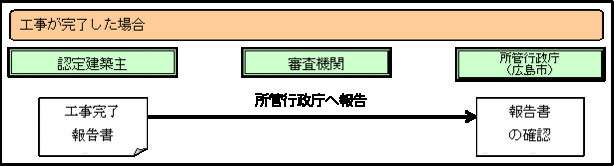
2.報告を求められた場合
広島市は、必要に応じて、認定低炭素建築物の新築等の状況について、報告を求めることがあります。
その際、認定建築主は、新築等状況報告書により報告をしてください。
3.申請を取下げる場合
認定をする前に、申請を取り下げようとするときは、取下届(正本及び副本)を届け出てください。
4.計画を取りやめる場合
認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等を取りやめようとするときは、取りやめ届(正本及び副本)に、認定通知書を添付して、届け出てください。
5.認定の取消しについて
以下の場合に該当し、改善を求められても従わない場合、認定を取り消されることがあります。この場合、認定は認定当初より無効となりますので、留意してください。
- 不適切な申請により認定を受け、認定当初から認定基準に適合しない状態であると認める場合
- 認定された計画に従って低炭素建築物の新築等が行われておらず、建設当初から認定基準に適合しない状態であると認める場合
11.関連リンク
-
都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報(国土交通省)(外部リンク)

-
低炭素建築物認定制度について(一般財団法人 住宅性能評価・表示協会(外部リンク)

-
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(独立行政法人建築研究所)(外部リンク)

-
長期優良住宅認定制度において、認定通知書偽造や認定基準不適合等の不正事案が発生しています。(国土交通省)(外部リンク)

-
よくあるご質問(国土交通省)(外部リンク)

12.ダウンロード
-
広島市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱(令和7年4月1日改正) (Word 64.5KB)

-
必要書類一覧表 (Word 28.4KB)

- 省令様式第五(認定申請書)(令和7年3月31日まで) (Word 120.0KB)

- 省令様式第五(認定申請書)(令和7年4月1日以降) (Word 126.0KB)

- 省令様式第七(変更認定申請書)(令和7年3月31日まで) (Word 40.0KB)

- 省令様式第七(変更認定申請書)(令和7年4月1日以降) (Word 40.0KB)

- 要綱第02号様式(軽微変更該当証明申請書) (Word 37.5KB)

- 要綱第06号様式(工事完了報告) (Word 38.5KB)

- 要綱第07号様式(新築等状況報告) (Word 35.5KB)

- 要綱第08号様式(取下届) (Word 37.0KB)

- 要綱第10号様式(取りやめ届) (Word 37.5KB)

-
(参考様式)設計内容説明書(基本的方針用) (Excel 39.0KB)

-
(参考様式)低炭素建築物変更説明書 (Word 48.5KB)

-
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料一覧(令和7年4月1日) (PDF 158.7KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局指導部 建築指導課第二指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号6階
電話:082-504-2288(第二指導係) ファクス:082-504-2529
[email protected]
