広島平和記念資料館展示整備等基本計画 第4章
第4章 管理運営
1 管理運営の指針
平和記念資料館では、被爆の実相をより分かりやすく伝えていくため、展示の充実を図るとともに、これと並行して、展示を支える被爆資料の収集・保存管理、原爆・平和に関する調査研究、さらには展示に関係する情報の発信などの取組について、一層の充実・強化を図っていく。
また、平和に関する博物館のネットワークづくりにおいて、平和記念資料館が国の内外の博物館に対して、中心的な役割を担っていく。
さらに、当館を訪れる来館者に対しては、平和への思いを記憶にとどめてもらうため、平和記念資料館ならではの様々な取組を展開していく。また、施設の利便性向上のための誘導サイン、各種の情報提供、トイレ、休憩場所、ミュージアムショップなどのサービス機能の充実を図る。
検討項目
- 資料・情報収集、情報発信・提供機能の充実
- 調査研究・人材育成機能の充実
- 平和に関する博物館などとの連携・交流
- 資料保存・管理のための施設整備
- 来館者サービスの向上
2 資料・情報収集、情報発信・提供機能の充実
(1) 資料・情報収集の充実
ア 現状
平和記念資料館では、被爆者が身に付けていた衣服、日用品、被爆瓦などの被爆資料や、原爆被災写真、市民が描いた原爆の絵、被爆者の証言映像、さらに、原爆や被爆に関係する文書資料や書籍などの収集に努めている。また、最近の核兵器を巡る動向等についての情報収集にも努めている。
イ 充実策
- 被爆者の高齢化に伴い、被爆資料や原爆被災写真などの散逸や廃棄が懸念されるため、被爆資料の提供を積極的に呼びかけていく。また、提供された資料については、毎年新着資料展を開催し、市民に公開する。
- 提供された被爆資料の聞き取り調査を強化して、被爆の実相に関するより多くの証言や体験などの情報を収集する。
- 国内外の研究機関や文書資料館などとの連携を図り、原爆や被爆に関係する貴重な資料の所在調査を実施する。その際、平和記念資料館で収集する資料の範囲を明確にしておく必要がある。
- 被爆者や被爆者運動などに関し、これまで報道機関が蓄積したデータについても情報を共有し、協力して資料を保存することなどに努める。
- 核兵器を巡る今日の動向や核政策に関する資料等について、国内外の研究機関との連携を通じ、より一層の情報収集に努める。
- 絶版になった原爆や被爆に関連する書籍、毎年出版される書籍などの収集に努める。
(2) 情報資料室の充実
ア 情報資料室の概要
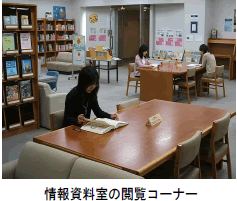
- 開室日
- 土曜日・日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日を除くすべての日
- 開室時間
- 午前8時30分~午後5時
- 蔵書数
- 54,645件(内訳は次表のとおり)
- その他の設備
- パソコン2台(平和に関するウェブサイト閲覧用)
ビデオ・DVD 視聴コーナー 1箇所 - 利用者数
- 6,099人[平成21年度(2009年度)]
原爆や平和に関する蔵書数(平成22年(2010年)3月末現在)
|
区分 |
蔵書数(件) |
|---|---|
| 総記 | 1,098件 |
| 哲学 | 527件 |
| 歴史 | 3,009件 |
| 社会科学 | 7,012件 |
| 自然科学 | 523件 |
| 技術 | 862件 |
| 産業 | 108件 |
| 芸術 | 1,231件 |
| 言語 | 100件 |
| 文学 | 6,746件 |
| 洋書 | 2,436件 |
| 雑誌 | 30,993件 |
| 合計 | 54,645件 |
イ 充実策
- 一般向けや引率教職員向けなど利用者に合わせた簡単な案内パンフレットの作成を検討する。
- 研究者向けの案内資料を作成するなど、研究サポート機能の充実を図る。
- 子ども向け書籍の充実を図る。
- 利便性の向上を図るため、現在のビデオシアター(東館1階)の場所に情報コーナーを設置する。
- 東館1階の情報コーナーや観覧後の心情に配慮した場で収集資料を検索できるようにする。
- 現在の常設展示のビデオコーナー(東館3階)の機能を取り込み、書籍等の資料と視聴覚資料の一体的な提供を図る。
- 土曜・日曜日の利用を可能にするなど開室日を拡充する。
- 平和学習などで何度でも利用してもらうことができるよう、市内の子どもたちを中心として、リピーターの増加に努める。
(3) ホームページ等の充実
ア 現状
平和記念資料館では、平成10年(1998年)6月に原爆や平和について学び、考えてもらうため、ホームページ「ヒロシマ・ピース・サイト」を開設し、情報を発信するとともに、平成11年(1999年)12月から被爆資料が閲覧できる「平和データベース」を運用している。
イ 充実策
(ア) 多言語化への対応

- より多くの海外の人が関心を寄せ、来館するように、平和記念資料館の利用案内、展示概要などの海外向けの広報を充実させるため、ホームページの多言語化を推進する。
- 「平和データベース」は、現在、日本語だけであるが、海外の人たちの利用を促進し、平和意識の高揚を図るため、英語対応について検討する。
(イ) 最新で的確な情報提供と操作性の向上
- 平和記念資料館関連ニュースの配信やデータの更新を定期的に行う。
- 画面のレイアウトの工夫や操作性の向上を図るよう改善に努める。
(ウ) ホームページによる平和学習に係る情報提供と支援

巡回展の開催状況や平和学習用資料の貸出方法、講座の開設などのお知らせを積極的に紹介し、学校や公民館などでの利用促進を図るとともに、遠隔地での被爆資料等を活用する機会の増加に努める。
(エ) 原爆に関連する情報のデータベース化

- より検索しやすくするとともに、公開データの内容の充実を図る。
- 原爆に関する研究成果などをデータベース化して紹介する。
(4) 被爆資料や被爆者証言ビデオなど所蔵資料データのデジタル化
被爆資料、被爆者証言ビデオ、写真などの資料の劣化に備えて、所蔵資料を高精細な画像でデジタル化し、活用を図る。
3 調査研究・人材育成機能の充実
(1) 調査研究機能
ア 現状
平成10年(1998年)に有識者で構成する「広島平和記念資料館資料調査研究会」(以下「資料調査研究会」という。)を設置し、原爆や平和に関して計画的・体系的な調査研究を行っている。その成果については、常設展示の更新や企画展の開催などで活用し公開するとともに、平和記念資料館の基礎的な資料として蓄積している。
さらに、平和記念資料館そのものが主体的に調査研究機能を持つ必要がある。
イ 充実策
- 調査研究機能の充実を図るため、専門的能力を有する研究員(以下「研究員」という。)の配置を検討する。
- 今後とも有識者等の協力を得ながら、資料調査研究会における原爆や平和に関する調査研究活動を推進する。
(2) 人材育成機能
ア 現状
学芸員を始めとする平和記念資料館の職員(以下「職員」という。)は、自主的に研修に参加し知識や技術の習得に努めている。
また、平和記念資料館や平和記念公園内で解説を行う「ヒロシマピースボランティア」(以下「ピース ボランティア」という。)を育成するとともに、要請に応じてインターンシップの学生や国外の良心的兵役拒否者を受け入れている。
イ 充実策
- 研究員が調査研究に専念できる環境づくりや、職員の大学への派遣研修など育成プログラムを検討する。
- 原爆被害の実相を伝え、平和のために活動する人材を育成するため、平和記念資料館でインターンシップを希望する国内外の学生等を積極的に受け入れる体制を整備する。
- ボランティア活動への市民参加の促進を図るための仕組みづくりやボランティア育成のための仕組みづくりに取り組む。
4 平和に関する博物館などとの連携・交流
(1) 日本平和博物館会議
平和記念資料館の呼びかけにより、平成6年(1994年)に、日本平和博物館会議が発足した。
会議は、博物館相互の情報交換を図るとともに、共同事業の企画・実施などにより、平和に関する博物館のネットワーク化を進めている。現在、埼玉県平和資料館、神奈川県立地球市民かながわプラザ、川崎市平和館、立命館大学国際平和ミュージアム、大阪国際平和センター(ピースおおさか)、広島平和記念資料館、長崎原爆資料館、沖縄県平和祈念資料館、ひめゆり平和祈念資料館、対馬丸記念館が加盟している。年1回会議を開催し、各館で当面の課題や関心事項について情報交換を行っている。
今後も各館の特徴を生かし、企画展の開催など具体的なレベルでの連携を探っていく。
(2) 海外の博物館

平和記念資料館では、平成20年(2008年)10月6日~10日、「第6回国際平和博物館会議」を、立命館大学国際平和ミュージアムなどと共同で開催した。海外から50施設が参加し、平和博物館の役割や意義、今後の展開などについて協議した。
今後も海外の平和博物館等への未活用の被爆資料の貸与や、巡回展などの共同事業の開催などを視野に入れた交流を深める。
国際平和博物館会議
世界の平和博物館の連携を通じて平和の実現に貢献するため、戦争の悲惨さや平和の尊さを発信する平和博物館のネットワークを構築する目的で発足。戦争や紛争といった直接的暴力に限らず、飢餓・貧困・社会的差別などの構造的暴力の克服を目指す広義の平和博物館や、これらに関連する展示を構成部分として含む民族博物館・美術館などで構成されている。平成4年(1992年)7月、イギリスのブラッドフォードで第1回会議が開催された。
(3) 大学の研究機関との連携・交流
ア 広島市立大学
広島市立大学とは、常設展示の更新や展示手法の研究などを通じて連携や交流を図っている。中でも、学術研究活動を通じて核兵器の廃絶への役割を担う広島平和研究所との結びつきが深い。今後も研究委託や相互の便宜供与、さらには共同研究などを通じて連携を深める。
イ 広島大学
広島大学の原爆放射線医科学研究所からは、放射線の被害調査について医学的な見地から協力を得ており、相互に資料の貸借や提供を行っている。また、米国国立公文書館所蔵の原爆被災写真を共同収集し、展示や調査研究に活用している。今後も、こうした取組を行い、同研究所をはじめとする機関と連携・交流を深める。
ウ 「広島・長崎講座」開設大学
広島市では、被爆体験を学問的なレベルで若い世代に継承するため、国内外の大学に「広島・長崎講座」の開設を呼びかけ、平成22年(2010年)4月末までに、国内29、海外15の大学で開設され、その拡大に取り組んでいる。平和記念資料館では、これらの大学に対し、教材提供の支援などを行い、連携・交流を深める。
(4) 追悼平和祈念館との連携
追悼平和祈念館は、原爆死没者の氏名と遺影の登録及び被爆体験記、手記などの収集や被爆体験記朗読会の開催を通じて、原爆死没者の尊い犠牲を銘記し追悼の意を表すとともに、被爆体験を継承・伝承し、平和について考える場となっている。平和記念資料館と追悼平和祈念館とは、機能を補完し合いながら、それぞれの特徴を生かした連携を深める。
また、来館者が平和記念資料館と追悼平和祈念館の両館を観覧することにより、平和の尊さについて、より深く理解し思索してもらうため、平和記念資料館から追悼平和祈念館への観覧ルートの案内方法等についても検討する。
(5) 平和に関する博物館のジャンルを超えた交流
平和に関する博物館に限らず、美術館や各分野の博物館との連携・交流の可能性を探り、広く平和意識の高揚に努める。
また、将来的には、原爆文学館の設置や原爆・平和をテーマとした音楽・美術作品の収集・保存の可能性について、他館と連携しながら研究する。
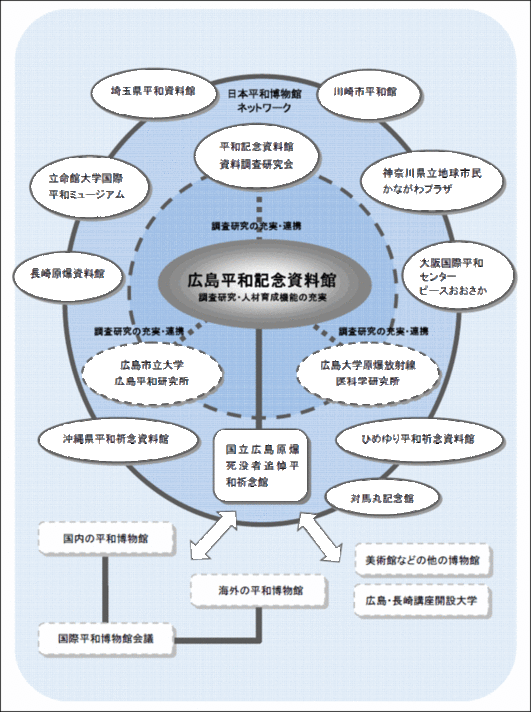
5 資料保存・管理のための施設整備
(1) 現状
ア 収蔵資料の状況
平和記念資料館では、平成6年(1994年)、東館の開館時に温湿度管理が可能な収蔵庫を新設し、資料を保存する体制を整えている。今後とも、引き続き良好な保存環境を保つとともに、受入資料の増加に対応できるよう、資料の適切な保存のための整備を行う必要がある。
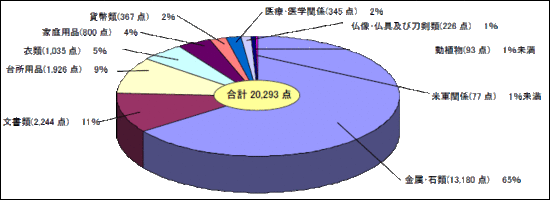
被爆資料の近年の寄贈状況〔平成22年(2010年)3月末現在〕
|
年度 |
件数 |
点数 |
|---|---|---|
| 平成15年度(2003年度) | 93件 | 481点 |
| 平成16年度(2004年度) | 137件 | 826点 |
| 平成17年度(2005年度) | 109件 | 421点 |
| 平成18年度(2006年度) | 65件 | 254点 |
| 平成19年度(2007年度) | 81件 | 822点 |
| 平成20年度(2008年度) | 67件 | 714点 |
| 平成21年度(2009年度) | 57件 | 589点 |
※寄贈写真等も含む。
被災写真の収蔵状況〔平成22年(2010年)3月末現在〕
|
区分 |
点数 |
|---|---|
| データベース登録済(公開) | 753 |
| データベース登録済(非公開) | 3,772 |
| データベース登録作業中調査中 | 約6,000 |
市民が描いた原爆の絵の収蔵状況〔平成22年(2010年)3月末現在〕
|
区分 |
点数 |
|---|---|
| 昭和49年(1974年)~昭和50年(1975年)収集キャンペーン | 2,306点 |
| 平成14年(2002年)収集キャンペーン | 1,419点 |
| 上記以外で収集した絵 | 444点 |
| 戦前の広島の絵 | 795点 |
| 合計 | 4,964点 |
イ 収蔵施設の状況
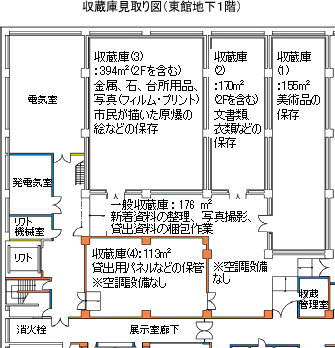
現在、被爆資料は、東館地下1階の4つの収蔵庫のうち温湿度管理が可能な3つの収蔵庫(収蔵庫(1)~(3))に分散させて保管しているが、いずれも満床に近い状況となっている。
また、4つの収蔵庫とは別に一般収蔵庫を設置し、新着資料の一時保管と整理、貸出資料の梱包作業、写真撮影などに使用しているが、空調設備がなく、資料の保管や作業場所としては好ましい環境にない。
さらに、東館地下1階収蔵庫から東館3階の展示室などへの資料の搬入・搬出ルートに大型リフト等がないため、展示替え等を行う場合の作業効率も悪い。



(2) 今後のあり方
ア 収蔵スペースの確保
- 寄贈資料が年々増加していることから、収蔵庫(4)を2階層に改修することなどによる収蔵面積の拡大を検討するとともに、温湿度管理が可能な空調設備の整った収蔵庫として整備する必要がある。
- 写真ネガフィルムについては、温湿度管理が可能な専用の保管庫で保存しているが、収蔵資料の増加に伴い保管庫を増設する必要がある。
イ 一般収蔵庫の整備
- 一般収蔵庫は、新着資料の受入・整理などの作業を円滑に行い、資料を適切に管理できるよう、空調設備を整備する必要がある。
- 写真撮影用の照明や機材・消耗品を適切に保管できるよう、専用の撮影ブースを整備する必要がある。
- 害虫を防除し、収蔵庫全体の良好な環境を維持できるよう、一般収蔵庫の入退室管理を厳格に行う。
ウ 収蔵庫・展示室間の搬入・搬出手段の整備
展示替え等を円滑に行うため、東館地下1階収蔵庫から展示室への資料の搬入・搬出ルートへの大型リフト等の整備を検討する。
エ 資料の適切な保存・管理
資料を適切に保存・管理していくため、長期的な収集の見込みを立て、それに対応した保存計画を策定する。
オ 新たな収蔵場所の確保
- 近い将来、館内の収蔵スペースが満床になることを想定し、館外への収蔵スペースの確保についても検討する必要がある。新たな収蔵施設を建設することも考えられるが、他の博物館では、温湿度管理を必要としない資料については、公共の未利用施設を活用している事例などもある。
- 収蔵庫の公開など、収蔵している資料をそのままの状況で観覧できるような機会を設けることについても検討する。
6 来館者サービスの向上
平和記念資料館を利用しやすい施設にするため、展示以外についても、ハード・ソフト両面でのサービスの向上を図る必要がある。具体的には、ミュージアムショップ、案内表示、エスカレーター、トイレ、休憩場所などについて、利便性向上のための整備を図る。また、平和記念資料館ならではの事業展開や開館時間の延長などについても、利用者ニーズを踏まえながら検討していく。
(1) ミュージアムショップの充実
ア 現状と課題
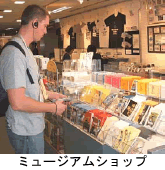
ミュージアムショップは、平和記念資料館で被爆の実相に触れたことを記憶にとどめ、観覧後も引き続き平和への思いを深めてもらうため、関係書籍や記念品などを提供する場として設置されている。
(ア) 場所
現在、東館3階ロビーの休憩場所に併設され、この後に本館の展示が続くため、時間をかけて購入することが難しく、ミュージアムショップだけを目的に来館する利用者にとって不便である。また、スペースが狭いため、ゆっくりと書籍などを手に取って見ることが難しく、レイアウトや壁面ディスプレイの拡充も困難である。
(イ) 利用状況
平成21年度(2009年度)の年間利用者数は56,689人、1日当たりの平均利用者数は157人で、8月6日、お盆時期を含む8月が特に利用者が多く、12月~2月は利用者が少ない。平成21年度(2009年度)の入館者数は1,400,543人であり、ミュージアムショップの利用率は入館者の4%である。
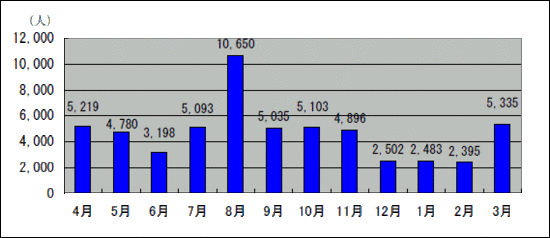
(ウ) 取扱品目
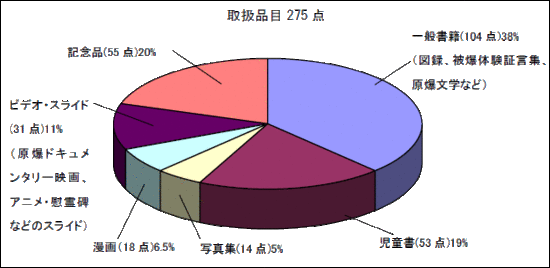
|
順位 |
商品名 |
販売単価(円) |
売上数(冊・個・枚) |
|---|---|---|---|
| 1 | あるいてみよう広島のまち(児童書) | 180円 | 13,250冊 |
| 2 | ミニタオル(記念品) | 350円 | 9,234個 |
| 3 | 平和記念資料館図録「ヒロシマを世界に」 | 1,000円 | 5,020冊 |
| 4 | メダルキーホルダー(記念品) | 450円 | 4,878個 |
| 5 | ピースポストカード(記念品) | 50円 | 4,665枚 |
| 6 | キーホルダー3種(記念品) | 450円 | 3,533個 |
| 7 | メダル(記念品) | 500円 | 2,610個 |
| 8 | 被爆写真集 ヒロシマ(写真集) | 380円 | 2,320冊 |
| 9 | 根付け 折鶴(記念品) | 400円 | 2,272枚 |
| 10 | 一筆箋(記念品) | 300円 | 2,227冊 |
イ 充実策
- ミュージアムショップを東館1階の展示室出口付近の無料空間へ移設する。
- 購入した書籍やはがき、折り紙などを館内で利用しやすいよう、観覧後の心情に配慮した場との連携を意識した配置とする。
- スペースを十分に確保し、書籍などを手に取って見ることができる陳列形態とする。また、壁面ディスプレイなどの充実を図る。
- 原爆・平和関係の専門書籍の充実を図るなど、展示との一体性や結び付きを深める。
- 学校や公民館などで活用できる平和学習用の教材の開発などについても検討する。
- 平和への願いを受け渡しできるような幅広いオリジナル商品(ピースグッズ)の研究・開発を検討する。
- ホームページなどで取扱品目や購入方法などをより分かりやすく紹介し、通信販売による利用の促進を図る。
- 英会話のできる販売員の配置や接客研修の導入など、国内外からの来館者への利便性の向上を図る。
- 専門業者の導入など適切な運営形態についても検討する。
- 折り鶴の折り方の解説が付いた折り紙のような商品を開発し、平和記念資料館ならではのユニークさを出していく。
ミュージアムショップのオリジナルグッズ


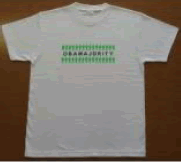
(2) その他
ア 平和記念資料館ならではの事業展開
当館を訪れる来館者に対して、平和への思いを記憶にとどめてもらうため、展示だけではなく、被爆者やピース ボランティアとの交流、市内の被爆建造物や平和記念公園内の慰霊碑巡りの紹介など、平和記念資料館ならではの様々な取組を展開していく。
イ 昼食会場の確保
修学旅行を中心とした団体利用者の雨天時等の昼食会場については、東館のメモリアルホール、会議室(1)・(2)、ビデオシアターの空き状況を見ながら提供している。さらに、昼食利用が可能な平和記念資料館周辺施設の紹介などの対応も行っている。今後とも、団体利用者へのサービスの向上を図るため、昼食会場の確保に努める。
ウ 案内表示の見直し
- 案内板の設置場所、サイズや色などの規格について、観覧動線と諸室配置の見直しなどと併せて検討し、来館者に分かりやすい案内表示とする。
- 来館者が目的や滞在時間に合わせて観覧できるよう、東館1階のエントランスロビー付近にガイダンスコーナーを設置して、展示の構成、観覧の動線、観覧所要時間などの案内表示を充実させる。
エ エスカレーター、トイレ、休憩用イス等の整備
観覧動線と諸室配置の見直しなどと併せて、主たる観覧動線上にエスカレーターを設置するとともに、利用しやすいトイレや休憩用イスの配置等について検討し、ユニバーサルデザインに配慮した整備を行う。
オ 休憩施設の充実
現在は、東館1 階にお土産の販売や、軽食などを提供する売店を設置している。平和記念公園の散策や平和記念資料館の観覧の前後で、休憩したり、飲食ができる空間の充実について検討する。
カ 展示室内のメンテナンスの充実
現在、平和記念資料館内の資料の展示状況の確認やパネル、模型などの清掃を定期的に行っている。引き続き、来館者の方が気持ちよく観覧できる環境の整備に努める。
キ 開館時間の延長等
開館時間については、これまで利用者のニーズに合わせて、夏休み期間中の8月(19時閉館)及び繁忙期である3月から11月まで(18時閉館)の閉館時刻の繰下げ、年間を通した開館時刻の繰上げ(8時30分開館)などの変更を行ってきた。今後とも、修学旅行生など利用者への利便性の向上を図るため、開館時間の延長について検討していく。
ク 施設の名称
施設の名称は現在、条例により広島平和記念資料館となっているが、名称からは展示内容のイメージがつかみにくい、広島として責任を持って展示すべき内容は原爆に関連したものであることなどから、原爆という言葉を使用すべきとの意見もある。また、「原爆資料館」が通称として広く市民に浸透していること、海外においても「A-BOMB MUSEUM」と呼ばれることがあることなどから、施設名称のあり方については、今後、さらに様々な意見を踏まえて議論していく必要がある。
ケ 観覧料
広島平和記念資料館条例により観覧料は、現在大人50円、小人30円と定められている。
昭和47年(1972年)の料金改定から38年が経過しており、この計画の策定と合わせて、これからの観覧料のあり方について、館内でアンケート調査を実施した。調査の結果、現状維持あるいは無料化を望む回答と、値上げを望む回答がほぼ拮抗した。また、値上げを望む回答では、100円相当とする意見が最も多く、300円、500円という意見がこれに続いた。このような結果を踏まえて、館の無料開放などの試行的な取組みなども行いながら、さらに論議していく必要がある。
ダウンロード
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民局国際平和推進部 平和推進課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2898(代表) ファクス:082-504-2986
[email protected]
