広島市の自主防災組織
1.自主防災組織とは?

自主防災組織は、昭和34年の伊勢湾台風による甚大な被害を教訓として「災害対策基本法」が制定され、この法律によって生まれた隣保協同の精神に基づく地域住民による自発的な防災組織です。
地震等の大規模災害が発生した場合、行政をはじめとする防災関係機関は災害対応に全力を尽くしますが、同時期に多発する災害に十分な対応できない可能性があります。
このような状況では、地域に住む方々が自ら行う「初期消火、負傷者の救出・救護活動」などの自主的な救出活動が、被害の軽減のために必要となります。
自主防災組織は、地域の安全を確保するため、住民の一人ひとりが「自分たちのまちは自分たちで守る」という固い信念と連帯意識のもとに、既設の町内会・自治会またはこれらの連合会を主体として組織されるものです。自主防災組織の活動が活発になると、地域の防災力が向上するだけでなく、コミュニティの活性化にも繋がります。
2.広島市自主防災組織の設立状況
広島市では昭和60年ごろから、町内会・自治会単位を基本とし、自主防災組織が設立され、現在では、市内全域に自主防災組織が設立されています。また、各自主防災組織が集まった、小学校区単位、区単位、市単位の連合自主防災組織も設立されています。
3.自主防災組織の構成と各班の役割

自主防災組織の活動は、各班別に役割を決めていますが、活動内容は、各班別に役割分担を行い、地域の特性を踏まえ、多様な活動に取り組んでいます。あらかじめ、住民の方々で話しあっておき、誰がどういった活動をするのか、役割分担を行っています。
自主防災組織の編成は、会長、副会長をリーダーとして、その下に、避難誘導班、救出救護班、情報広報班、給食給水班などの班が設置され、各班には責任者として班長が置かれています。また、会長、副会長、各班の班長で本部を構成し、自主防災組織の総括や各班の運営指導、訓練の計画・実施等を行っています。
各班の活動(例)
|
区分 |
平常時の活動 |
災害時の活動 |
|---|---|---|
|
本部 (会長・副会長) |
|
|
| 避難誘導班 | 避難計画の作成 |
|
| 救出救護班 |
|
|
| 情報広報班 | 防災知識の普及啓発 |
|
| 給食給水班 | 非常持ち出し品、家庭内備蓄の広報 | 水・食料・生活必需品の調達・配付 |
| 施設管理班 | 防災備蓄倉庫の管理 |
|
4.自主防災組織の活動について
自主防災組織では、次のような活動に取り組まれ、地域の防災活動に貢献されています。
(1) 防災知識の普及


各自主防災組織での懇談会、防災に関する講習会・講演会の開催や、AED使用体験や非常食の試食等の体験を通し、防災に関する知識を習得する防災フェア等を自主防災組織が主体となり、開催しています。
(2) 防災訓練の実施


災害による被害を最小限にするには、発災直後における地域住民による自主的かつ組織的な防災活動が重要になります。
このため、救出・救護活動に使用する資機材や初期消火に必要な資器材を活用した実践的な訓練を自主防災組織が主体となり、開催しています。
また、地域の消防団が自主防災組織主催の訓練に積極的に参加し、訓練指導等を行うことで、両者の連携を強化し、更なる防災対応能力の向上に努めています。
(3) リーダーの養成
自主防災組織が活発な活動を行うためには、行動力のあるリーダーの存在が必要不可欠です。
このため、広島市総合防災センターでリーダー研修を実施したり、広島市が発行する「たちまち防災」を活用し、自主防災組織のリーダー養成を行っています。
(4) 指定避難所運営マニュアル検証訓練の実施

指定避難所とは、大規模災害時の臨時的な宿泊・滞在の場所となる避難場所で、避難された方々による協力や連携が円滑に図られるよう、日常的な生活圏である小学校区を基本単位としています。
自主防災組織では、大規模災害時に生活の場を失った被災者の方の生活が地域住民の主体により円滑に行えるよう、平常時において、班編成と各班の任務内容をあらかじめ定めておく指定避難所運営マニュアルの作成に努められています。
そして、策定された指定避難所運営マニュアルの検証訓練を実施することで、必要な見直しに取り組まれています。
5.広島市防災普及啓発ハンドブック「たちまち防災」について
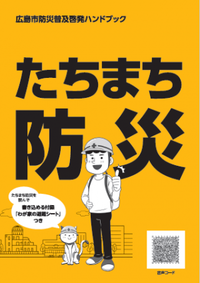
防災ハンドブック「たちまち防災」は、「たちまち」ここが知りたい!と思う防災情報が満載です。
第3章では「地域の備え 自主防災組織」として自主防災組織の活動について記載しています。地域で活動される際の参考としてお役立てください!
このページに関するお問い合わせ
危機管理室 災害予防課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2664(代表) ファクス:082-504-2802
[email protected]
