恵下埋立地(仮称)整備事業に係る環境影響評価書 要約書(その3)
印刷する場合はページ下のダウンロードファイルをご利用ください。
第11章 調査結果の概要並びに予測及び評価の結果 1 大気質
1.1 現況調査結果
大気質の調査は,図1-1に示すとおり,工事用車両及び廃棄物搬入車両等が通過する経路の沿道(以下,「走行ルート沿道」という。)の4地点において,二酸化硫黄(SO2),一酸化炭素(CO),浮遊粒子状物質(SPM),光化学オキシダント,二酸化窒素(NO2),非メタン炭化水素及び気象(夏季・冬季,各7日間)の調査を実施しました。
さらに,平成21年(2009年)9月に環境基準に追加された微小粒子状物質(PM2.5)の調査を冬季と夏季の2回実施しました。
調査地点は,走行ルートを交通条件の違いにより4区分に分割し,各区間の代表地点を選定しました。
代表地点は,沿道住民の生活環境に対する影響を把握するため,沿道に保全すべき対象となる住居等が存在する地点を選定しました。
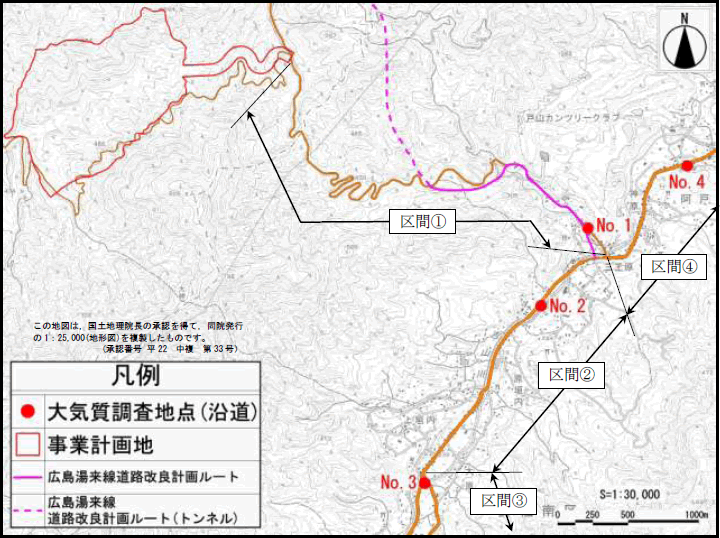
大気質の調査結果は,表1-1に示すとおりです。
二酸化硫黄,一酸化炭素,浮遊粒子状物質,二酸化窒素,微小粒子状物質は,調査期間内のすべての地点において,環境基準値を下回りました。
光化学オキシダントについては,夏季に3地点(No.1,2,3)で,環境基準値を超過しました。なお,周辺の一般大気測定局においても環境基準値の超過が確認されています。
非メタン炭化水素は,調査期間内のすべての地点において,夏季または冬季に光化学オキシダント生成防止のための濃度レベルの指針値を上回りました。
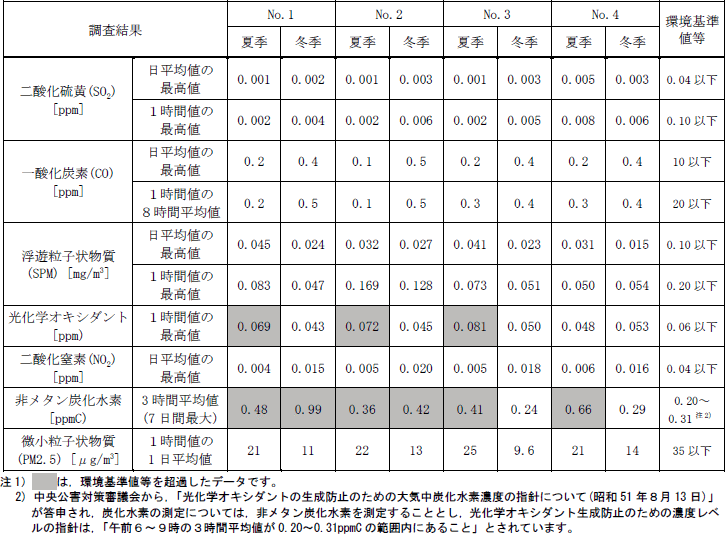

また,図1-2に示す事業計画地内の1地点において,ベンゼン,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,粉じん(夏季・冬季,各1日間)及びダイオキシン類(夏季・冬季,各7日間)の調査を実施しました。なお,事業計画地における気象については年間の状況を把握するため,1年間の継続調査を実施しました。
調査結果は,各項目いずれも環境基準値を下回りました。
粉じんについては,夏季が46μg/m3,冬季が13μg/m3でした。(粉じんについては,環境基準等の比較すべき基準はありません。)
1.2 予測・評価
大気質の予測手法の概要は,表1-2に示すとおりです。
|
内容 |
予測事項 |
予測方法 |
予測地域 |
予測時期 |
|---|---|---|---|---|
|
建設機械の稼動 |
粉じん等 | 気象データの解析等による定性予測 | 事業計画地及びその周辺 | 工事の実施による影響が最大となる時期 |
|
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 |
二酸化窒素 (NO2) 浮遊粒子状物 質(SPM) |
道路環境影響評価の技術手法,2007改訂版,財団法人道路環境研究所に示されるプルーム・パフモデル | 走行ルート沿道4地点 | 工事の実施による影響が最大となる時期 |
|
内容 |
予測事項 |
予測方法 |
予測地域 |
予測時期 |
|---|---|---|---|---|
|
廃棄物の埋立て |
粉じん等 | 気象データの解析等による定性予測 | 事業計画地及びその周辺 | 埋立期間中 |
|
廃棄物の搬入 |
二酸化窒素 (NO2) 浮遊粒子状物 質(SPM) |
道路環境影響評価の技術手法,2007改訂版,財団法人道路環境研究所に示されるプルーム・パフモデル | 走行ルート沿道4地点 | 埋立期間中 |
(1) 工事の実施
ア 粉じん等
予測結果
建設機械の稼動による粉じんの発生・飛散については,気象データの解析等による定性的な予測を行いました。現地調査結果による気象の状況を1時間値の最大風速について整理すると,図1-3のとおりとなります。
事業計画地において,砂ぼこりが立つ程度の風速である5.5m/s以上の風速が出現するのは,季節ごとに5~14%,通年で8%程度となりました(表1-3参照)。
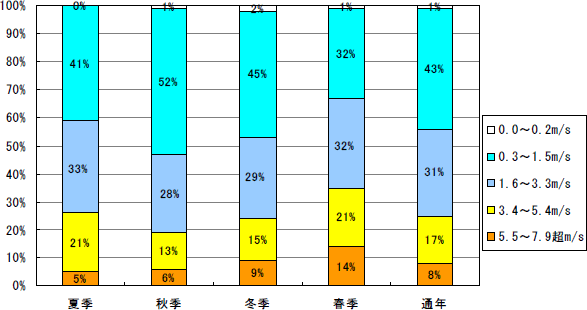
|
階級 |
地上10mの風速(m/s) |
名称 |
陸上の状態 |
|---|---|---|---|
|
0 |
0.0m/s~0.2m/s |
静穏 |
静穏,煙はまっすぐに昇る。 |
|
1 |
0.3m/s~1.5m/s |
しけいふう |
風向は,煙がなびくのでわかるが風見には感じない。 |
|
2 |
1.6m/s~3.3m/s |
軽風 |
顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動き出す。 |
|
3 |
3.4m/s~5.4m/s |
軟風 |
木の葉や細い小枝がたえず動く。軽い旗が開く。 |
|
4 |
5.5m/s~7.9m/s |
和風 |
砂ぼこりが立ち,紙片が舞い上がる。小枝が動く。 |
出典「環境アセスメントの技術」(1999年,(社)環境情報科学センター)
環境保全措置
予測結果では,建設機械の稼動に伴い粉じんが飛散する頻度は年間8%程度でしたが,この影響を回避又は低減することを目的として,表1-4に示す環境保全措置を実施します。
|
環境保全措置 |
環境保全措置の効果 |
|---|---|
| 工事工程の調整 | 建設機械の集中稼働を避けることにより,粉じん等の発生が抑制されます。 |
| 強風時の作業の一時中断又は中止 | 強風時には粉じんの発生を伴う作業を一時中断又は中止することにより,粉じん等の発生が抑制されます。 |
| 施工エリアの分割 | 広域な掘削エリアを出現させないように施工エリアを分割して,裸地の発生を抑えることにより,粉じん等の発生が抑制されます。 |
| 工事場所等への散水 | 散水を行うことにより,工事施工ヤードや工事用道路からの粉じん等の発生が抑制されます。 |
| 工事車両の洗浄 | 施工区域外に退出する場所に洗車設備を設け,工事車両のタイヤ等を洗浄することにより,粉じん等の発生が抑制されます。 |
| 法面の保護 | 法面をシートあるいは法覆工で早期に養生することにより,粉じん等の発生が抑制されます。 |
評価
回避又は低減に係る評価
本事業の実施にあたっては,環境保全措置を実施し,建設機械の稼動に伴う粉じん等の発生を低減する計画としており,大気環境への粉じん等の影響を回避又は低減した計画であると評価します。
イ 二酸化窒素(NO2)・浮遊粒子状物質(SPM)
予測結果
資材及び機械の運搬に用いる車両等の運行に伴い排出される大気汚染物質の影響を把握するため,二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)について,年間の平均的な濃度を予測しました。
走行ルート沿道における予測対象交通量は,表1-5のとおりです。
予測時期は,工事関係車両台数(第1期工事)が最大となる時期(平成27年(2015年))としました。
一般車両は,現況交通量(平成21年(2009年))の調査結果)に対して,将来(平成27年(2015年))の交通量の伸び率(=小型車・大型車いずれも0.99)が,概ね同程度であると考え,現況と同じ台数で設定しました。
工事関係車両は,事業計画に基づき1日当りの使用台数が最大となる時期の台数(小型車=往復約60台/日),大型車=往復約120台/日)としました。
|
|
小型車両 |
大型車両 |
合計 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 413台 | 11台 | 424台 |
| No.2 | 2,598台 | 193台 | 2,791台 |
| No.3 | 1,248台 | 139台 | 1,387台 |
| No.4 | 2,948台 | 232台 | 3,180台 |
|
|
一般車両 |
一般車両 |
一般車両 |
工事関係車両 |
工事関係車両 |
工事関係車両 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No.1 |
413台 |
11台 |
424台 |
60台 |
120台 |
180台 |
604台 |
|
No.2 |
2,598台 |
193台 |
2,791台 |
60台 |
120台 |
180台 |
2,971台 |
|
No.3 |
1,248台 |
139台 |
1,387台 |
60台 |
120台 |
180台 |
1,567台 |
|
No.4 |
2,948台 |
232台 |
3,180台 |
60台 |
120台 |
180台 |
3,360台 |
計算の結果,各予測地点での二酸化窒素(NO2)の予測濃度(日平均値の年間98%値)は,図1-4のとおり,No.1地点で0.01346ppm,No.2地点で0.01549ppm,No.3地点で0.01515ppm,No.4地点で0.01862ppmと予測されました。
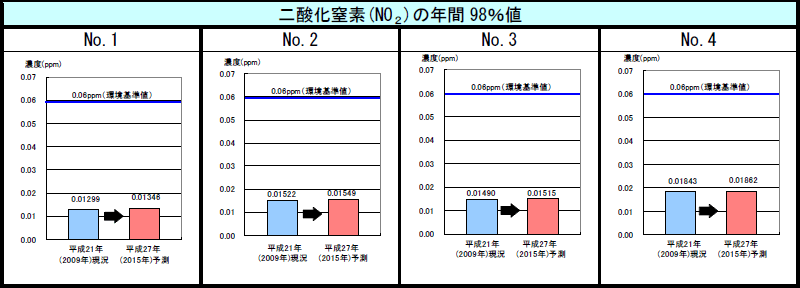
各予測地点での浮遊粒子状物質(SPM)の予測濃度(日平均値の年間2%除外値)は,図1-5のとおり,No.1地点で0.05690mg/m3,No.2地点で0.05251mg/m3,No.3地点で0.05026mg/m3,No.4地点で0.04585mg/m3と予測されました。
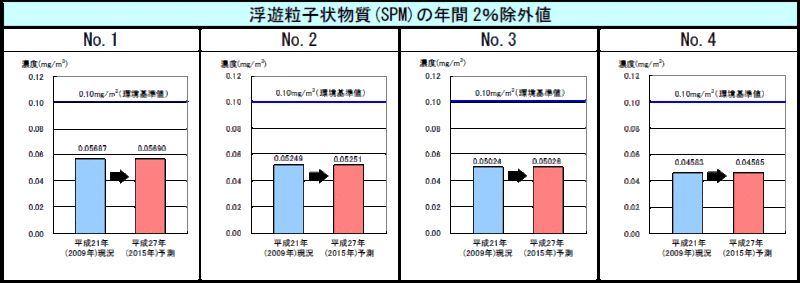
環境保全措置
予測結果では,工事関係車両の走行に伴う二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の濃度の増加は,各予測地点とも少ないものでしたが,沿道の環境への影響を回避又は低減することを目的として,表1-6に示す環境保全措置を実施します。
|
環境保全措置 |
環境保全措置の効果 |
|---|---|
| 工事関係車両の運転管理の徹底 | 工事関係車両の定期的な点検整備の実施,法定速度の遵守,高負荷運転及び空ぶかし・急発進運転の回避等を徹底することにより,二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の発生が抑制されます。 |
| 低公害車・低排出ガス車等の積極的な導入 | 最新の技術動向を踏まえ,低公害車,低排出ガス車等の積極的な導入により,二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の発生が抑制されます。 |
| 工事関係者の乗合い通勤 | 工事関係者が乗合いで通勤することにより,工事関係車両(小型車)の台数が減少し,二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の発生が抑制されます。 |
評価
回避又は低減に係る評価
本事業の実施にあたっては,環境保全措置を実施し,工事関係車両の走行に伴う二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の発生を低減する計画としており,走行ルート沿道の大気環境への影響を回避又は低減した計画であると評価します。
基準又は目標との整合性の検討
図1-4,図1-5のとおり,各予測地点における二酸化窒素(NO2)の日平均値の年間98%値,及び浮遊粒子状物質(SPM)の日平均値の年間2%除外値は,いずれも環境基準を満たしており,基準又は目標との整合は図られていると評価します。
(2) 存在・供用
ア 粉じん等
予測結果
廃棄物の埋立作業による粉じんの発生・飛散については,気象データの解析等による定性的な予測を行いました。
現地調査結果による気象の状況を1時間値の最大風速について整理すると図1-3のとおりとなります。
事業計画地において,砂ぼこりが立つ程度の風速である5.5m/s以上の風速が出現するのは,季節ごとに5~14%,通年で8%程度となりました。
環境保全措置
予測結果より,埋立作業中に粉じんが飛散する頻度は年間で8%程度となりましたが,環境への影響を回避又は低減することを目的として,表1-7に示す環境保全措置を実施します。
|
環境保全措置 |
環境保全措置の効果 |
|---|---|
| 強風時の作業の一時中断又は中止 | 強風時には粉じんの発生が伴う作業を一時中断又は中止することにより,粉じん等の発生が抑制されます。 |
| 埋立区域内等への散水 | 必要に応じて,散水を行うことにより埋立区域内等からの粉じん等の発生が抑制されます。 |
| 飛散防止用のフェンスの設置 | 埋立地の外周部に飛散防止用のフェンスを設置することにより,粉じん等の飛散が抑制されます。 |
| 廃棄物のダンピング時の散水 | 廃棄物を荷台からダンピングする時に散水することにより,粉じん等の発生が抑制されます。 |
| 廃棄物搬入車両の洗浄 | 埋立区域外に退出する時にタイヤ等を洗浄することにより,粉じん等の発生が抑制されます。 |
評価
本事業の実施にあたっては,環境保全措置を実施し,埋立機械の稼動に伴う粉じん等の発生を低減する計画としており,大気環境への粉じん等の影響を回避又は低減した計画であると評価します。
イ 二酸化窒素(NO2)・浮遊粒子状物質(SPM)
予測結果
廃棄物の搬入に伴い排出される大気汚染物質の影響を把握するため,二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)について,年間の平均的な濃度を予測しました。
走行ルート沿道における予測対象交通量は,表1-8のとおりです。
予測時期は,廃棄物搬入車両等と工事関係車両(第2期工事)の合計車両台数が最大となる時期(平成37年(2025年))としました。
一般車両交通量の推計は以下のとおりとしました。
No.1地点については,現在1車線道路ですが,存在・供用時に2車線道路に拡幅される計画です。2車線拡幅後の将来交通量については,「(主)広島湯来線の交通需要予測結果(平成10年度業務成果)」による,一般車両計画交通量(平成32年(2020年)推計交通量)5,000台/日を採用しました。
No.2~4地点については,平成21年(2009年)から平成37年(2025年)の一般車両の伸び率は,小型車0.979,大型車0.973であり,概ね同程度の交通量で推移するものと考えられるため,現況と同じ台数で設定しました。
廃棄物搬入車両(大型車)の走行台数は,日平均約50台を想定していますが,平成20年度(2008年度)の玖谷埋立地搬入車両台数実績における日平均台数と日最大台数の比(日最大台数/日平均台数=1.5)から,日最大約75台と設定し予測しました。
通勤車両台数(小型車)の走行台数は,玖谷埋立地の事例を踏まえて,約15台/日(往復約30台/日)と設定し予測しました。
工事関係車両(第2期工事)は,事業計画に基づき1日当りの使用台数が最大となる時期の台数(小型車=往復約40(台/日),大型車=往復約60(台/日))を設定しました。
|
|
小型車両 |
大型車両 |
計 |
|---|---|---|---|
| No.1 |
413台 |
11台 |
424台 |
| No.2 |
2,598台 |
193台 |
2,791台 |
| No.3 |
1,248台 |
139台 |
1,387台 |
| No.4 |
2,948台 |
232台 |
3,180台 |
|
一般車両 |
一般車両 |
一般車両 |
廃棄物搬入車両 |
廃棄物搬入車両 |
廃棄物搬入車両 |
第2期工事関係車両 |
第2期工事関係車両 |
第2期工事関係車両 |
合計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No.1 |
4,620台 |
380台 |
5,000台 |
30台 |
150台 |
180台 |
40台 |
60台 |
100台 |
5,280台 |
|
No.2 |
2,598台 |
193台 |
2,791台 |
30台 |
150台 |
180台 |
40台 |
60台 |
100台 |
3,071台 |
|
No.3 |
1,248台 |
139台 |
1,387台 |
30台 |
150台 |
180台 |
40台 |
60台 |
100台 |
1,667台 |
|
No.4 |
2,948台 |
232台 |
3,180台 |
30台 |
150台 |
180台 |
40台 |
60台 |
100台 |
3,460台 |
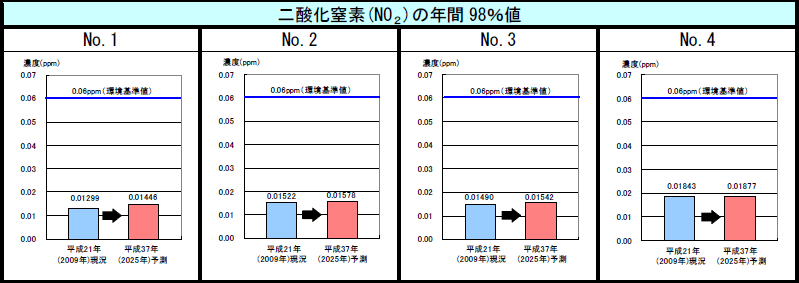
浮遊粒子状物質(SPM)の予測濃度(日平均値の年間2%除外値)は図1-7のとおり,No.1地点で0.05699mg/m3,No.2地点で0.05254mg/m3,No.3地点で0.05029mg/m3,No.4地点で0.04587mg/m3と予測されました。
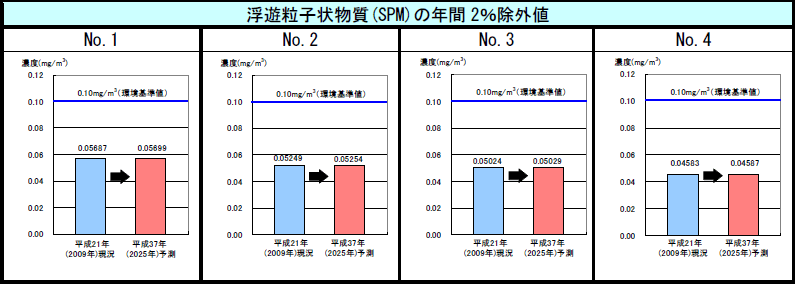
環境保全措置
予測結果では,廃棄物搬入車両の走行に伴う二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の濃度の増加は,いずれの予測地点でも少ないものでしたが,沿道環境への影響を回避又は低減することを目的として,表1-9に示す環境保全措置を実施します。
|
環境保全措置 |
環境保全措置の効果 |
|---|---|
| 廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の運転管理の徹底 | 廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の定期的な点検整備の実施,法定速度の遵守,空ぶかし・急発進運転の回避等を徹底することにより,二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の発生が抑制されます。 |
| 覆土運搬車両の搬入・搬出の軽減 | 埋立中の覆土は,基本的に事業計画地外からの覆土搬入車両の搬入・搬出を行わないことにより,覆土搬入車両の走行距離が減少し,二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の発生が抑制されます。 |
| 低公害車・低排出ガス車等の積極的な導入 | 最新の技術動向を踏まえ,低公害車,低排出ガス車等の積極的に採用することにより,二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の発生が抑制されます。 |
評価
回避又は低減に係る評価
本事業の実施にあたっては,環境保全措置を実施し,廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の走行に伴う二酸化窒素(NO2)及び浮遊粒子状物質(SPM)の発生を低減する計画としており,走行ルート沿道の大気質への影響を回避又は低減した計画であると評価します。
基準又は目標との整合性の検討
図1-6,図1-7のとおり,各予測地点における二酸化窒素(NO2)の日平均値の年間98%値,及び浮遊粒子状物質(SPM)の日平均値の年間2%除外値は,いずれも環境基準を満たしており,基準または目標との整合は図られていると評価します。
第11章 調査結果の概要並びに予測及び評価の結果 2 騒音
2.1 現況調査結果
工事関係車両及び廃棄物搬入車両等が通過する走行ルート沿道における道路交通騒音等の調査を実施しました。(調査地点は,大気質と同様の4地点。)
道路交通騒音の調査結果は,図2-1に示すとおりです。
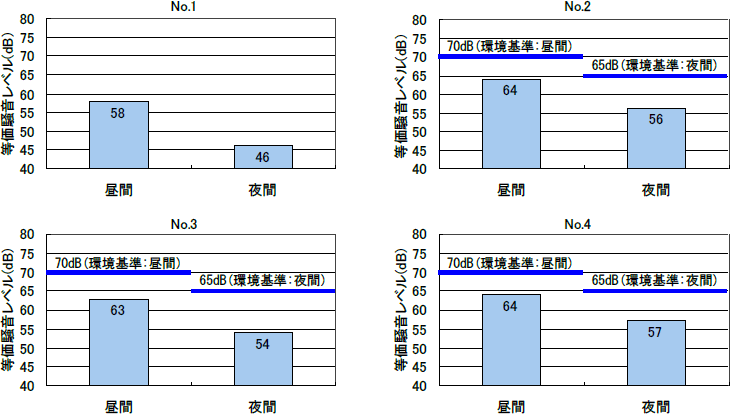
- 注1)昼間は6時~22時(16時間),夜間は22時~翌朝6時(8時間)です。
- 注2)環境基準(No.2~4地点)は,幹線交通を担う道路に近接する空間の基準です。
「等価騒音レベル」とは
時間とともに変動する騒音(非定常音)について,一定期間の平均的な騒音の程度を表す指標のひとつです。
下の図は,一般的に言われている騒音レベルの目安です。
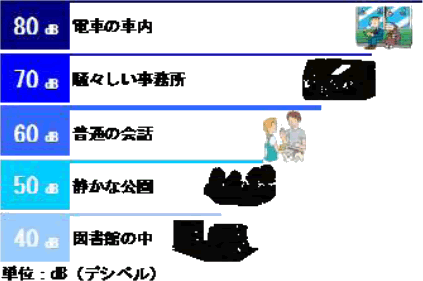
| 地点 |
交通量(台/日) 小型 |
交通量(台/日) 大型 |
交通量(台/日) 計 |
平均走行速度(km/h) |
|---|---|---|---|---|
|
No.1 |
413台/日 |
11台/日 |
424台/日 |
44km/h |
|
No.2 |
2,598台/日 |
193台/日 |
2,791台/日 |
52km/h |
|
No.3 |
1,248台/日 |
139台/日 |
1,387台/日 |
49km/h |
|
No.4 |
2,948台/日 |
232台/日 |
3,180台/日 |
47km/h |
交通量及び平均走行速度の調査結果は,表2-1に示すとおりです。
交通量は,No.4地点が最も多く3,180台/日であり,平均走行速度は,No.2地点が52km/hと最も速くなっていました。
また,事業計画地内1地点(大気質の図1-2と同じ地点)における環境騒音の調査を実施しました。
環境騒音の調査結果は,図2-2に示すとおりです。
環境騒音は,各時間帯(昼間,夜間)において,39dBでした。
- 注1)昼間は6時~22時(16時間),夜間は22時~翌朝6時(8時間)です。
- 注2)環境基準は,一般地域の基準(B地域)です。
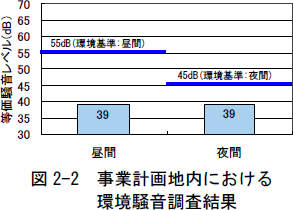
2.2 予測・評価
騒音の予測手法の概要は,表2-2に示すとおりです。
|
内容 |
予測事項 |
予測方法 |
予測地域 |
予測時期 |
|---|---|---|---|---|
|
【工事の実施】 建設機械の稼動 |
建設作業騒音 | 音の伝搬理論式に基づく距離減衰式 | 事業計画地及びその周辺 | 工事の実施に伴う影響が最大になる時期 |
|
【工事の実施】 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 |
道路交通騒音 | (社)日本音響学会提案の道路交通騒音の予測モデル (ASJ RTN-Model 2008) |
走行ルート沿道4地点 | 工事の実施に伴う影響が最大になる時期 |
|
【存在・供用】 廃棄物の搬入 |
道路交通騒音 | (社)日本音響学会提案の道路交通騒音の予測モデル (ASJ RTN-Model 2008) |
走行ルート沿道4地点 | 存在・供用に伴う影響が最大になる時期 |
1) 工事の実施
ア 建設作業騒音
予測結果
建設機械の稼動に伴い発生する騒音(以下,「建設作業騒音」という。)について,その影響の程度を予測しました。
予測時期は,建設機械の月別稼動台数,作業配置等から,多くの建設機械が敷地境界に近接して稼動する時期として,平成27年(2015年)11月頃,建設作業中の騒音パワーレベルの合成値が最大になる時期として,平成28年(2016年)9月頃を設定しました。
予測の結果,敷地境界における建設作業騒音は,想定した建設機械が全て同時に稼働した場合,平成27年(2015年)11月頃が81dB,平成28年(2016年)9月頃が69dBと予測されました。
環境保全措置
予測結果では,建設機械の稼動に伴う建設作業騒音が,敷地境界の最大地点で特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準値(=85dB)を下回っているものの,周辺環境への影響を回避又は低減することを目的として,表2-3に示す環境保全措置を実施します。
|
環境保全措置 |
環境保全措置の効果 |
|---|---|
| 工事工程の調整 | 建設機械の集中稼働を避けることにより,騒音の発生が抑制されます。 |
| 建設機械の運転管理の徹底 | 建設機械の定期的な点検整備の実施,高負荷・空ぶかし運転等の回避を徹底することにより,騒音の発生が抑制されます。 |
| 低騒音型建設機械の積極的な採用 | 最新の技術動向を踏まえ,より騒音の発生の小さい低騒音型建設機械を積極的に採用することにより,騒音の発生が抑制されます。 |
評価
回避又は低減に係る評価
本事業の実施にあたっては,環境保全措置を実施し,建設機械の稼動に伴う建設作業騒音の影響を低減する計画としており,事業計画地周辺への影響を回避又は低減した計画であると評価します。
基準又は目標との整合性の検討
建設作業騒音が最大となる時期の予測結果は,平成27年(2015年)11月頃が81dB,平成28年(2016年)9月頃が69dBであり,いずれの時期においても,特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準値(=85dB)を満たしており,基準との整合は図られていると評価します。
イ 道路交通騒音
予測結果
工事関係車両等の走行に伴い発生する騒音について,その影響の程度を予測しました。
走行ルート沿道における予測対象交通量は,「1.大気質」(表1-5参照)と同様の設定をしています。
予測時期は,現時点で想定される事業計画において,工事関係車両の走行台数の合計が最大になる平成27年(2015年)11月頃としました。
また,予測時間帯は,騒音に係る環境基準の時間区分(昼間6時~22時,夜間22時~翌朝6時)のうち,工事関係車両の走行時間帯(8時台~17時台)を含む昼間の時間帯(6時~22時)を対象としました。
予測地点は,工事関係車両の走行による沿道住民の生活環境に対する影響を把握するため,沿道に住居が存在する地点(現地調査を実施した4地点)としました。
また,予測位置は車線数に応じて以下のとおりとしました。
- No.1(1車線):敷地境界(地上高さ1.2m)
- No.2~4(2車線):敷地境界及び敷地境界から15m地点(地上高さ1.2m)注)
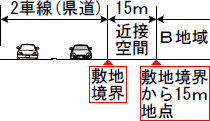
注)走行ルートのうち,2車線道路では,「道路の敷地の境界線から15mまでの範囲(近接空間)」と「道路の敷地の境界線から15m離れた地点以遠の地域(B地域)」で環境基準が異なるため,予測評価はそれぞれの地域の中で最も騒音影響が大きい地点(敷地境界及び敷地境界から15m地点)で行います。
道路交通騒音の予測結果は,図2-3のとおりです。
予測結果によると,敷地境界では62~65dBの範囲内となり,敷地境界から15m離れた地点では58~60dBの範囲内となりました。
(なお,敷地境界の予測結果の平成21年(2009年)現況の値は,平成21年(2009年)の現地調査結果です。
また,敷地境界から15m離れた地点の予測結果の平成21年(2009年)現況の値は,計算値です。)
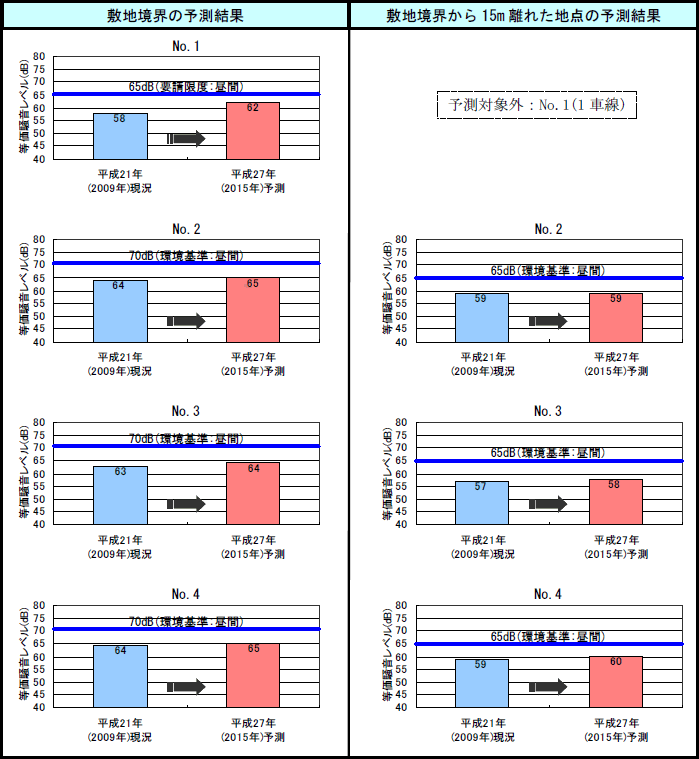
環境保全措置
予測結果では,工事関係車両の走行に伴う道路交通騒音が,いずれの地点も要請限度(No.1地点:65dB)又は環境基準(No.2~4地点:70dB)は下回っているものの,沿道環境への影響を回避又は低減することを目的として,表2-4に示す環境保全措置を実施します。
|
環境保全措置 |
環境保全措置の効果 |
|---|---|
| 工事工程の調整 | 工事工程を調整し,工事関係車両の平準化を図ることにより,工事関係車両による騒音の発生が抑制されます。 |
| 工事関係車両の運転管理の徹底 | 工事関係車両の定期的な点検整備の実施,法定速度の遵守,高負荷運転及び空ぶかし・急発進運転の回避等を徹底することにより,騒音の発生が抑制されます。 |
| 工事関係者の乗合い通勤 | 工事関係者が乗合いで通勤することにより,工事関係車両(小型車)の台数が減少され騒音の発生が抑制されます。 |
評価
回避又は低減に係る評価
本事業の実施にあたっては,環境保全措置を実施し,工事関係車両の走行に伴う道路交通騒音の影響を低減する計画としており,沿道環境への影響を回避又は低減した計画であると評価します。
基準又は目標との整合性の検討
図2-3のとおり,工事の実施中の昼間の時間帯(6時~22時)の等価騒音レベルは,いずれの地点においても,設定した要請限度及び環境基準を満たしており,基準又は目標との整合は図られていると評価します。
「No.1地点について」(図2-3参照)
- 走行ルート沿道のNo.2~4地点は,環境基準(近接空間の特例値)が適用されます。
- しかしながら,No.1地点については,現況において1車線道路であり,近接空間の特例値が適用されないことから,No.1地点の予測に当たっては,1車線道路における要請限度を適用することとしました。要請限度は,近接空間の特例値よりも数値的に厳しいことから,適切な評価基準であると考えられます。
事後調査
交通量予測の不確実性が大きいことから,環境保全措置の効果を検証するために事後調査を実施します。事後調査の概要は,表2-5のとおりです。
|
調査項目 |
調査内容 |
実施主体 |
|---|---|---|
| 工事関係車両の走行に伴う道路交通騒音 | 工事関係車両台数が最大となる時期に道路交通騒音の調査を行います。
|
事業者 |
(2) 存在・供用
ア 道路交通騒音
予測結果
廃棄物搬入車両等及び工事関係車両(第2期工事)の走行に伴い発生する騒音について,その影響の程度を予測しました。走行ルート沿道における予測対象交通量は,「1.大気質」(表1-8参照)と同様の設定をしています。
予測時期は,現時点で想定される事業計画において,廃棄物搬入車両等及び工事関係車両(第2期工事)の走行台数の合計が最大になる平成37年(2025年)12月頃としました。また,予測時間帯は,騒音に係る環境基準の時間区分(昼間6時~22時,夜間22時~翌朝6時)のうち,廃棄物の搬入時間帯(8時台~16時台)を含む昼間の時間帯(6時~22時)を対象としました。
道路交通騒音の予測結果は,図2-4のとおりです。予測結果によると,敷地境界では65~67dBの範囲内となり,敷地境界から15m離れた地点では59~61dBの範囲内となりました。
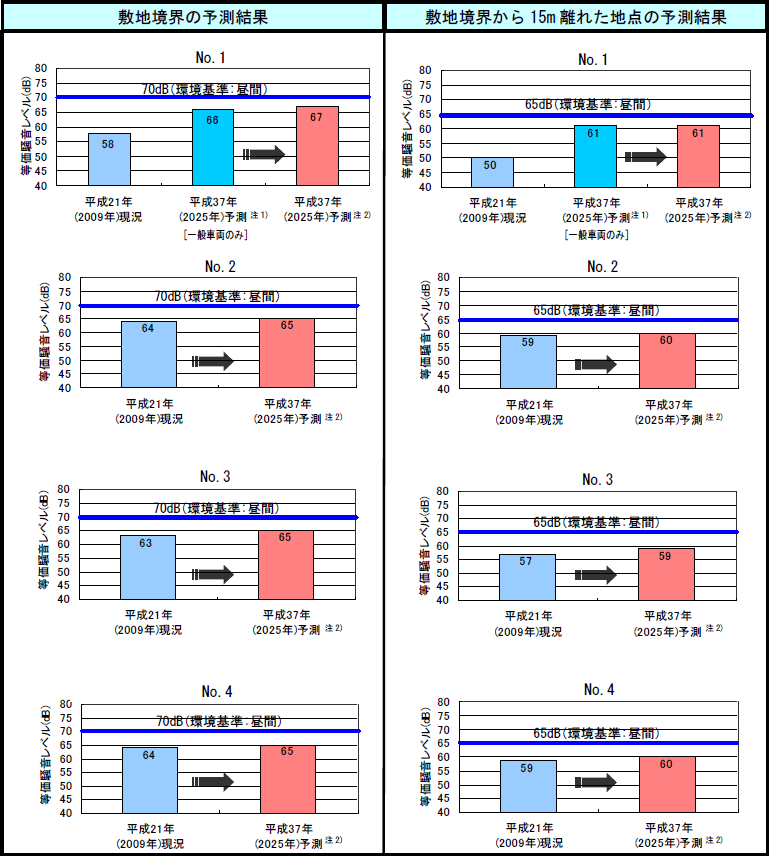
- 注1)No.1地点の平成37年(2025年)予測注1)は,一般車両のみの予測結果です。
- 注2)No.1~4地点の平成37年(2025年)予測注2)は,一般車両と廃棄物搬入車両及び工事関係車両による予測結果です。
環境保全措置
予測結果では,廃棄物搬入車両等及び工事関係車両(第2期工事)の走行に伴う道路交通騒音が,いずれの地点も環境基準(70dB)を下回っているものの,沿道環境への影響を回避又は低減することを目的として,表2-6に示す環境保全措置を実施します。
|
環境保全措置 |
環境保全措置の効果 |
|---|---|
| 工事工程の調整 | 工事工程を調整し,工事関係車両の平準化を図ることにより,工事関係車両による騒音の発生が抑制されます。 |
| 廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の運転管理の徹底 | 廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の定期的な点検整備の実施,法定速度の遵守,高負荷運転及び空ぶかし・急発進運転の回避等を徹底することにより,騒音の発生が抑制されます。 |
| 工事関係者の乗合い通勤 | 工事関係者が乗合いで通勤することにより,工事関係車両(小型車)の台数が減少され騒音の発生が抑制されます。 |
評価
回避又は低減に係る評価
本事業の実施にあたっては,環境保全措置を実施し,廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の走行に伴う道路交通騒音の影響を低減する計画としており,沿道環境への影響を回避又は低減した計画であると評価します。
基準又は目標との整合性の検討
図2-4のとおり,存在・供用時の昼間の時間帯(6時~22時)の等価騒音レベルは,いずれの地点においても,環境基準を満たしており,基準との整合は図られていると評価します。
「No.1地点について」(図2-4参照)
No.1地点は,存在・供用時は道路改良により2車線道路に拡幅する計画です。このため,評価基準は,存在・供用時は2車線道路になることを踏まえて環境基準を適用することとしました。
事後調査
交通量予測の不確実性が大きいことから,環境保全措置の効果を検証するために事後調査を実施します。事後調査の概要は,表2-7のとおりです。
|
調査項目 |
調査内容 |
実施主体 |
|---|---|---|
| 廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の走行に伴う道路交通騒音 | 廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の合計台数が最大となる時期に道路交通騒音の調査を行います。
|
事業者 |
関連情報
- 環境影響評価審査会開催結果(恵下埋立地(仮称)整備事業 第1回:平成20年12月16日)
- 環境影響評価審査会開催結果(恵下埋立地(仮称)整備事業 第2回:平成21年3月18日)
- 環境影響評価審査会開催結果(恵下埋立地(仮称)整備事業 第3回:平成22年12月20日)
- 環境影響評価審査会開催結果(恵下埋立地(仮称)整備事業 第4回:平成23年1月31日)
- 環境影響評価審査会開催結果(恵下埋立地(仮称)整備事業 第5回及び(仮称)JR可部線電化延伸事業 第2回:平成23年3月11日)
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
環境局 環境保全課 環境管理係
電話:082-504-2097/ファクス:082-504-2229
メールアドレス:[email protected]
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境局環境保全課 環境管理係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2097(環境管理係)
ファクス:082-504-2229
[email protected]
