今日からみんな「下水道博士」!
下水道のことに興味を持ってくれてありがとう!
ここでは【下水道管】【マンホール】【微生物】【下水道の歴史】について、詳しく説明するよ。
1)下水道管
下水道管の工事現場に入ってみよう!

地下30mの下水道工事現場に入ってみましょう。
よく見ると、下には人が見えます。

あまりにも深いので、専用エレベーターで地下へ降りていきます。

ついに地下30mに到着!
大雨が降ったときに、ここは街が水びたしにならないために、雨水を流すための下水道管です。
直径は4、5mもあります。工事中の下水道管には、人が歩くための道をつけたり、荷物を運ぶためレールをつけたりしています。
完成後にはそれらはすべて外され、雨水が流れます。

トンネル工事の最先端はこうなっています!
シールドマシンが見えてきました。シールドマシンは地中に穴を掘っていくための機械で、一日に5mから20m位掘り進んでいきます。日本のシールドマシンの技術は世界中で評価されています。
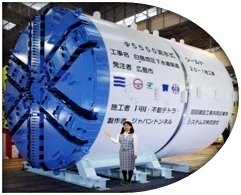
人間が作ったモグラマシーンの「シールドマシン」
下に女性の方が見えますか?
となると、このトンネルの大きさは‥。
知ってる?

広島市に埋まっている下水道管を掘り起こして、1本の管にすると、約6000kmになります。6000kmはおよそ日本からハワイまでの距離になります。
2)マンホールのイロイロ
広島市内には、約22万個のマンホールがあります。

ただ今、下水道管を点検中!
マンホールは下水道管がこわれたり詰まった時に、掃除や点検、修理をするためにあります。

マンホールのふたを開け、高圧洗浄車のホースをマンホールの中に入れて清掃します。

(1)油のこびりついた下水道管!
こんなになると、下水も流れにくくなります。

(2)マンホールからホースを入れて、いきおいよく水を出し、汚れを吹き飛ばして掃除しています。

(3)清掃すると、こんなにキレイになりました。
3)デザインマンホール
広島市には、デザインされたマンホールがこんなにたくさんあります。

もみじ
広島城周辺にあります。

折り
広島駅周辺にあります。

かもめ
広島港周辺にあります。

カープ坊や
マツダスタジアム周辺にあります。

かよこバス
横川駅周辺にあります。

西国街道
猿猴橋から中央通りまでの西国街道にあります。
近くに行ったときは探してみてね!
知ってる?

マンホールのフタは、どれも丸いことを知っていますか?
フタが丸いのには理由があって、丸いと、どの方向に向けても下に落ちることがないからです。もしマンホールのフタが三角や四角だと、向きが違うとずれて落ちることがあるのです。
4)知って楽しい微生物

下水をキレイにする微生物は約200種類。その中で大きく3種類【細菌類・原生動物・後生動物】に分けることができます。
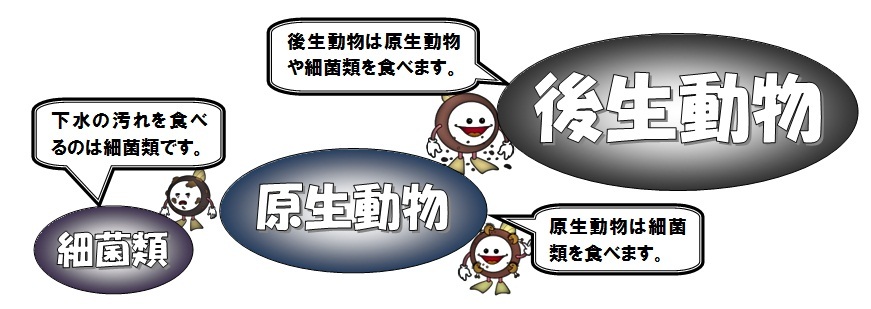
細菌類
大きさ
0.01mm以下
細胞の数
一つだけ
主な微生物

原生動物
大きさ
0.01mm~0.4mm位
細胞の数
一つだけ
主な微生物




後生動物
大きさ
0.1mm以上
細胞の数
たくさん
主な微生物




※すべての生物は細胞により構成されていることは知っているよね!そして、私たち人間は60兆個の細胞があるんだ。
知ってる?
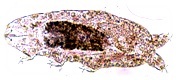
下水をキレイにする微生物の中で一番大きくて長生きなのは、「クマムシ」です。「クマムシ」は足が8本あり動物のような動きをします。タマゴも生みます。
「クマムシ」は地上最強の微生物といわれています。
5)下水道の歴史
下水道はいつ、どのようにして出来たのか見ていきましょう。
世界の下水道の歴史
- 紀元前
5000年頃 - 古代メソポタミア文明の都市に下水道ができる
※地図-1 - 紀元前
2000年頃 - インダス川流域にモヘンジョダロの下水道ができる
※地図-2 - 1347年
-
ヨーロッパでペストが流行
- 1370年
- パリに初めての下水道ができる
※地図-3 - 1728年
- ベルサイユ宮殿に最初の水洗トイレを設置
※地図-3 - 1848年
- ヨーロッパでコレラが流行
- 1856年
- ロンドンで下水道工事がはじまる
※地図-4 - 1914年
- 活性汚泥法の最初の処理場がイギリスにできる
※地図-4

日本の下水道の歴史
- 奈良時代
- 平城京に下水きょ(排水溝)ができる
※地図-1 - 鎌倉時代
- し尿の農業処理がはじまる
- 1583年
- 大阪・城下町に背割下水をつくる(太閤下水)
※地図-2 - 1879年
- コレラの流行
- 1884年
- 東京・神田に下水道管ができる
※地図-3 - 1900年
- 下水道法が制定される
- 1922年
- 東京三河島汚水処分工場が運転 開始
※地図-3 - 1930年
- 名古屋で日本最初の活性汚泥法による処理が始まる。
※地図-4
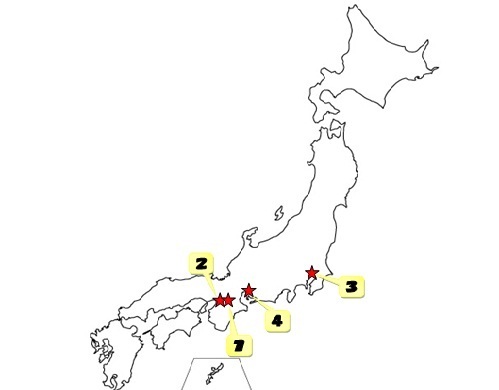
広島市の下水道の歴史
- 1908年
- 下水道事業に着手
- 1945年
- 原爆により下水道事業の大半が被災する
- 1946年
- 戦後ゼロから下水道事業に着手
- 1961年
- 千田下水処理場の稼動
※地図-1 - 1967年
- 千田下水処理場で活性汚泥法による処理が始まる
- 2007年
- 下水処理場を【水資源再生センター】に名称変更
- 2009年
- 公共下水道人口普及率が93%に達する
- 2012年
- 西部水資源再生センターで汚泥燃料化事業開始
- 2017年
- 公共下水道人口普及率が95%に達する
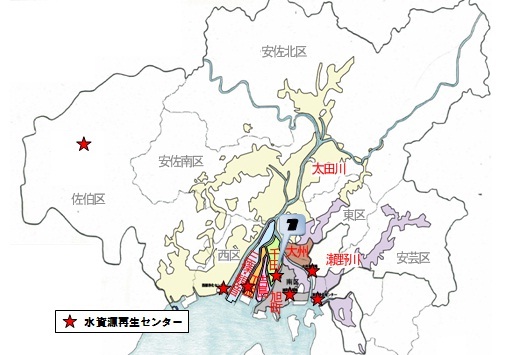
知ってる?

花の都と呼ばれるフランスのパリは、古い歴史のある都市ですが、他の諸都市と同様、1400年頃には道路に周辺の窓から汚物が投げ捨てられていたそうです。
このページに関するお問い合わせ先
下水道局経営企画課庶務係
電話:082-504-2265/ファクス:082-504-2429
メールアドレス:[email protected]
このページに関するお問い合わせ
下水道局経営企画課 庶務係広報担当
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 12階
電話:082-504-2265(庶務係広報担当)
ファクス:082-504-2429
[email protected]
