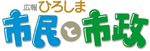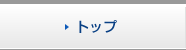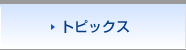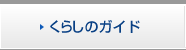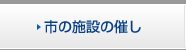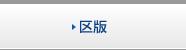カンピロバクター食中毒にご注意を

■生で食べない
■菌を付けない
■しっかり加熱
湿度・気温が高くなるこの時期、細菌性の食中毒が起こりやすくなります。加熱や洗浄、消毒などで食中毒を予防しましょう。
バーベキューだけじゃない!
家庭でも安全な調理を
家庭や飲食店でもカンピロバクター食中毒は発生します。焼肉や家庭調理の際には十分注意しましょう
「新鮮だから安全」ではありません!
カンピロバクターは、主に鶏、豚、牛などの腸管内にいる細菌です。食肉に加工する際に細菌が付くため、鮮度にかかわらず、食肉には高い確率でカンピロバクターが付いています。市保健所の調査では、市販の鶏肉の約8割から、この細菌が検出されています。「新鮮なお肉だから安全」は間違いです。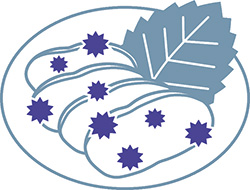
まれに重症化することも
カンピロバクターに感染すると、2〜7日後に下痢や腹痛、発熱などを発症し、回復まで1週間程度かかります。子どもや高齢者などは重症化することも。抵抗力の弱い人は特に注意しましょう。細菌性食中毒の中で発生件数1位
カンピロバクターによる食中毒は例年多く発生しています。原因となりやすいのは、生や半生の鶏肉料理(刺し身、たたきなど)、加熱不足の焼き鳥、焼肉など。肉は、表面だけでなく、中心部まで十分加熱しましょう。二次汚染に注意
包丁やまな板は肉と野菜で使い分け、生肉に触れた調理器具や手指はしっかり洗浄・消毒。調理器具や手指を介してサラダなど他の食品に細菌が付着しないよう気をつけましょう。市ホームページはこちら

予防のポイント
肉を生や生焼けで食べない
■「鳥のたたき」、「鳥刺し」などを食べないようにする
菌を付けない
■生肉を扱うトングや箸、食べる箸をそれぞれ用意し、使い分ける
■生で食べる野菜や調理済みの食品に肉汁が付かないよう、分けて保管する
■生肉を扱った後の手指や調理器具は、しっかり洗浄する

しっかり加熱する
■肉は中心部の色が変わるまでしっかり加熱する(中心部を75度以上で1分以上)
■ホルモンやミンチ肉、タレ付き肉は内部に細菌が入り込んでいることがあるので要注意
肉を生や生焼けで食べない
■「鳥のたたき」、「鳥刺し」などを食べないようにする
菌を付けない
■生肉を扱うトングや箸、食べる箸をそれぞれ用意し、使い分ける
■生で食べる野菜や調理済みの食品に肉汁が付かないよう、分けて保管する
■生肉を扱った後の手指や調理器具は、しっかり洗浄する

しっかり加熱する
■肉は中心部の色が変わるまでしっかり加熱する(中心部を75度以上で1分以上)
■ホルモンやミンチ肉、タレ付き肉は内部に細菌が入り込んでいることがあるので要注意


この記事は、主に上記SDGs(エスディージーズ)のゴールの達成に役立つものです。
【SDGs…持続可能な開発目標】
◆問い合わせ先:食品保健課(電話241-7434、ファクス241-2567)