認知症の人を地域で見守る
認知症サポーターになりませんか

写真【1】
Q.認知症サポーターって?
認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人や家族などに対してできる範囲でサポートする人のこと。「認知症サポーター養成講座」の修了者です。
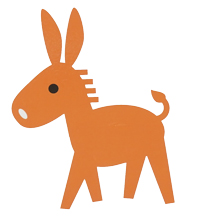
市は、「認知症サポーター」を増やすことで、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指しています。
日常生活や職場で支援「認知症サポーター」
認知症サポーターは特別なことをする人ではありません。日常生活や職場で、次のようなサポートをお願いしています。
- 認知症の人や家族を温かい目で見守る
- 家族や友達などに講座で学んだ知識を伝える
- 地域の集まりなどに認知症の人を誘う
- 店の中や屋外などで困った様子の人がいたら優しく声を掛ける
- レジで支払いに時間がかかっている人に「ゆっくりで大丈夫ですよ」と声を掛ける
一つの声掛けが命を救うことも
地域で高齢者の見守り活動を行っている「黄金山つながりネット・ボランティアバンクみどり」の皆さん(下写真)は、認知症サポーター養成講座を受講後、近くの公園で認知症の人への声掛けの練習を行いました(写真【1】)。梶川美貴恵さん(同写真左)は「認知症の人が行方不明になるケースが増えていて、一つの声掛けが命を救うこともあります。日頃の見守りに生かしたいですね」と話します。


写真【2】ユアーズLIVI(リビ)本通店(中区)
▲AEDの設置や補助犬の同伴可などと同様に、日常で目にすることが増えています
学校や事業所でも開催しています
昨年度、庚午中学校(西区)では1年生240人が受講。生徒たちは「相手を尊重して接することが大切だと分かった」などと感想を述べていました。
従業員68人が受講したスーパーマーケットは、サポーターの存在を知らせるステッカーを店頭に掲示(写真【2】)。佐藤店長(下写真)は「安心して買い物を楽しんでほしい」と笑顔で話します。

佐藤店長
認知症の人は市内に4万人弱
認知症は、病気の名前ではなく、状態のこと。脳の病気や脳に影響を及ぼす体の病気により、これまで培ってきた知識や技術が失われ、社会生活に支障を来すようになった状態をいいます。市内の認知症高齢者(日常生活自立度が一定以下の人)の人数は、令和5年9月末時点で約3万7500人です。
認知症サポーター養成講座
-
受講修了者には、認知症サポーターの証しとして、「認知症サポーターカード」お渡しします。受講した企業などには掲示用ステッカー(写真【2】)をお渡しします。
- 対象
市内の地域団体や企業に所属するおおむね5人以上のグループ - 内容
認知症の主な症状、関わり方、認知症の人の気持ち、認知症の人と接するときの心構え、認知症サポーターの役割など。約90分 - 申し込み方法
希望日のおおむね2カ月前までに、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターか区地域支えあい課(右記)へ。地域包括支援センターの一覧は、市ホームページで
市ホームページ
- 問い合わせ先
区地域支えあい課
| 区 | 電話 | ファクス |
|---|---|---|
| 中 | 504-2586 | 504-2175 |
| 東 | 568-7731 | 568-7790 |
| 南 | 250-4109 | 254-4030 |
| 西 | 294-6289 | 294-6113 |
| 安佐南 | 831-4568 | 870-2255 |
| 安佐北 | 819-0587 | 819-0602 |
| 安芸 | 821-2810 | 821-2832 |
| 佐伯 | 943-9728 | 923-1611 |

この記事は、主に上記SDGs(エスディージーズ)のゴールの達成に役立つものです。
【SDGs…持続可能な開発目標】
◆問い合わせ先:地域包括ケア推進課(電話504-2648、ファクス504-2136)
