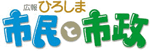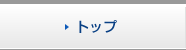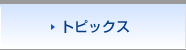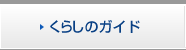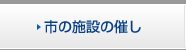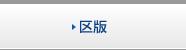メンター交流を始めてみませんか
楽しみも成長も二人で

人生の先輩である大人(メンター)が、1対1の関係で子どもの発達段階などに応じて継続的・定期的に交流。信頼関係を築きながら、子どもの成長を支援する「青少年支援メンター制度」を紹介します。
交流内容などは話し合って決定を
メンターと利用者の相性などを十分考慮し、市がマッチングを行って、ペアを決め、職員立ち合いの顔合わせを経て交流を開始します。交流日時や内容は決まったものではなく、メンターと子ども(利用者)・保護者で相談して決定します。交流回数/時間 原則として、放課後や休日を利用して、月に1・2回から週に1・2回/1回当たり2時間程度
交流場所 原則として、子どもの自宅(近くの公民館や公園などでも)。また出かけることもOK
交流内容 基本的には子どもがやりたいことをメンターが支援。料理やスポーツをする、動物園やスポーツ観戦に出かける、宿題をする、悩みの相談をする、メンターの特技を生かすなど
研修やサポートが充実
市はメンターへの研修や交流状況の確認など、きめ細かなサポートを行いますので、双方安心して交流できます。
◆メンターと利用者を募集
【申し込み条件】●メンター 子どもに対する深い愛情と理解を持ち、責任を持ってメンターとしての役割を果たせる人(高校生を除く18歳以上。資格などは問いませんが、面接や審査があります)
●利用者 市内に在住か市立学校に在籍している小・中学生
申し込み方法など詳しくは、市ホームページで。

report(リポート)
「何、しよっか?」と決めるのも楽しみ
満ち足りた時間を共有

「焼けたかな?」「まだじゃない?」。明るい日が差し込む公民館の調理室。この日は、メンター制度の利用者・森島小枝(もりしまさえ)さん(メイン写真右・中学校2年生)の希望で、メンターの瀬戸帆風(せとほのか)さん(同左・大学4年生)とチョコブラウニー作りをしました。材料を用意し、レシピを見ながら調理。手を動かしながらも森島さんの体育祭の話で盛り上がり、終始笑顔の二人です。
交流を始めて7カ月。森島さんは「瀬戸さんは年の離れたお友達のよう。家族に話さないことでも何でも話せます」とはにかみます。瀬戸さんは「自分が悩んでいた時期に周りに助けられた恩返しになればと心理士を目指しています。思春期の頃を思い出し、小枝ちゃんに接しています」。月に1回ほど、二人でお菓子作りや映画鑑賞、おしゃべりなどを楽しんでいるそうです。
この日、特に森島さんが楽しみにしていたのが、瀬戸さんの愛犬との散歩。動物好きの二人は、散歩をしながら、リラックスした表情を見せます。交流時は、いつも充実した時間が流れているようです。

次の交流が楽しみ
「メンターは相手によってさまざまな活動ができ、自分の成長にもつながります。ボランティアを探していてこの制度を知りましたが、もっと広まって、いろいろな交流が増えるといいですね。両親にも勧めているんですよ」と瀬戸さん。森島さんは「将来、私もメンターになりたい」と話します。
「次回は、スポーツセンターでバウンドテニスをしたいね」と、顔を見合わせて約束していました。
「何、しよっか?」と決めるのも楽しみ
満ち足りた時間を共有

「焼けたかな?」「まだじゃない?」。明るい日が差し込む公民館の調理室。この日は、メンター制度の利用者・森島小枝(もりしまさえ)さん(メイン写真右・中学校2年生)の希望で、メンターの瀬戸帆風(せとほのか)さん(同左・大学4年生)とチョコブラウニー作りをしました。材料を用意し、レシピを見ながら調理。手を動かしながらも森島さんの体育祭の話で盛り上がり、終始笑顔の二人です。
交流を始めて7カ月。森島さんは「瀬戸さんは年の離れたお友達のよう。家族に話さないことでも何でも話せます」とはにかみます。瀬戸さんは「自分が悩んでいた時期に周りに助けられた恩返しになればと心理士を目指しています。思春期の頃を思い出し、小枝ちゃんに接しています」。月に1回ほど、二人でお菓子作りや映画鑑賞、おしゃべりなどを楽しんでいるそうです。
この日、特に森島さんが楽しみにしていたのが、瀬戸さんの愛犬との散歩。動物好きの二人は、散歩をしながら、リラックスした表情を見せます。交流時は、いつも充実した時間が流れているようです。

次の交流が楽しみ
「メンターは相手によってさまざまな活動ができ、自分の成長にもつながります。ボランティアを探していてこの制度を知りましたが、もっと広まって、いろいろな交流が増えるといいですね。両親にも勧めているんですよ」と瀬戸さん。森島さんは「将来、私もメンターになりたい」と話します。
「次回は、スポーツセンターでバウンドテニスをしたいね」と、顔を見合わせて約束していました。

この記事は、主に上記SDGs(エスディージーズ)のゴールの達成に役立つものです。
【SDGs…持続可能な開発目標】
◆問い合わせ先:こども青少年支援部(電話504-2261、ファクス504-2727)