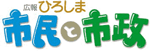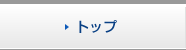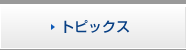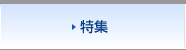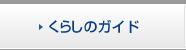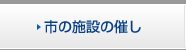特集/わたしたちのまちづくりを紹介します!
新たな協力体制づくりに取り組む地域における事例
1.七つのネットで担い手発掘
東区早稲田学区団体の垣根を越える仕組みづくり

各地域団体がより連携して地域活動に取り組むための仕組みづくりとして、地域課題のテーマごとに七つのネットワーク(ネット)を作っています。
各ネットを構成する委員は、町内会やPTAなどの既存の団体から、幅広い年代の人を選出。団体の垣根を越えて、課題の解決を検討しています。

仕事と子育てを両立しながら地域活動を行う高田久美子さん(上写真)は「7年前に子育て支援をテーマとしたネットに初めて参加したときは、地域でさまざまな取り組みが行われていることに驚きました。知らず知らずのうちに地域活動に足を踏み入れ、今も活動を続けています。各ネットには若い世代の参加者も多く、自由な発想で協議が行われていますよ」と話します。
ネットで決まったアイデアは、各種団体が実施します。それにより、実施団体の活性化にもつながっています。ネットに参加した若者の中には、これをきっかけに地域の各種団体で活躍するようになる人も多く、担い手の発掘の場としても機能しています。
2.ICT※を使った地域活動
南区比治山学区コロナ禍でも地域で交流するために
新型コロナウイルス感染症の影響でさまざまな地域活動が制限される中、オンラインによる活動を模索し、市立大学へ協力を仰ぎました。地域住民の健康維持や、交流機会をつくることが目的です。
ICTを活用した健康体操

同大学や地域関係者との協議を経て、まずはオンラインでの健康体操を行うことに。各個人が家庭で使用できるスマートフォンやタブレット端末への配信など、人と人が顔を見ながら体操できる環境を目指して、現在試験的に実施しながら、取り組みを進めています。

集会所でのオンラインによる体操に参加した尾西幸春さん(上写真)は「ICTって何? という感じでしたが、実際に体験してみると、思ったよりも簡単に行うことができたので、徐々にやってみようという気持ちになってきました。本格稼働が待ち遠しいです」と話します。
今後は、地域全体でICTを活用しながら、地域の活性化を目指し、さまざまな活動を進めていきます。
※ICTとは
インフォメーション・アンド・コミュニケーション・テクノロジーの略。情報通信技術
3. 住民の笑顔が見える関係づくり
西区大芝学区キッチンカーがつなぐ住民の笑顔

安全・安心で住み続けたいと思える地域を目指して、「安心」と「元気」をキーワードに活動しています。
住民に「元気」を届けるために走り回っているのが、手作り弁当を乗せたキッチンカー。キッチンカーは、各集会所、神社、地域に貢献したいという申し出があった企業の駐車場の他、各種イベント会場などを回っています。安価でおいしい弁当を提供することで、住民同士の交流の場を作ると同時に笑顔を届けています。

この弁当を作っているのは、大芝地区社会福祉協議会の支え合い事業部が設立した「にんじんの会」。会の名称には「人」が「参」加するという思いが込められています。同会(上写真)は「住民の皆さんが楽しく笑顔になってほしいという願いを込めて作っています。実際に話をしながら弁当を提供しているので、多くの住民と知り合える機会になっています」と話します。
コロナ禍でも、キッチンカーでの弁当配布を通じて、お互いの顔が見える交流の機会をつくり、住民同士で支え合いができるまちづくりを進めていきます。
4.住民主体の活動拠点づくり
安佐南区毘沙門台学区地域で作り上げた活動拠点
平成28年6月にオープンした「毘沙門台ふれあいセンター絆」。解体予定の市の施設を同学区が市から無償で借り上げ、募金や企業からの協賛金を得てリフォームし、地域の活動・交流拠点にしました。
住民が気軽に立ち寄れる拠点づくり

この場所は、一人暮らしの高齢者などが日中気軽に過ごすことができる、交流・集いの場となっています。また、子どもたちの放課後の居場所としても活用されています。その他、地域住民が趣味や得意なことを生かして、そば打ちやパソコン、子育て、英会話の教室、モーニング(食事会)などさまざまな活動を主催するなど、幅広い世代の人が気軽に立ち寄れる場所でもあります。
この場所で週2回、親子スペース「まるまゆ」(上写真)を運営する森川万理子さん(下写真)は「地域の皆さんに見守っていただき、まるで実家のような安心感があります。親子だけでなく、多世代で交流することができる貴重な場所です」と話します。

開設した年度は年間延べ約5,000人程度の利用でしたが、地域住民による活動が年々広がりを見せ、現在では年間延べ約1万2000人が訪れています。
5.廃校を活用したにぎわいづくり
安佐北区飯室(旧久地)学区廃校でのイベントの開催


久地地区では人口減少が進み、令和2年3月には久地小学校が廃校となりました。地域では廃校を活用したにぎわいづくりの取り組みを進めています。


昨年11月には、地元産野菜や加工品などの販売、ステージイベントを行う「久地収穫祭」を開催(上写真)。今年の3月には、安佐地区の四つの神楽団による「あさ神楽祭り」を開催する予定です。
地区連合自治会会長の中村三郎さん(写真右)と地区社会福祉協議会会長の藤田富男さん(同左)は「子どもから高齢者まで幅広い世代の人が楽しめるイベントを同校で開催して、久地地区の新たな魅力を発信し、若者が活躍できるまちづくりを進めていきたい」と話します。
今後、同地区では、連合自治会と地区社会福祉協議会が中心となって、地域のさまざまな団体などと連携し、同地区をさらに活性化させるための同校の活用方法などについて検討を進めていく予定です。
6.「テーマ型」コミュニティで課題解決
安芸区みどり坂学区みどり坂のコミュニティ
同学区は、平成9年に入居が始まった比較的新しい団地にあるため、現役世代が多く、まちの高齢化率は5%程度と他地域と比べて低い状況です(市内平均26%程度)。また、他の地域に見られるような地域に根差した団体が少ないことから、「テーマ型」のコミュニティづくりに取り組んでいます。
「テーマ型」のコミュニティの実現へ 「テーマ型」のコミュニティは、町内会などの既存のコミュニティが吸い上げたまちの課題をテーマとして、これを解決するために各地域団体や有志の個人・団体が集まり、自分たちで考え、活動に取り組んでいく仕組みです。
同学区で「みどり坂にゃんこクラブ」(下写真)を発足させ、地域猫活動をしている岩田佳美さん(同前列右)は「団地内の野良猫が増えてきており、ふん尿被害などの問題を解決するために、同クラブを発足しました。小学生を含む幅広い年齢層のメンバーで、地域の人の理解を得ながら、餌やりのルールを決めるなどの活動を行っています」と話します。
さまざまな参加者が、自分の興味があるテーマに取り組みながら、まちの活性化を図っています。