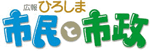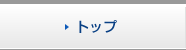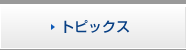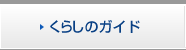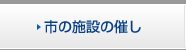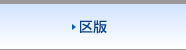神楽

写真:第13回あさきた神楽発表会の合同演目「八岐大蛇」
区では、市内で最も多い14の神楽団が活動しています。
今回は、区の誇る伝統芸能である神楽について紹介します。
神楽とは
神楽は、日本古来の伝統芸能で、神の前で行う鎮魂(ちんこん)・五穀豊穣・厄災の払拭・豊作のお礼のための歌舞(かぶ)がその発祥といわれています。今でも秋祭りでは、地域の幸せを祈る舞として神楽が奉納されています。神楽は、日本各地に伝承されていますが、その形はさまざまです。区内では、高陽地区の6団体が儀式的な性質の強い「十二(じゅうに)神祇(じんぎ)神楽(かぐら)」を、白木・可部・安佐地区の8団体が演劇性の高い「旧舞(きゅうまい)、新(しん)舞(まい)」と呼ばれる神楽を継承しています。

区内の神楽団体分布図
十二神祇神楽
十二神祇神楽は、旧安芸国南部の広島市・廿日市市・大竹市に伝わる伝統的な舞です。神楽本来の目的や形式の古さをよくとどめているといわれており、その価値が評価されています。また、演目の幕間に吹火(ふきび)や傘火(かさび)をするのが特徴の一つでもあります。10M以上にもなる火の粉が勢いよく吹き上げる「吹火」や、勢いよく回転しながら火の粉を吹き出し傘のように見える「傘火」は壮観です。

くむら神楽保存会による「世鬼(せき)の舞」

くむら神楽保存会による「吹火」
旧舞、新舞
旧舞、新舞は、どちらも芸北神楽と呼ばれるもので、島根県の石見地方が源流といわれています。新舞は、戦後、連合国軍総司令部(GHQ)により神楽が規制される中で創作されたもので、神道色を薄めた娯楽性の高い神楽です。これに対し、戦前の芸北神楽が旧舞と呼ばれるようになりました。演劇性が高いことから人気を集め、定期公演や大会が開かれるほか、各種イベントでも上演されています。

飯室神楽団による「塵倫(じんりん)」(旧舞)

宮崎神楽団による「紅葉狩(もみじがり)」(新舞)
区内で活動中の神楽部を紹介
県立可部高等学校の神楽部では、1年生6人、2年生6人、3年生4人の計16人の部員が日々楽しみながら練習に励み、昨年7月には、安芸高田市で開かれた神楽甲子園に出場しました。神楽部の部長で2年生の石浦稜也(いしうら りょうや)さんに話を聞きました。

◎神楽を始めたきっかけ
中学校2年生のときに神楽を始めました。もともと神楽を見たりまねをしたりするのが好きで、神楽をやっていた友達に誘われ、地域の神楽団の子ども神楽に参加したのがきっかけです。
◎可部高校神楽部の強み
地域の神楽団とは一味違った高校生らしい元気のある公演をすることです。
◎神楽をする上で意識していること
神楽は一人ではできないので、周りと協力し、コミュニケーションをとりながらやっています。また、神楽の伝統や舞い方などを崩さないようにすることを意識しています。
◎区民の皆さんにメッセージ
コロナ禍以前の生活が戻ることはまだまだ難しいと思いますが、地域の皆さんの前で神楽を披露できるときに向けて、精一杯練習を頑張ります。
神楽を盛り上げよう
現在、コロナ禍で公演の中止が余儀なくされ、神楽団の運営も厳しい状態です。公演などが再開された際には、鑑賞に行き、神楽の魅力を感じてみてはいかがでしょうか。区の誇る伝統芸能である神楽をみんなで盛り上げ、後世に引き継いでいきましょう。◆問い合わせ先:地域起こし推進課(電話819-3904、ファクス815-3906)