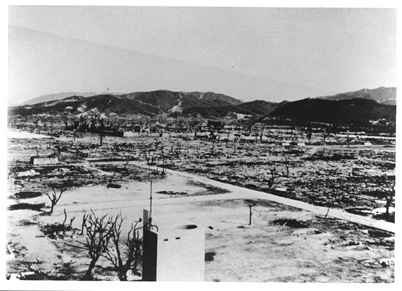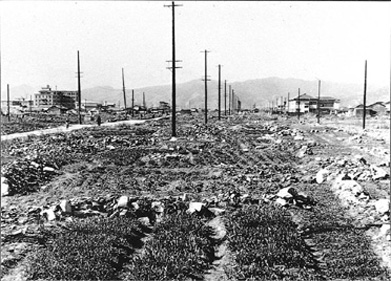|
�s�ړI�t
��1���@�@���̖@���́A�P�v�̕��a�𐽎��Ɏ������悤�Ƃ��闝�z�̏ے��Ƃ��āA�L���s�a�L�O�s�s�Ƃ��Č��݂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B
|
|
�i����j
�@���̖@���̖ړI�́A�L���s�𑼂̐�Гs�s�Ɠ����悤�ɒP�ɕ������邾���łȂ��A�P�v���a���ے����镽�a�L�O�s�s�Ƃ��Č��݂��Ă������Ƃ������̂ł��B
|
|
�@
|
|
�s�v��y�ю��Ɓt
��2���@�@�L�����a�L�O�s�s�����݂�����ʓs�s�v��i�ȉ����a�L�O�s�s���v��Ƃ����B�j�́A�s�s�v��@�i���a43�N�@����100���j��4���1���ɒ�߂�s�s�v��̊O�A�P�v�̕��a���L�O���ׂ��{�݂��̑����a�L�O�s�s�Ƃ��Ăӂ��킵�������I�{�݂̌v����܂ނ��̂Ƃ���B
2�@�L�����a�L�O�s�s�����݂�����ʓs�s�v�掖�Ɓi�ȉ����a�L�O�s�s���ݎ��ƂƂ����B�j�́A���a�L�O�s�s���v������{������̂Ƃ���B
|
|
(����j
�@���H�A�����A�������ȂǓs�s�̊�ՂƂȂ�����{�݂��͂��߁A�y�n�̎g�����⌚���̌��ĕ��̃��[���ȂǁA�܂��Â���ɕK�v�ȑ����̂��Ƃ���́A���ׂĂ̓s�s�ɋ��ʂ��āA�s�s�v��@�ɂ���߂��Ă��܂��B
�@�������A���̓s�s�v��@�ɂ́A�P�v�̕��a���ے����镽�a�L�O�s�s�ɂӂ��킵���v��܂Ŋ܂݂���Ă��܂���B���̂��߁A���ʂ̓s�s�v��̂ق��ɁA���a�s�s�ɂӂ��킵�������I�{�݂�u���a���L�O����{�݁v�Ȃǂ��܂߂邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���܂����B
|
|

|

|
|
��Ќ�̒����n��
1946�i���a21�j�N
|
���݂̒����n��
�i�L�O�{�݁u���a�L�O�����v�j
|
|
|
�@
|
|
�s���Ƃ̉����t
��3���@�@���y�ђn�������c�̂̊W���@�ւ́A���a�L�O�s�s���ݎ��Ƃ��A��1���̖ړI�ɂĂ炵�d�v�ȈӋ`�������Ƃ��l���A���̎��Ƃ̑��i�Ɗ����Ƃɂł������̉�����^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
|
(����j
�@�{�@�ł́A�P�v�̕��a�𐽎��Ɏ������悤�Ƃ��闝�z�̏ے��Ƃ��āA�L���s�a�L�O�s�s�Ƃ��Č��݂��邽�߂ɁA�W���@�ւ͂ł������̉������A�ϋɓI�ɍs��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ���Ă��܂��B
�{�@�Ɋ�Â��W���@�ւ���̉����̎���͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
(1)���ɂ�镽�a�勴�E�����a�勴�̐���
(2)�����{��s�L���x�X�̍L���s�w��d�v�������ւ̎w��ɔ����A2000�i����12�j�N7�����A���{��s���瓯�����A�y�n���s�ɖ����ݗ^����Ă��܂��i�����A���̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ���_�ŁA���{��s�͖{�@�̓K�p�ɂ��A�s�ɏ��^������j�����肵�Ă��܂��j
�i3�j���ɕ⏕���̕⏕���̈����グ�i1950�i���a25�j�N�x����1955�i���a30�j�N�x�j
�i4�j���ɕ⏕���̕ʘg�z���i1944�A1945�i���a19�A20�j�N�ɑ��̐�Гs�s�Ƃ͕ʘg�ōL���s�ɔz���j
�����̂���(1)�A(2)�ɂ��ẮA�u�L�����a�L�O�s�s���ݖ@�̊֘A�{�݁v�̃R�[�i�[�ŏڂ����Љ�Ă��܂��B
|
|
�@
|
|
�s���ʂ̏����t
��4���@�@���́A���a�L�O�s�s���ݎ��Ƃ̗p�ɋ����邽�߂ɕK�v������ƔF�߂�ꍇ�ɂ����ẮA���L���Y�@�i���a23�N�@����73���j��28���̋K��ɂ�����炸�A���̎��Ƃ̎��s�ɗv�����p�S��������c�̂ɑ��A���ʍ��Y�����^���邱�Ƃ��ł���B
|
|
�i����j
�@�������L���Ă���y�n�Ȃǂ̍��Y�́A�ʏ�A���L���Y�@�Œn�������c�̂������ŏ���邱�Ƃ͍���ɂȂ��Ă��܂����A���R�p�n���̕��ʍ��Y�́A�{�@�ɂ��A���a�L�O�s�s�����݂��邽�߂ɍ����K�v�ƔF�߂��ꍇ�ɁA���肤���邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���Ă��܂��B
�{�@�Ɋ�Â����R�p�n���̕��ʍ��Y�̏��^����͈ȉ��̕\�̂Ƃ���ł��B
|
�p �r
��
|
�{�݂̓��e
|
���^�y�n�ʐρi�u�j
|
|
����{��
|
�����E�����E�F�i���E�g���̊e���w�Z�A
�]�g�E��t�E�����E��i�ꕔ�j�̊e���w�Z�A������w�Z
|
146,888.26
|
|
�����{��
|
�L���s�����̋��c���O�X�����݂̎{��
�@
|
171,153.39
|
|
�����{��
|
�����厙������
���֓���n�Α���
|
1,513.44
|
|
�ی��E�q���{��
|
�s���a�@�E�����|������
�@
|
25,974.91
|
|
��
�v
|
�@
|
345,530.00
|
���j���L���Y�̖������^��1967�i���a42�j�N�̊�����w�Z���Ō�ł��B
��̕\�̈ꕔ�ɂ��ẮA�u�L�����a�L�O�s�s���ݖ@�̊֘A�{�݁v�̃R�[�i�[�ł��Љ�Ă��܂��B
|
|
�@
|
|
�s�t
��5���@�@���a�L�O�s�s���ݎ��Ƃ̎��s�҂́A���̎��Ƃ����₩�Ɋ�������悤�ɓw�߁A���Ȃ��Ƃ��U�ӌ����ƂɁA���y��ʑ�b�ɂ��̐i������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
2�@���t������b�́A���N�P��ɑ��A���a�L�O�s�s���ݎ��Ƃ̏���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
|
�i����j
�@�{�@�����A�L���s�ɂ�����s�s�v�掖�Ƃ͂��ׂĕ��a�L�O�s�s���ݎ��ƂƂ��čs���Ă��܂��B���̎��Ƃ̎��т͖��N����֕��Ă���A2012�i����24�j�N�x���܂ł́A�X�H���ƁA���������ƁA�y�n��搮�����ƁA�������Ƃ����킹���v���Ɣ�́A��2��8,080���~�ɒB���Ă��܂��B
|
|
�@
|
|
�s�L���s���̐Ӗ��t
��6���@�@�L���s�̎s���́A���̏Z���̋��͋y�ъW���@�ւ̉����ɂ��A�L�����a�L�O�s�s���������邱�Ƃɂ��āA�s�f�̊��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
|
|
�i����j
�@�L���s���́A�L���s���Ȃǂ̋��͂ɂ��A�L���s�a�L�O�s�s�Ƃ��Č��݂��邱�ƂɁA����܂ʓw�͂����邱�Ƃ��`���t�����Ă��܂��B
�{�@�Ɋ�Â��Z�����̑�����̉�������͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
- �s�Ή����i�{���ɂ����đ�X�I�ȋ��؉^�����s��ꂽ�B�Ȃ��ł��A1957�A1958�i���a32�A33�j�N��2���N�ɂ͌����̎s�������獇�v��6,000�{�̋�����ꂽ�B���̋��؉^���ɂ�蕽�a��ʂ�͗ΖL���Ȍi�ς�L���铹�H�ƂȂ����B
- 1967�i���a42�j�N�A1990�i����2�j�N�̉ߋ��Q��ɂ킽��A�s������̊�t���ɂ�茴���h�[���̕ۑ��H�����s�����B
- �L���s�����ꌚ�ݔ�ɂ��āC�@��P���̖ړI�ɑ������a�L�O�s�s�ɂӂ��킵���X�|�[�c�̓a�������݂�������̊m�ۂɎ������|�̎s���ƌ��ݔ��t�҂Ƃ̊o���Ȃǂɂ��A�n�����E����1956�`1958�i���a31�`33�j�N�x�Ɋ�t�����B
- ���a�L�O�������̌�����n�����E�ɂ��1955�i���a30�j�N�Ɍ��݂���A��t�����B
- �L���̎��������̂��߂ɂƂ����č����T���[���X�s����L�����l���̊�t�����A1952�i���a27�j�N�Ɏ����}���ق����݂��ꂽ�B
- ���a�s�s�̌��݂ɖ𗧂ĂĂق����Ƃ����s����c�̓��̊�t���́A����܂ł��A�܂����݂������Ă���A���E���a���i�̂��߂̊e��̎��Ƃ����{���Ă���B
���̂����A1.�`3.�ɂ��ẮA�u�L�����a�L�O�s�s���ݖ@�̊֘A�{�݁v�̃R�[�i�[�ŏڂ����Љ�Ă��܂��B
|
|
�@
|
|
�s�@���̓K�p�t
��7���@�@���a�L�O�s�s���v��y�ѕ��a�L�O�s�s���ݎ��Ƃɂ��ẮA���̖@���ɓ��ʂ̒肪����ꍇ�������O�A�s�s�v��@�̓K�p��������̂Ƃ���B
|
|
�i����j
�@�ʏ�A�s�s�ɕK�v�ȓ��H�A�����A�������Ȃǂ́A�s�s�v��@�Ƃ����@���ɂ��v�悵�A���݂�����̂ł����A���a�L�O�s�s�ɂ��ẮA�s�s�v��@�y�і{�@�ɂ���Čv�悵�A���݂�����̂Ƃ���Ă��܂��B
|